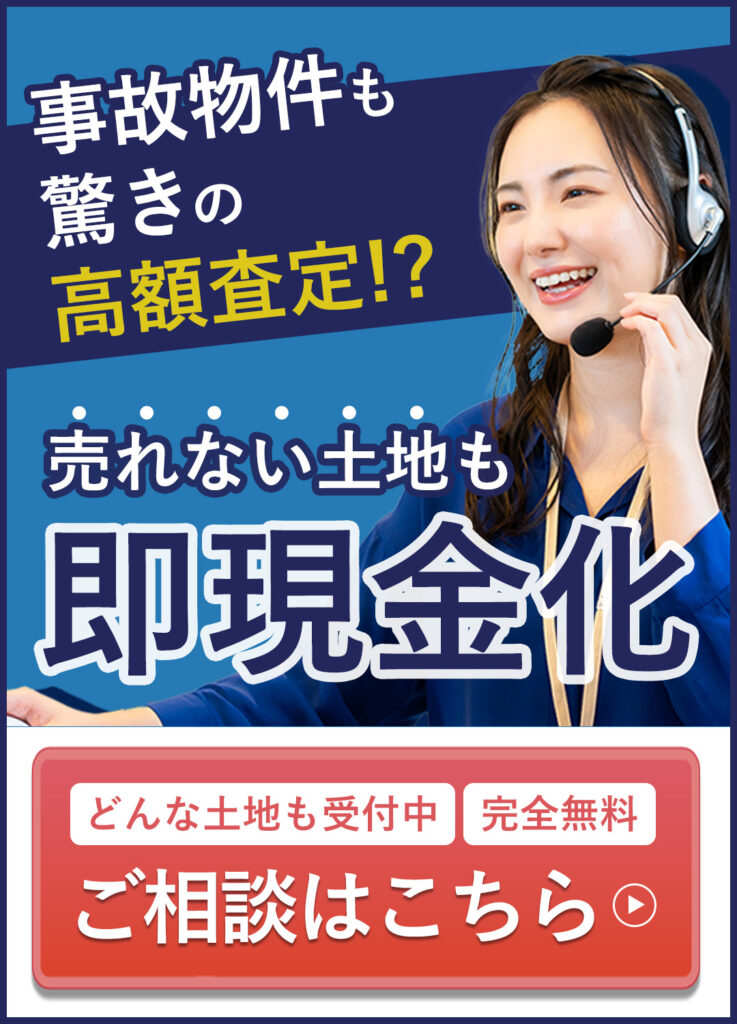実家の相続でやってはいけないのはこれ!相続で失敗しないための注意点
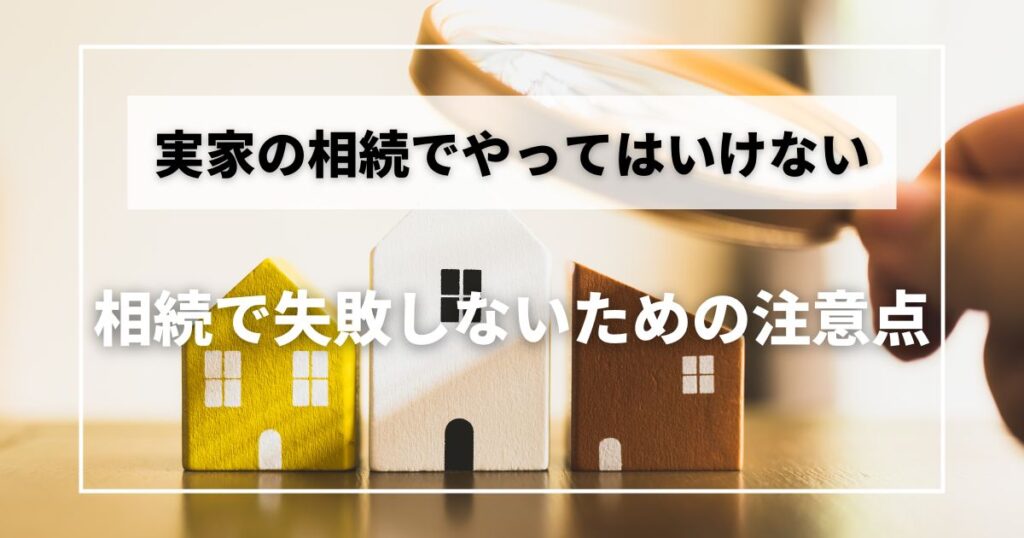
実家に住んでいる両親が高齢化したり他界すると相続が発生することになりますが、土地・建物の活用方法や相続人が決まっていなければそのまま放置し空き家になってしまうこともあります。
また所有者が複数となる登記をしてしまうと管理の仕方や売却するかどうかでトラブルが発生しやすくなることから、ただ相続登記すれば問題が解決するわけでもありません。
親族全員が納得した内容で遺産分割をしなければ、相続後に親族の関係が悪化することもありますので、注意が必要です。
このことからも実家を活用する方法や相続後の売却については親族全員で協議する必要があり、一番納得できる方法を選ぶことが大切です。
この記事では実家を相続する際の注意点や相続税を節税する方法など、相続対策のポイントについて解説します。
実家を相続する予定があるものの誰が相続するのか決まっていない人は、参考にしてください。
- 実家の相続でやってはいけないこと
- 相続した実家した場合の対策
- 相続トラブルを避ける方法
空き家パスは、相続など権利関係が複雑な不動産の買取も得意としています。司法書士などの専門家と連携して進めることが可能です。相続した実家が空き家になる、売却したいがなかなか売れない、などお困りの方はぜひご相談ください。ご相談・査定は完全無料です。
目次
実家の相続でやってはいけないこと
不動産は相続財産の中でも高額になりやすく、相続時に親族間で揉めることも少なくありません。
そのため面倒事として放置したり取り急ぎ相続人全員の共有名義にするケースもありますが、安易な相続はトラブルの原因になります。
だからといって実家を誰も利用することなく空き家のまま放置すると多くのリスクを抱えてしまいますので、相続関係の協議はなるべく早い段階で実施しておくことをおすすめします。
この章では実家を相続する際にやってはいけないことを6つ紹介しますので、相続開始の前にチェックしてください。
複数の兄弟などで共有名義にする
相続は法定相続に合わせて財産を分割するのが一般的ですが、不動産は分割できないためトラブルになることがあります。
たとえば実家の評価額が2,000万円で現金1,000万円の遺産を兄弟3人で分ける場合、実家を相続した兄弟は持分を超えていることになります。
この場合は他の兄弟に500万円ずつ支払うことで持分通りの遺産分割となりますが、現金がなければできない方法です。
このようなケースでは兄弟全員が実家を所有する共有名義を選択することもあります。
共有名義にすることで兄弟間で現金や現物の授受をせずともスムーズに財産を分けられるため、検討しておきたい選択肢といえます。
しかし共有名義にしてしまうと利用や処分について全員の合意が必要となり、自分だけの判断で売却や賃貸経営ができなくなってしまいます。
さらに実家の掃除や老朽化した場合の維持費や倒壊した場合の撤去費用の支払いで揉めることもありますので、兄弟で共有名義にする方法はなるべく避けることをおすすめします。
相続登記をしないで放置する
実家を相続し所有権を得るためには相続登記が必要です。
相続登記をしなければ第三者が実家を名義変更してしまった場合、利用や売却ができなくなってしまいます。
このようなトラブルに巻き込まれると裁判によって真なる所有権を訴えることになりますが、時間がかかる上に所有権を奪還できないことも少なくありません。
そのため実家を相続した場合は速やかに相続登記することが大切です。
なお、相続登記は2024年4月1日より義務化されており、相続を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
2024年3月31日以前に相続した場合であっても3年以内に相続登記する必要があり、万が一期日内に登記しなかった場合は10万円以下の過料が科せられる可能性もあるため、注意が必要です。
【参考サイト:東京法務局】
相続したあと実家を放置する
実家を相続したものの利用することがなく、管理しないまま放置してしまうことも少なくありません。
家屋の掃除や草むしりといった管理は手間がかかるからといって実家を放置してしまうと老朽化が進んでしまい、倒壊する可能性が高くなってしまいます。
このように管理が不十分な家屋は国や自治体によって「特定空き家」や「管理不全空き家」に認定されてしまうことがあり、認定されると固定資産税の税制優遇撤廃や行政代執行による強制解体が実施される可能性があります。
特定空き家や管理不全空き家については、以下のいずれかの状態にあると認められた場合に該当します。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
- 適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態
これ以外にも建物や塀の倒壊によって隣地が被害を受けた場合、損害賠償を請求されることも考えられます。
実家を空き家のまま放置することにはこのようなデメリットを抱えることになるため、面倒でも実家は管理すべきといえます。
【参考サイト:固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置】
相続した実家を活用方法を決めず解体して更地にする
特定空き家の認定を避けたり管理の手間を減らすために実家を早々に解体する人もいますが、具体的な土地の活用方法を決めないまま家屋を解体することはおすすめできません。
なぜなら解体してしまうと家屋を活用できなくなってしまい、将来実家を利用することも中古戸建として売却することもできなくなってしまうからです。
解体費用もかかってしまう上に実家を解体したことについて親族間のトラブルが起きることもありますので、解体については慎重に判断する必要があります。
さらに実家を解体してしまうと住宅用地の税制優遇を受けられなくなってしまい、固定資産税が高くなってしまいます。
このことからも、実家を解体する明確な理由がなければそのまま管理しておくことがポイントです。
相続した直後に実家を売却する
相続税を軽減させる特例に「小規模宅地等の特例」があり、相続した住宅用地で300㎡以下の部分については評価額を8割減にすることができます。
節税効果が高いため必ず利用したい特例ですが、利用するためには相続開始時から相続税申告期限まで相続した不動産を保有している必要があります。
相続申告期限は相続発生を知った翌日から10ヶ月以内となっているため、相続してすぐに売却してしまうとこの特例を利用できません。
そのため相続税を支払った上で実家を相続する場合は、売却する前に相続税の申告と納税を行い、その上で売却することが重要です。
ただし相続税を支払った上で相続取得してから3年以内に売却した場合、売却時の譲渡所得税を軽減できるといった特例もあります。
このことからもどのタイミングで売却するのが最適なのか、利用できる特例を把握した上で検討することが大切です。
【参考サイト:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁】
【参考サイト:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁】
専門家に相談せずに進める
不動産会社や司法書士、税理士といった専門家は相続の相談を日常的に受けていることから、相続内容に沿ったアドバイスを受けることができます。
特に相続税や遺産分割協議については不慣れな法定相続人も多く、勘違いした状態で進めてしまい損をするケースも少なくありません。
場合によっては相続税が追徴課税されてしまい、親族間のトラブルになってしまいます。
このような失敗を避けるためにも、利用できる特例や相続税が少なくなる遺産分割について専門家に相談することがポイントです。
無料相談やネットでの問い合わせなど気軽に相談できるサービスが公開されていますので、相続の発生が分かった時点で家の近くに相談できるサービスがないか調べておくことをおすすめします。
相続した実家はどうするべき?
相続した実家を放置するのは得策ではないとしても、具体的な活用方法が分からないという所有者も多いです。
利用する予定がないまま手間と費用をかけて管理することはストレスにもなるため、相続した実家をどうすべきかなるべく早く決める必要があります。
この章では実家を相続した場合の対処方法を紹介します。
相続した人が住む
実家を自己利用することで家賃を抑え、日常的に効率よく管理することができます。
固定資産税や都市計画税といった維持費も空き家の状態では無駄な出費となってしまいますが、自分が住むのであれば必要経費として納得することも可能です。
家屋は人が住むことでメンテナンスされ資産価値を維持できることから、将来売却する予定があったとしても居住することはおすすめです。
賃貸に出す
生活拠点が実家から離れている場合は住むことが難しくなってしまいますが、その場合は賃貸に出して誰かに住んでもらうという方法があります。
賃貸は入居者が家をキレイな状態に保ってくれるだけでなく、家賃を使って維持費を軽減できるというメリットもあります。
立地が良ければ空室になる期間も短くなりますので、賃貸物件として活用できるかどうか不動産会社に相談し決めることがポイントです。
ただし賃貸に出した場合は設備の修繕費用をオーナーが負担することになり、入居者の使い方によっては家屋が傷んでしまうこともあり得ます。
また将来売却しようとしてもすぐに売り出すことができなくなってしまい、さらに譲渡所得税を軽減させられる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」も使えなくなります。
そのため賃貸に出すべきかどうかは、慎重に判断することをおすすめします。
【参考サイト:No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁】
土地活用をする
実家の立地が良ければ建物を解体して更地にし、マンションを建てたり駐車場として活用する方法があります。
誰も住まない状態で放置するよりも収益性が高く、資産価値も維持することができます。
入居者や駐車場の利用者を検証する必要がある、田舎だと利用者がおらずかえってマイナスになるなど土地活用にはいくつかハードルがありますが、土地の資産価値が高い場合に有効な対処法といえます。
売却する
維持費や管理の手間を省きたいのであれば、売却がおすすめです。
不動産の売却には「仲介」と「買取」があり、次のような違いがあります。
| 売却方法 | 買い手 | 販売期間 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 仲介 | 一般人 | 売買契約締結する時期まで | 自由に決められる |
| 買取 | 不動産会社 | ほとんどなし | 買取査定額 |
仲介は不動産会社に販売を依頼し、買い手を探してもらう売却方法です。
売却価格や条件を売主が決められるというメリットがある一方、販売期間が長期化する可能性があるというデメリットもあります。
一方、買取は不動産会社が提示する買取査定額がそのまま買取額になってしまいますが、販売期間はほとんどなく価格に合意すればすぐに売買契約を締結することができます。
また買取の場合は解体費用や測量費、残置物の撤去費用も不要となりますので、手間をかけずスピーディーに売却したい人に向いている方法です。
相続後のトラブルを避けるにはどうしたらいい?
実家をトラブルなく相続するためには相続開始前に準備しておくポイントがあり、実家の相続人だけでなく親族全員が知っておく必要があります。
相続関係のトラブルは親族間の関係が悪化する可能性が高く、相続がきっかけで親族と疎遠になってしまうケースも少なくありません。
遺族全員がこれまで通りの関係を維持できるようにするためにも、この章で解説するポイントは押さえておくことをおすすめします。
遺言書を作成しておく
実家の相続人を遺言書に明記することで親族間の話し合いをスムーズに進めることができますので、おすすめの方法です。
遺言書には一般的に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があり、次のような違いがあります。
| 遺言書の種類 | 内容 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 遺言者本人が自由に作成できる遺言書。内容に決まりがないため手軽に作成することができ保管場所の制限もないが、不備が発生しやすく無効になることも多い。 |
| 公正証書遺言 | 遺言者本人が公証人と証人2名に対して口頭で内容を告げ、公証人が文書にまとめて遺言者と証人に読み聞かせて作成する遺言書。専門家が内容を精査した上で公証役場に原本が保管されるため信頼性が高く、紛失する心配もない。 |
| 秘密証書遺言 | 公正役場で作成する遺言書。公正証書遺言と違い公証人は内容を精査することができないため、不備が発生し無効になることがある。 |
生前贈与をする
生前贈与は実家の現所有者を贈与者、所有権を得る人を受贈者として贈与契約書を締結し、所有権を移転する方法です。
生前贈与をすることで相続を待たずして実家を継承することができるため、特定の法定相続人に実家の所有権を確実に移転させたい場合に有効な方法といえます。
ただし生前贈与によって本来の持分を超えた財産を取得することになった場合は他の相続人に対して金銭などを授受する必要があることから、生前贈与は親族全員が納得している状態で進めることをおすすめします。
なお、生前贈与の場合は贈与税が発生し、直系尊属からの贈与と直系尊属以外からの贈与で次のように税額が異なります。
直系尊属からの生前贈与
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 無し |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円を超える | 55% | 640万円 |
直系尊属以外からの生前贈与
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 無し |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円を超える | 55% | 400万円 |
たとえば評価額5,000万円の実家を生前贈与する場合、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税は2,100万円ですが、直系尊属以外の場合は2,350万円です。
このことからも実家の所有者との関係性は贈与税に大きく影響することが分かります。
【参考サイト:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁】
遺産分割協議をする
遺産分割協議とは実家を含めた全ての相続財産に対して法定相続人の分割内容を協議し、協議書にまとめる作業のことです。
法定相続人が持つ持分割合に合わせて財産を分割することになり、全員が合意した内容を協議書に記載し、全員が署名押印することで完成します。
全員が納得する内容で合意させられることからトラブルが起きにくくなり、相続財産と法定相続人が多い場合は必ず作成することが大切です。
ただし相続財産は不動産や預貯金だけでなく、株や証券といった分割が難しい遺産も含まれます。
さらに生前に被相続人を介護していた場合は「寄与分」という権利が発生し、遺産分割協議がまとまらないことも多いです。
そのため遺産分割協議を行う際には専門家に同席してもらい、法律上の問題点と権利を確認しながら進めることが重要といえます。
実家の活用方法を話し合っておく
実家の所有権を得たからといって他の親族が納得しない扱いをしてしまうと後からトラブルになりやすく、注意が必要です。
たとえば相続してすぐに実家を売却したり賃貸に出してしまうと、親族から反感を買うことがあります。
特に実家を解体して処分した場合は思い出の家屋がなくなることで親族がショックを受けることもあり、関係を悪化させないためにも実家の活用方法については事前に話し合っておくことでトラブル防止となります。
相続した実家を手放す方法は?
実家を有効活用することなく放置していると様々なリスクを抱えることになるため、親族全員が納得するのであれば手放すことを検討する必要もあります。
所有権を放棄すれば実家の管理から解放され、固定資産税や都市計画税の負担もなくなります。
そのため実家を活用しないことを決めた場合は、なるべく早く手放すことが大切です。
実家を手放す方法として「売却」と「国や自治体への寄付」があり、どちらにもメリットとデメリットがあります。
納得のいく形で実家を手放すためにも、この章で解説するそれぞれの特徴を押さえておくことをおすすめします。
最適なタイミングで売却する
実家の築年数がなるべく浅い時期に不動産会社へ売却を依頼し、建物がまだ新しい間に売却するのがポイントです。
不動産の査定額は建物面積や敷地面積、築年数が類似している成約事例をベースにして算出しますが、査定額は一番売れやすい価格帯として提示されます。
つまり、同じエリアで建物と敷地の面積が同じであれば、築年数が浅い方が資産価値が残っているとみなされ、査定額は高くなるといえます。
さらに築年数が浅く設備がそのまま使える状態であればその分高く売却できますので、経年劣化が進む前に売却することが大切です。
ただし数年後に区画整理事業や駅前の再開発事業がスタートするなど、土地の価値が上昇する可能性が高いイベントが発生する場合は公開時期を見極める必要があります。
こうした情報は自治体のHPで公開されている場合がほとんどですが、中には水面下で進められている計画もあります。
地元の不動産会社はこうした情報に詳しいので、売却を検討する際には複数の不動産会社に査定を依頼し、最適な売却タイミングはいつなのかチェックすることも重要です。
国や自治体に返す
実家を売却することが難しいと分かった場合、国や自治体に寄付することで所有権を手放すという方法もあります。
寄付はまず自治体の窓口に相談し、土地の調査を受けた上で寄付が可能か判断してもらう流れとなります。
そして寄付が可能だと判断されれば必要書類を窓口に提出し、受理されれば所有権移転の登記が行われます。
国や自治体は倒壊のリスクが高い家が増えることを問題視しており、放置されるよりは寄付を受けて管理した方がメリットがあると判断するケースも多いです。
そのため親族への贈与や売却が難しい場合には、寄付という選択肢を検討するのもおすすめです。
ただしどのような物件であっても寄付できるわけではなく、道が狭かったり再建築不可物件などは寄付の申請が否決になることもあります。
特に市街化調整区域の山奥にある物件は資産価値が低いため断られやすく、注意が必要です。
まとめ
実家を相続する場合は他の相続財産とのバランスを見極め、相続の持分割合に合わせて遺産分割した上で実家の所有権を取得することが重要です。
そのためには遺言書や遺産分割協議書の作成、生前贈与などが有効な手段といえます。
ただしどのような方法であっても親族が納得しなければ相続後にトラブルが起きることがあり、実家の活用方法や売却の可能性について親族間で十分に話し合う必要があります。
また相続が完了しても活用しなければ管理の手間と費用がかかり、長期間放置していると特定空き家に認定され様々なリスクを抱えることになります。
築年数が古くなると維持費も高くなり資産価値が下がってしまいますので、活用しない場合はなるべく早く手放すことをおすすめします。
空き家パスでは国や自治体が寄付を断った物件や訳あり物件などを積極的に買取しており、全国を対応エリアとしている買取専門業者です。
買取依頼は電話だけでなくメールやLINEでも受付しており、査定時の現地立会も不要ですので仕事の合間に買取査定を依頼することも可能です。
相続した実家の活用方法がなく維持費やメンテナンス工数で悩んでいる人は、空き家パスへお問い合わせください。