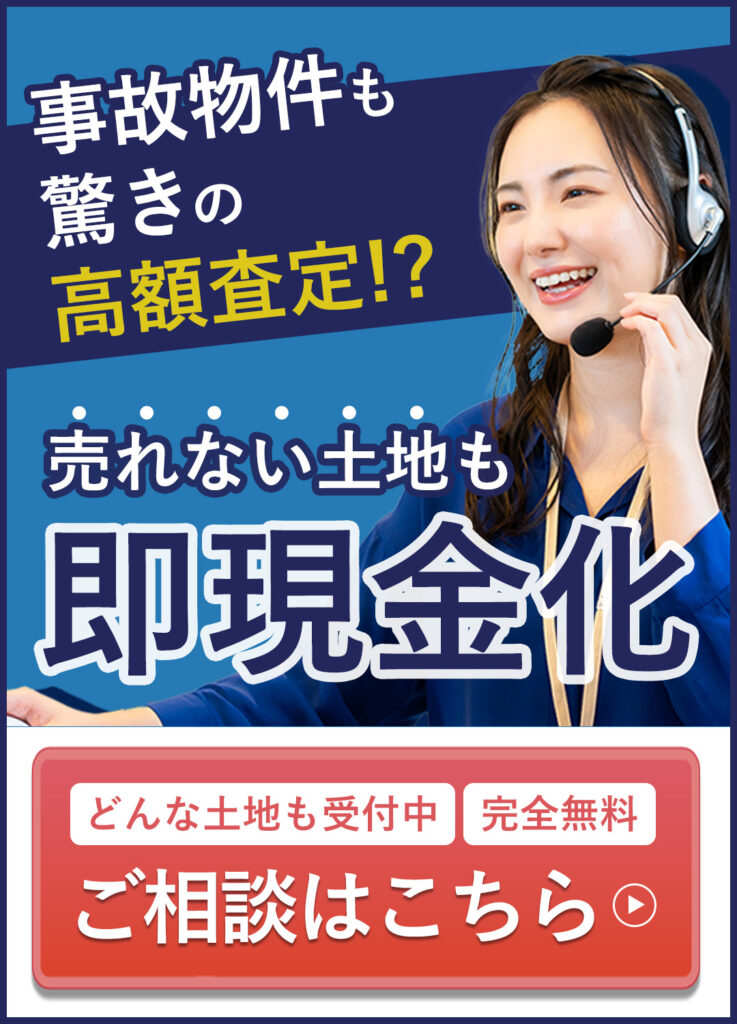長野の空き家補助金を解説ー解体・リフォームなどで活用!申請の流れや注意点も
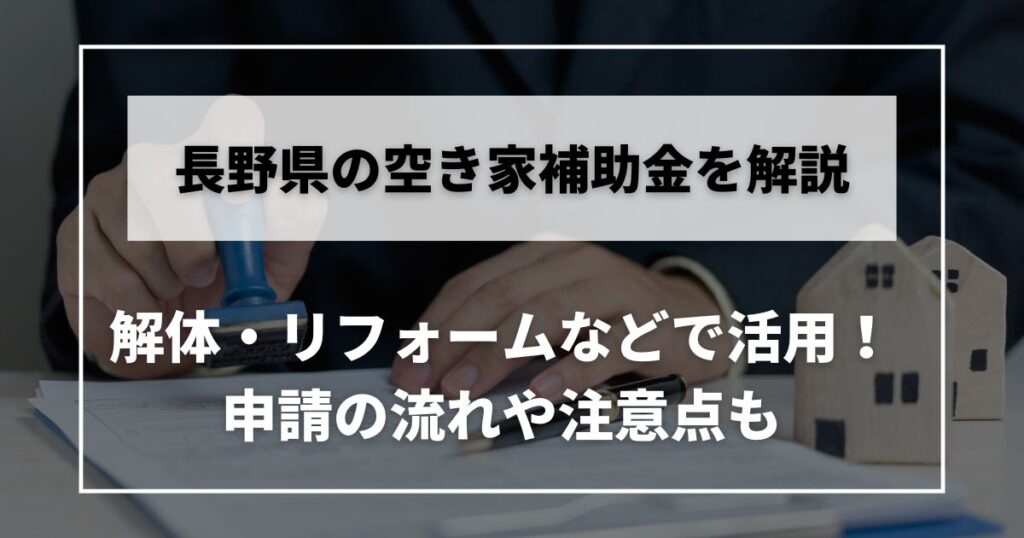
長野県でご実家や土地を相続された方、または将来相続を控えている方の中には、空き家の管理や処分に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
老朽化が進んだ空き家は、リフォームや解体に多額の費用がかかるため、「どうすればよいかわからない」と手を付けられないまま放置されているケースも少なくありません。
そんなときに活用できるのが、長野県や各市町村が提供している「空き家に関する補助金制度」です。空き家のリフォームや解体、家財の処分、購入などにかかる費用の一部を公的に支援してもらえるため、自己負担を抑えて空き家の利活用を進めることができます。
本記事では、長野県内で利用できる空き家関連の補助金制度を目的別に詳しく紹介するとともに、申請時の注意点や補助金では解決が難しい場合の対処法についても解説します。
- 長野県で空き家が増加している背景と放置によるリスク
- 空き家のリフォーム・解体・取得・家財整理に使える補助金制度の概要
- 市町村ごとに異なる補助金の上限額や条件の違い
- 補助金申請時に必要な書類や手続き上の注意点
- 補助金を使えない・使いにくいケースとその対処法
- 空き家を手放したいときの現実的な選択肢と相談先
補助金の活用とあわせて、空き家の売却も重要な選択肢のひとつです。
空き家パスは、相続不動産の買取を得意とする専門業者です。築古の物件や再建築不可物件、他社で断られた物件でも対応しており、相談・査定はすべて無料です。まずはお気軽にご相談ください。
長野県の空き家問題、現状は?
長野県は、全国的に見ても空き家の数が多く、空き家率も高水準で推移している地域のひとつです。
総務省統計局が公表した「令和5年住宅・土地統計調査(速報値)」によると、長野県の空き家率は20.0%に達しており、全国平均の13.8%を大きく上回っています。これは、県内のおよそ5戸に1戸が空き家である計算となり、空き家問題の深刻さがうかがえます。
空き家が増加している主な背景には、人口減少や高齢化の進行、都市部への若年層の流出といった地域構造の変化があります。特に、親の住まいを相続したものの、すでに都市部で生活していて戻る予定がないというケースも多く、放置空き家の増加に拍車をかけています。
また、長野県は別荘地や移住人気エリアとしても知られており、「長期不在のセカンドハウス」や「移住後の未活用住宅」といった形でも空き家が発生しやすい状況にあります。
こうした状況を受けて、長野県や各市町村では、空き家の利活用や除却を後押しする補助制度を整備し、地域の安全と景観を守るための対策を進めています。
【参考:令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果】
空き家問題解決策のひとつ「補助金制度」
空き家の増加が社会問題となる中、国や自治体では、空き家の解体やリフォーム、利活用を促進するために、さまざまな「補助金制度」を整備しています。
補助金制度は、老朽化した空き家の改修や撤去、取得、家財処分などにかかる費用の一部を公的に支援する制度で、所有者の経済的な負担を軽減し、空き家の放置を防ぐことを目的としています。
多くの制度では、申請後に交付決定を受けてから工事を開始する「後払い方式」が採用されており、事前に自治体への相談や申請手続きが必要です。
また、補助金には年度ごとの予算上限が設定されているため、申請が集中した場合は早期に受付が終了することもあります。
補助金の対象や条件は自治体によって異なりますが、活用方法によっては空き家の利活用や売却、管理コストの削減につながります。
長野県で使える空き家関連補助金
長野県内では、空き家の再生や除却を支援するため、多くの市町村が独自の補助制度を整備しています。補助対象はリフォーム・解体・取得・家財整理などに分かれており、物件の状態や活用目的に応じて使い分けることができます。
例えば、老朽化した空き家を住宅として活用する場合は「リフォーム補助」、危険な建物を取り壊す場合は「解体補助」、移住・定住を目的とした取得には「購入費補助」、残された家財道具の処分には「家財整理補助」が利用できます。
多くの補助制度は「空き家バンクへの登録」が前提であり、居住年数や年齢制限、市内業者の利用義務など、自治体ごとに条件が異なります。補助率や上限額にも差があるため、制度内容を比較して選ぶことが重要です。
次項では、目的別に長野県内で利用できる補助金制度の概要を紹介します。
空き家のリフォーム・改修に関する補助金
長野県内では、空き家を再活用するためのリフォームや改修工事に対して、各市町村が独自の補助制度を設けています。
対象となる工事は、老朽化した住宅の修繕や耐震補強、水回り設備の更新、断熱改修など多岐にわたります。特に空き家バンクに登録された物件や移住・定住を目的とする世帯への支援制度が充実しています。
制度によっては、市内業者による施工が必須となっていたり補助対象となる工事金額に下限が設定されている場合もあるため、事前の確認が欠かせません。
以下に、各市町村で実施されている主な補助制度を紹介します。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 安曇野市 | 安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金 | ・移住者: 最大60万円 ・市内在住者: 最大40万円 など属性により区分あり |
・市空き家バンク経由の物件購入/賃貸 ・3年~10年の居住義務 |
| 飯田市 | 飯田市空家改修補助金 | ・30万円 ・特定地区所在空き家は50万円(橋北、橋南、羽場、丸山、東野、下久堅、上久堅、千代、龍江、三穂、上村、南信濃) |
・売買/賃貸借契約の締結日から1年以内に改修工事を実施 ・改修工事は補助金交付決定後に着手 |
| 伊那市 |
空き家バンク登録促進補助金 空き家バンク利用促進補助金 |
・所有者/利用者: 最大75万円 | ・空き家バンク登録物件 ・利用者は45歳以下等の年齢要件あり ・自治会への加入 |
| 岡谷市 | 岡谷市空き家バンク移住・田舎ぐらし応援事業補助金 | ・改修費: 最大80万円 (工事費の1/2以内) ・移住奨励金: 20万円以上加算 |
・市外からの移住者が空き家バンク物件を購入 ・3年以上の居住 ・市内業者による工事 |
| 小諸市 | 小諸市空き家バンク登録・利用促進補助金 | ・基本: 最大5万円 (費用の1/2以内) ・市内事業者利用で最大10万円 |
・空き家バンク登録物件の所有者が対象 ・最低限の改修や家財道具の撤去が対象 |
| 佐久市 | 佐久市空き家再生等推進事業(活用事業) | 最大240万円 (対象経費の2/3以内) | ・改修後、地域活性化目的(体験宿泊施設等)で10年以上継続使用 |
| 塩尻市 | 塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金 | ・個人: 最大50万円 (経費の1/2) ・法人: 最大25万円 (経費の1/4) |
・1年以上空き家の戸建て住宅が対象 ・所有者申請は空き家バンク登録が必要 ・工事費10万円以上 |
| 須坂市 | 須坂市空き家活用事業補助金 | ・所有者/購入者: 最大40万円 (条件により50万円) ・転入購入者: 最大60万円 (条件により70万円) |
・空き家バンク登録物件 ・工事費20万円以上 ・市内施工業者利用 ・購入者は5年以上の活用/管理を誓約 |
| 千曲市 | 千曲市空き家バンクリフォーム補助金 | ・移住定住者: 最大100万円 | ・空き家バンク物件の購入者/賃借人が対象 ・移住者は20~55歳、10年以上の居住意思 ・工事費20万円以上 |
| 茅野市 | 茅野市空き家対策促進事業補助金(改修事業) | 最大25万円 (対象経費の10%) | ・1年以上空き家の物件 ・工事費100万円以上 ・改修後に利活用すること |
| 東御市 | 東御市空き家リフォーム補助金 | ・基本: 30万円 (経費の2/3) ・条件により最大80万円まで加算 |
・空き家バンク物件を購入した移住者対象 ・10年以上の居住を誓約 |
| 長野市 | 長野市移住者空き家改修等補助金 | ・市街化区域: 最大50万円 ・その他区域: 最大100万円 ・条件により補助率3/4、子育て加算あり |
・長野市空き家バンク物件の購入/賃借者 ・完了までに長野市への住民登録が必要 |
| 中野市 | 中野市空き家活用等事業補助金 | ・基本: 80万円 (経費の2/3) ・子育て世帯: 上限200万円 ・特定区域で20万円加算 |
・転入後5年以内の方対象 ・工事費20万円以上 |
| 南木曽町 | 南木曽町空家及び空店舗利活用推進補助金 | 最大50万円 (経費の1/2以内) | ・空き家/空き店舗の利用者対象 ・事業費10万円以上 ・町内事業者の利用 |
| 大町市 | 移住推進空き家改修事業補助金 | ・所有者/移住者: 各最大30万円 | ・工事費10万円以上で市内業者利用 ・所有者は空き家バンク登録 ・移住者は5年以上の定住意思が必要 |
補助金の交付額や条件は自治体によって大きく異なりますが、多くの場合「空き家バンク登録」「居住年数」「施工業者の指定」などが共通の要件となっています。
また、移住や定住を促すために、年齢制限や子育て世帯への加算が設けられている制度も多く見られます。
申請にあたっては、契約や工事着手のタイミングに制限がある場合もあるため、補助金を利用する場合は必ず事前に自治体へ相談するようにしましょう。
空き家の解体に関する補助金
長野県内では、老朽化が進んだ空き家の解体を支援する補助制度を設けている自治体が多数あります。
倒壊の危険がある建物や再建築不可で放置されがちな物件については、解体費用の一部を公費で支援することで、空き家の放置を防ぎ、周辺環境への悪影響を抑える狙いがあります。
補助対象となるのは、老朽化した空き家の所有者や相続人が中心ですが、一部ではNPO法人などの団体による申請が可能な制度もあります。また、解体後の活用方法(住宅用地としての売却、公園としての無償提供など)により、補助率や上限額が異なるケースもあります。
補助制度によっては、事前調査で「危険空き家」として認定を受ける必要があるほか、所得制限や施工業者の要件が設けられている場合もあるため、利用前には制度内容の確認が欠かせません。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 安曇野市 | 空家等整備流通促進事業補助金 | 最大30万円~70万円 (対象経費の1/3) ※物件条件により変動 |
・1年以上空き家の個人所有者が対象 ・所有期間5年以上 ・解体後、住宅用地として売却意思があること |
| 飯田市 | 災害危険住宅対策事業補助金 | 最大97.5万円 (災害危険住宅対策事業の場合) | ・市指定の危険区域内にある既存不適格住宅 ・安全な場所への移転が目的 |
| 池田町 | 池田町空家解体撤去事業補助金 | 50万円 (定額) | ・解体工事費が100万円以上 ・申請者は個人/法人不問 ・工事着手前の申請が必要 |
| 上田市 | 上田市老朽危険空家解体利活用事業補助金 | 最大50万円 (解体工事費の1/2) (令和7年度予算は受付停止) |
・市の事前審査で「老朽危険空家」の認定が必要 ・申請者は個人所有者またはその相続人 |
| 岡谷市 | 岡谷市老朽危険空き家対策補助金 | 最大30万円 | ・市の事前調査で補助対象の認定が必要 ・1年以上空き家であること ・市内業者が施工 |
| 木曽町 | 木曽町空き家解体工事費補助金 | ・通常: 最大30万円 ・危険空き家認定: 最大100万円 (いずれも費用の1/2) |
・申請者は個人所有者またはその相続人 ・固定資産税の「住宅用地特例」が解体後5年間継続 |
| 佐久市 | 佐久市空き家再生等推進事業(除却) | 最大240万円 | ・跡地を30年以上公園等として無償提供 (補助率4/5) または10年以上活性化施設として活用 (補助率2/3) ・申請者に所得制限あり |
| 塩尻市 | 移住・定住促進居住環境整備事業補助金(解体事業) | ・個人: 最大50万円 (経費の1/2) ・法人: 最大25万円 (経費の1/4) |
・1年以上空き家の所有者/購入者が対象 ・所有者申請の場合は空き家バンクへの登録が必要 |
| 須坂市 | 須坂市老朽危険空き家解体事業 | 最大100万円 (対象経費の4/5 等) | ・市の事前判定で「老朽危険空き家」の認定が必要 ・申請者に所得制限あり (世帯所得850万円以下) |
| 諏訪市 | 諏訪市空家跡地活用支援事業補助金 | 最大20万円 (工事費の1/10 等) | ・1年以上空き家の所有者が対象 ・解体後の土地を自己居住用以外で活用する場合 |
| 千曲市 | 千曲市空き家等解体事業 | 最大100万円 (対象工事費の1/2) | ・「老朽危険空き家」または再建築不可の空き家 ・申請者に所得制限あり |
| 茅野市 | 茅野市空き家対策促進事業補助金(解体事業) | 最大20万円 (対象経費の10%) | ・築30年以上、1年以上空き家の個人所有者が対象 ・生活の本拠として使用されていたこと ・抵当権等が設定されていないこと |
| 東御市 | 東御市老朽危険空き家解体支援事業 | 最大75万円 (対象経費の1/2) | ・市の事前判定で「老朽危険空き家」の認定が必要 ・申請者に所得制限あり |
| 長野市 | 長野市老朽危険空き家解体事業補助金 | ・基本: 100万円 (補助率5/10) ・低所得者: 最大120万円 (補助率6/10) (令和7年度予算は受付終了) |
・市の事前調査で「老朽危険空き家」の判定が必要 |
| 中野市 | 民間事業者対象型の空き家活用補助金(解体) | 最大120万円 (対象経費の4/5) | ・NPO法人等の民間事業者が対象 ・解体後の跡地を地域活性化目的で利活用すること |
| 松本市 | 松本市老朽危険空家等除却費補助金 | 最大50万円 (除却工事費の1/2) | ・市の事前調査で「老朽危険空家等」の判定が必要 ・昭和56年5月31日以前着工の旧耐震基準の建物 |
多くの制度では、「工事前の申請」「老朽危険空き家の認定取得」が前提となっており、着工後では補助対象外となるケースがほとんどです。
また、補助率や上限額は自治体ごとに大きく異なるため、解体費用全体に対してどの程度支援を受けられるかを見極めたうえで、予算計画を立てることが求められます。
空き家の老朽化が進行する前に、補助制度を活用した早めの対応が費用・リスクの両面から見ても有効な選択となります。
空き家の取得に関する補助金
長野県内では、空き家を購入して移住や定住を希望する人に向けた「取得費用の補助制度」も整備されています。
補助の対象となるのは、空き家バンクに登録された物件を購入するケースが多く、制度によっては改修費用と併せて支援を受けられる場合もあります。
取得補助の多くは、移住者や若年世帯、子育て世帯を支援対象とするものが中心で、年齢制限や家族構成に関する条件が設けられているケースがほとんどです。また、「5年以上の定住意思」などの居住義務が課される点にも注意が必要です。
市町村によって補助金額や対象エリアが異なるため、制度の詳細を確認したうえで、ライフプランに合った選択が大切です。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 伊那市 |
空き家バンク利用促進補助金 |
最大75万円 (経費の2/10) ※特定エリアでは最大150万円 |
・空き家バンク登録物件の取得/増改築が対象 ・申請者に年齢/家族構成の要件あり (45歳以下等) |
| 小諸市 |
小諸市移住促進補助金 |
・基本額20万円 ・空き家バンク物件: +10万円 ・市内業者改修: +最大20万円 ・子育て/若者世帯等、他加算あり |
・長野県外からの移住者が対象 ・購入した住宅に5年以上定住を誓約 |
| 飯山市 |
飯山市移住支援住宅建設促進事業 |
・40歳未満/18歳以下扶養親族がいる世帯: 最大80万円 (経費の1/2) ・その他世帯: 最大40万円 |
・市外からの転入者が対象 ・購入した住宅に5年以上居住 |
| 中野市 |
居住誘導区域空き家購入費補助 |
最大20万円 (購入費の2/3) | ・市指定の「居住誘導区域」内の空き家購入者 ・同市のリフォーム補助金と併用可能 |
取得費用に対する補助制度は、移住支援や人口減少対策として位置づけられており、条件を満たせば手厚い支援が受けられる場合もあります。
一方で、補助申請には「県外からの転入」「扶養家族の有無」「改修の実施」など複数の要件を満たす必要があるため、事前の準備が欠かせません。
補助金の交付には、購入前の申請が必要な場合や、申請から交付までに時間がかかるケースもあるため、スケジュールには余裕をもって検討することが大切です。
空き家の家財処理に関する補助金
長野県では、空き家を売却・賃貸・活用する前段階として、家財の処分や清掃にかかる費用を補助する制度も複数の市町村で実施されています。
空き家には長年放置された家具や生活用品が残されていることも多く、残地物の整理には想定以上に高額な費用が発生する場合があります。こうした負担を軽減し、スムーズな流通や利活用を促すために、片付け費用の一部を公費で支援する仕組みが整えられています。
補助制度の多くは、「空き家バンクへの登録」や「市内業者の利用」を条件としており、物件の売却や賃貸に向けた準備段階での活用が想定されています。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 安曇野市 |
空家等整備流通促進事業補助金(片付け清掃補助) |
・最大10万円 (経費の1/3) ・一部地域(明科地域)では最大30万円 (経費の1/2) |
・物件所有者が売却/賃貸のため空き家バンクへ登録することが前提 |
| 飯山市 |
飯山市空き家活用等事業補助金(家財の運搬処分補助) |
最大10万円 (経費の1/2) | ・物件所有者が空き家バンクを通じて売却/賃貸するために家財を処分する場合 ・市内業者の利用が必須 |
| 大町市 |
空き家流通促進事業補助金(片付け清掃) |
最大8万円 (経費の1/3) | ・物件所有者が空き家バンクに登録するために片付け等を行う場合 |
| 塩尻市 |
移住・定住促進居住環境整備事業補助金(整備事業) |
・個人: 最大10万円 (経費の1/2) ・法人: 最大5万円 (経費の1/4) |
・所有者申請の場合は空き家バンクへの登録が必要 ・購入者も利用可能 |
| 須坂市 |
須坂市空き家活用事業補助金(空き家整理事業) |
最大10万円 (経費の1/2) | ・空き家バンク登録物件の所有者が対象 |
| 諏訪市 |
諏訪市移住促進空き家バンク家財処分補助金 |
資料内では確認不可 | ・空き家バンクに登録済み/登録予定の物件所有者が対象 |
| 千曲市 |
千曲市空き家バンクリフォーム補助金(家財処分) |
最大10万円 (経費の1/2) | ・空き家バンク物件を購入/賃借した移住者が対象 ・最低処分費用5万円以上 |
| 茅野市 |
茅野市空き家対策促進事業補助金(家財等処分事業) |
最大10万円 (経費の50%) | ・1年以上空き家の所有者が利活用/売却/賃貸/解体目的で家財を処分する場合 ・市内の許可業者の利用が必須 |
| 東御市 |
東御市空き家片付け補助金 |
最大10万円 (経費の1/2) | ・空き家バンク物件の売買/賃貸借契約を締結した方が対象 |
| 長野市 |
長野市移住者空き家改修等補助金 |
・市街化区域: 最大15万円 ・その他区域: 最大30万円 |
・移住者向けリフォーム補助金の一部 ・市の許可を受けた一般廃棄物処理運搬業者への依頼が必要 |
| 中野市 |
中野市空き家活用等事業補助金(活用) |
最大10万円 (経費の1/2) | ・空き家バンク登録物件の所有者が対象 |
| 木島平村 |
空き家活用等事業(家財搬出及び清掃) |
最大10万円 (経費の1/2) | ・空き家の有効活用、移住定住促進、廃屋化防止を目的とする |
家財の片付けや清掃に対する補助は、比較的少額ながらも即効性のある支援です。
特に「費用負担がネックで空き家を手放せない」という所有者にとっては、負担軽減と活用促進を同時に実現できる支援策です。
制度ごとに補助対象となる作業範囲や費用の下限が異なるため、申請前には見積書や業者の条件などを自治体に確認しておくと安心です。
その他の補助金
空き家の利活用を円滑に進めるために、長野県や一部の市町村では、登記費用や仲介手数料、住宅診断(インスペクション)に対する補助制度も整備されています。
これらの補助金は、空き家の売却や購入の際に発生する間接的なコストを軽減し、流通促進やトラブルの回避を目的としています。相続登記が未了の物件については、売却前に登記を済ませる必要があるため、登記補助は特に有用です。
| 管轄 | 補助金制度名 | 補助上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 長野県 |
あんしん空き家流通促進事業 |
・インスペクション: 5万円 ・瑕疵保険: 5万円 (合計最大10万円) |
・買主のリスク低減と市場の透明性を高め、取引を活性化させることが目的 |
| 須坂市 |
須坂市空き家活用事業補助金 (相続登記補助事業) |
最大5万円 (経費の1/2) | ・空き家バンク登録に必要な相続登記費用を支援 |
| 須坂市 |
須坂市空き家活用事業補助金 (媒介手数料補助事業) |
低廉な空き家売買等特例部分の媒介手数料の2/3以内 | ・空き家バンク登録物件の売買/賃貸契約時の仲介手数料の一部を補助 |
相続登記やインスペクションは、空き家を売却・流通させるための「前提条件」として重要な手続きです。
特に、登記未了のままでは正式な売買契約が締結できないため、補助制度を活用して早めに対応しておくことが求められます。
他の補助金と併用できるケースもあるため、空き家の現状や今後の活用方針にあわせて柔軟に組み合わせるのが効果的です。
補助金を受けるための流れと注意点
長野県内の各自治体が実施している空き家補助金制度は、原則として申請→審査→交付決定→工事着手→実績報告という流れで進みます。
多くの制度では、「交付決定を受ける前に工事に着手した場合は補助対象外」となっているため、早まった契約や着工には十分注意が必要です。
また、自治体によっては申請前に現地確認や事前相談が義務付けられていたり、予算上限に達し次第受付を終了する制度もあるため、補助金の利用を検討する際は、できるだけ早めに窓口へ相談するのが安全です。
特に、補助対象となる物件の条件(空き家バンクへの登録や所有期間、構造・用途の制限など)は自治体ごとに異なるため、自分のケースが該当するかどうかを確認したうえで申請準備を進めることが大切です。
次の項目では、申請時に必要となる主な書類や実際によくある見落としポイントについて解説します。
申請に必要な主な書類
空き家補助金を申請する際には、制度の種類や自治体によって提出書類が異なりますが、共通して求められることが多い基本書類は次のとおりです。
- 補助金交付申請書(自治体所定の様式)
- 対象物件の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 位置図・現況写真・平面図などの物件情報
- 施工業者が発行した見積書
- 売買契約書や賃貸契約書の写し(該当する場合)
- 住民票または移住証明書(移住者向け補助の場合)
- その他、誓約書や同意書など各自治体が指定する添付書類
また、補助金は「交付決定後に工事を着工すること」が原則となっているため、契約書や見積書の日付にも注意が必要です。
手続きの流れや必要書類は自治体によって異なるため、まずは窓口へ相談し、申請要件を正確に把握することが大切です。
申請する上での注意点や落とし穴
空き家補助金を利用する際は、いくつかの重要な注意点があります。特に、以下のような点は見落とされやすく、制度をうまく活用できなかったというケースも少なくありません。
交付決定前の工事着手は対象外になる
多くの補助金制度では、申請後に自治体から交付決定を受けてからでなければ、工事を始めることができません。契約や着工を急いでしまうと、補助の対象外となってしまうため注意が必要です。
補助金の申請時期と受付枠に注意する
年度ごとの予算枠が設定されている制度が多く、申請が集中すると早期に受付終了となることもあります。利用を検討している場合は、なるべく早めに問い合わせることが大切です。
制度の条件や制限を見落とさない
対象物件の所在地や築年数、申請者の年齢、居住年数の条件など、制度によって細かい制限があります。特に「移住者向け」「子育て世帯向け」などの加算要件は見落としやすいため、申請前に制度要綱を確認しましょう。
補助金の併用可否を事前に確認する
複数の補助制度を活用したい場合は、それぞれの制度で併用が可能かどうかを確認しておく必要があります。市町村ごとに取り扱いが異なるため、個別に問い合わせて確認するのが確実です。
必要書類が揃っていないと申請できない
申請書以外にも登記簿や見積書、契約書、写真などが必要になります。書類が不足していると申請そのものが受理されないため、事前の準備が欠かせません。
こうした点に注意しながら、補助金制度を正しく活用すれば、空き家にかかる費用負担を大きく抑えることができます。
補助金以外で空き家問題を解決する方法
空き家の管理や処分にあたっては、補助金制度の活用は有効な手段となります。ただし、すべての物件や状況に適用できるわけではなく、補助金だけでは解決が難しいケースもあります。
まずは補助金の利用が難しいケースを整理しつつ、空き家問題を前向きに解決するための方法をご紹介します。
補助金だけでは難しいケースがある
空き家補助金は費用負担の軽減に役立ちますが、現実には制度の条件を満たせず利用できないケースも少なくありません。
例えば、空き家バンクに登録していない物件や、活用予定がなく単に「手放したい」と考えている空き家は、補助対象から外れることがあります。
また、申請には工事見積書や登記簿など複数の書類が必要で、所有者が高齢であったり、遠方に住んでいる場合、準備そのものが負担となるケースもあります。
さらに、自己負担分の資金が確保できなかったり、交付までの期間に工事を進めたいといった事情から、断念せざるを得ない例も見られます。
制度の概要だけで判断せず、事前に「実際に利用できるかどうか」を専門家に相談することが重要です。
空き家を売却する
補助金を活用できない、あるいは活用しても費用がかさむ場合には、空き家そのものを売却するという選択肢もあります。
特に、今後も使う予定がない物件については、放置によって劣化が進む前に売却した方が、維持費や修繕コストを抑えられるという現実的なメリットがあります。
長野県では都市部から離れた地域に築古の空き家が集中しており、不動産市場では扱いが難しい物件も少なくありません。そうした場合には、空き家パスのような再建築不可や現状渡しの空き家にも対応している買取専門業者に相談するのが有効です。
買い手を探す手間を省き、スピーディーに処分できる点でもメリットがあります。相続後の管理負担を減らすうえでも、売却という選択は有効です。
関連記事:長野県で空き家売却に強い買取業者5選|選び方やすぐに買い取ってもらうためのポイントを解説
空き家バンクを活用する
空き家バンクは、自治体が管理する公的なマッチング制度で、空き家を必要とする移住希望者や地域事業者に向けて、物件情報を提供し、利活用を促進する制度です。
長野県内でも多くの市町村が導入しており、登録には物件調査や写真提出、所有者の意向確認などが必要となります。売却や賃貸どちらにも対応しており、登録物件は補助金の対象になる場合もあるため、制度を組み合わせた活用が可能です。
ただし、民間仲介と異なり広範な広告や営業活動は期待しにくく、成約までに時間がかかる傾向があります。また、利用には自治体とのやり取りが前提となるため、丁寧な情報提供と手続きの理解が不可欠です。
空き家を活用する
補助金を活用して空き家をリフォームし、自らのアイデアで再活用するという選択肢もあります。
たとえば、観光客の多い地域では民泊施設として運営したり、地域のニーズに合わせてカフェやアトリエ、子育て支援拠点などにリノベーションしたりする事例も見られます。
長野県内でも、空き家を地域の交流スペースやシェアオフィスに改修し、地域活性化の拠点として活用する取り組みが広がっています。特に移住希望者や二拠点生活を送る人々の増加により、「住む」以外の用途で空き家を活かす動きが注目されています。
ただし、こうした活用を行うには、初期費用の確保や運営に関する知識・体制が求められます。また、用途によっては建築基準法や消防法、旅館業法などの関係法令への対応が必要なケースもあるため、事前に行政や専門家への相談を行うことが重要です。
【参考:古民家等活用マニュアルについて/長野県】
よくある質問とトラブル例
空き家の補助金制度は魅力的ですが、制度が複雑で自治体ごとに条件も異なるため、いざ利用しようとしたときに戸惑うケースも少なくありません。実際に、「どの制度を使えばいいのかわからない」「対象になるか不安」「申請の手順が難しそう」といった声は多く寄せられています。
ここでは、補助金の利用を検討する際に、多くの方が直面する疑問や悩みに対する対応策を、質問・事例形式で紹介していきます。
Q:補助金と売却、どちらが良いですか?
A:空き家を今後も活用したいかどうかが判断の分かれ目です。
補助金制度はリフォームや解体を前提としており、所有を継続する意思がある場合に有効です。
一方、活用予定がなく管理が難しい空き家は、補助金の手続きを経るよりも、現状での売却を選ぶ方が負担を減らせるケースもあります。
築年数や立地によっては、買取専門業者が現状のまま引き取ってくれる場合もあるため、将来的な活用の可能性と現状の維持コストを比較し、自分に合った方法を選ぶことをおすすめします。
Q:古い空き家や傷みがある空き家でも補助金は使えますか?
A:制度によっては利用可能ですが、状態や立地によっては対象外となることもあります。
例えば、老朽化が進んだ建物はリフォーム補助ではなく、解体補助の対象となることが多く、構造や築年数に制限を設けている自治体もあります。
また、倒壊リスクがある建物や再建築不可の物件については、申請時に現地調査や安全性の確認が行われる場合もあります。
補助金の種類ごとに判断基準が異なるため、対象になるかどうかは必ず事前に市町村の窓口で確認することが大切です。
Q:補助金申請が難しそう…誰かに頼めますか?
A:制度によっては、行政書士や地域の建築業者が申請をサポートしてくれる場合があります。
特に高齢の所有者や遠方に住む相続人にとっては、必要書類の収集や工事見積もりの手配が大きな負担になります。地域によっては、空き家対策の窓口や宅建協会、不動産業者が書類準備や段取りを支援する体制を整えています。
事前相談を通じて、代理申請の可否やサポート内容を確認することで、スムーズに申請を進められる可能性が高まります。
Q:空き家を自治体に寄付できますか?
A:原則として、空き家をそのまま自治体に寄付することはできません。
老朽化した建物や再建築不可の土地は、維持や用途の問題から多くの自治体で受け入れが難しいのが現状です。 ただし、特定目的に限り寄付が認められる場合もあります。
例えば、長野市では、狭あい道路の拡幅を目的とした「道路後退用地提供制度」があり、一定の条件を満たせば土地の一部を寄付できます。こうした制度は、道路整備など都市計画上の必要に応じた例外的な対応です。
寄付を検討する際は、まず自治体に相談し、現地調査や条件の確認を受ける必要があります。
【参考:道路後退にご協力ください – 長野市公式ホームページ】
まとめ
長野県内には、空き家のリフォームや解体、取得・片付けに対する多様な補助制度が用意されており、条件に合えば費用負担を大きく抑えることが可能です。ただし、すべての物件や状況に補助金が適用できるわけではないため、制度内容の確認や申請準備は慎重に進める必要があります。
また、補助金以外にも、空き家の売却や空き家バンクの活用、自らの手による利活用といった複数の選択肢が存在します。今後のライフプランや地域との関係性も考慮しながら、自分に合った対処法を検討してみてください。
「早く手放したい」「これ以上、維持費や手間をかけたくない」と感じている方は、まずは空き家パスへご相談ください。
空き家パスは、築古物件や再建築不可物件、他社で断られた空き家にも対応する買取専門会社です。相続など複雑な事情が絡む物件にも、専門家と連携して対応しています。査定・相談はすべて無料です。
LINEやウェブサイトの申込フォームから、まずはお気軽にお問い合わせください。