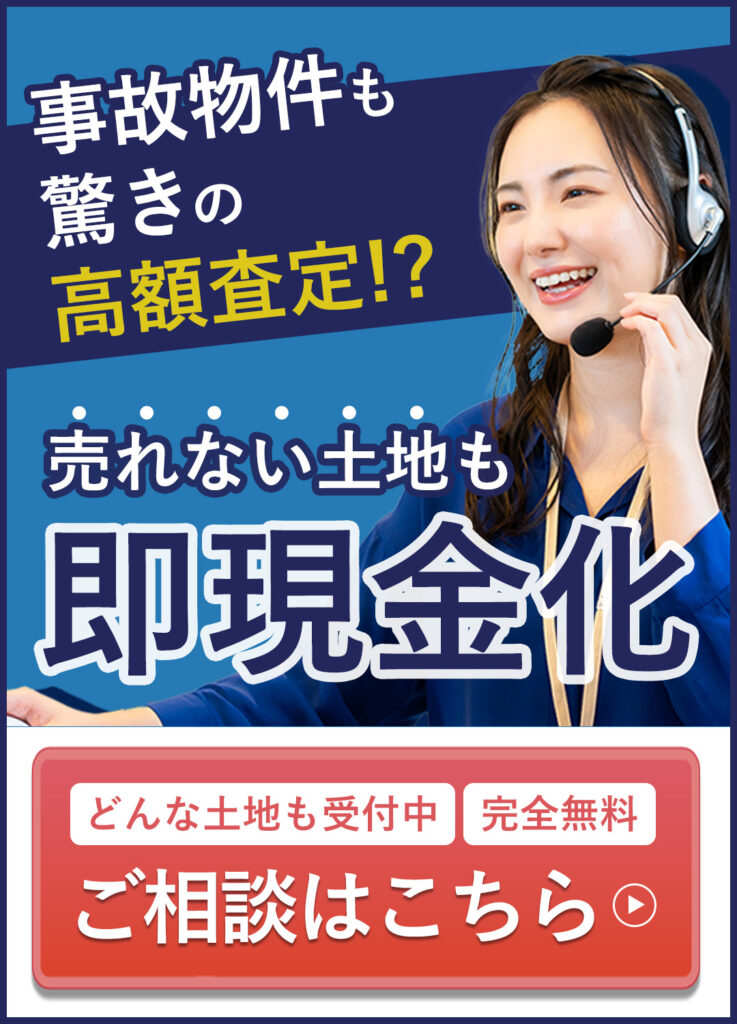島根の空き家補助金を解説ー解体・リフォームなどで活用!申請の流れや注意点も
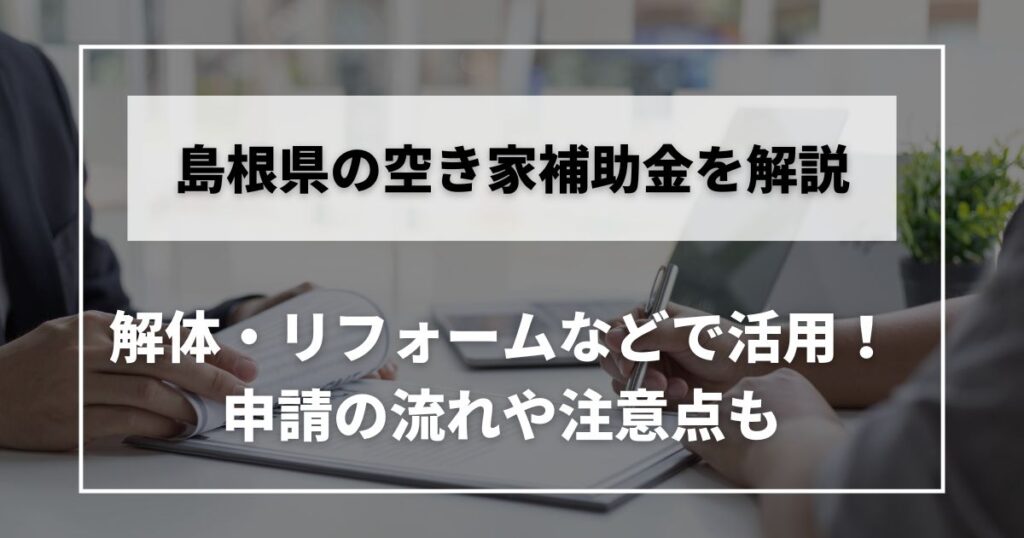
島根県でご実家や土地を相続された方、または将来相続を控えている方のなかには、空き家の管理に悩んでいる方も多いかもしれません。
老朽化が進んだ建物は、リフォームや解体に多額の費用がかかるため、対策を先延ばしにしてしまうケースも少なくありません。
そんなときに頼りになるのが、島根県や各市町村が設けている「空き家に関する補助金制度」です。リフォームや解体、家財の整理といった費用の一部を公的にサポートしてくれるため、自己負担を抑えて対策を進めることができます。
本記事では、島根県内で利用できる空き家関連の補助金について、種類から申請の流れ、注意点まで専門家の視点で網羅的に解説します。
- 島根県が直面している空き家問題の現状
- 島根県で利用できるリフォームや解体などの補助金の具体的な種類
- 補助金を受け取るための申請手続きの流れと事前に知るべき注意点
- 補助金以外の方法で空き家問題を解決するための選択肢
補助金の活用とあわせて、空き家の売却も重要な選択肢のひとつです。空き家パスは、相続不動産の買取を得意とする不動産会社です。
相続関係で複雑になっている物件や、田舎の築古物件、再建築不可物件、訳あり物件など、他の不動産会社に断られた空き家でも買取を行っています。ご相談、査定は完全無料です。お気軽にお問い合わせください。
島根県の空き家問題、現状は?
島根県は、全国的に見ても空き家の割合が高い地域の一つです。
総務省統計局の「令和5年住宅・土地統計調査(速報集計)」によると、島根県の空き家率は17.0%で、全国平均の13.8%を大きく上回っています。これは県内のおよそ6軒に1軒が空き家であることを示しており、依然として深刻な課題といえます。
空き家の高水準が続く背景には、少子高齢化や県外への人口流出が大きく影響しています。
実家を相続した所有者がすでに県外で生活しているため、戻って住むことが難しく、そのまま放置されるケースが増えています。
管理不全の空き家は、老朽化による倒壊リスクに加え、景観の悪化や不法投棄、害獣の発生、放火といった防犯・防災上の問題も引き起こします。
こうしたリスクを背景に、国は近年、空き家対策の強化を進めており、島根県や各市町村も対応を急いでいます。
【参考:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査】
空き家問題解決策のひとつ「補助金制度」
空き家の増加が社会問題となるなか、国や地方自治体では、老朽化した建物の改修や除却を支援する「補助金制度」を整備しています。
補助金制度は、空き家のリフォーム、解体、耐震改修、家財処分などにかかる費用の一部を公的に補助するもので、所有者の経済的負担を軽減し、適正管理や利活用を促進するための制度です。
多くの自治体で採用されているのは、申請後に交付決定を受けてから着工する「後払い方式」です。
また、制度には年度ごとの予算上限があり、申請件数が一定に達すると早期終了する場合もあります。補助金の活用を検討する際は、工事内容や申請時期、対象要件などを事前に確認しておくことが重要です。
島根県で使える空き家関連補助金
島根県内でも、空き家の再生や解体を支援するために、各市町村が独自の補助制度を設けています。
これらの制度を活用すれば、リフォーム費用や解体費用などの一部を公的に負担でき、空き家の有効活用や安全確保につなげることが可能です。
県内の制度は、目的によって大きく「改修」「解体」「取得」「家財処理」「その他(登録・維持管理支援)」に分かれます。補助金の名称や上限額、対象条件は自治体によって異なり、空き家バンクへの登録や定住を条件とするケースも多く見られます。
なお、各制度には年度予算枠が設けられており、募集期間内であっても予算上限に達し次第受付が終了することがあります。
利用を検討する際は、必ず各市町村の公式サイトや担当窓口で最新情報を確認しましょう。
以下では、島根県内の代表的な市町村で実施されている補助金制度を、目的別に整理して紹介します。
空き家のリフォーム・改修に関する補助金
空き家のリフォーム・改修に関する補助金は、老朽化した空き家を修繕し、再び居住や地域活性化の拠点として活用する際に利用できる制度です。
島根県内では、移住促進や地域コミュニティの再生を目的とした補助金が多く、特に空き家バンク登録物件を対象とするケースが目立ちます。
また、単なる居住用だけでなく、地域交流施設や賃貸住宅など、地域のにぎわい創出に資する用途への改修も支援対象となっています。
以下に、主要な市町村の制度をまとめました。
| 市町村名 | 制度名 | 補助上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 松江市 | 空き家再生等推進事業補助金 | 70万円 (耐震改修併用で140万円) |
・個人の居住用ではなく、交流施設など地域活性化目的での活用 ・事業完了後10年間の継続活用が必須 ・工事着手前の申請が必要 |
| 浜田市 | 空き家バンク登録物件改修事業補助金 | 通常30万円 (40歳未満のU・Iターン者等は最大100万円) |
・空き家バンク登録物件の契約者が対象 ・契約日から6ヶ月以内の申請が必要 |
| 出雲市 | いずも移住リフォーム助成金 | 最大80万円 (移住者の条件により変動) |
・市外に5年以上在住する移住者が対象 ・世帯状況や移住先地域により補助額が変動 ・工事着手前の申請が必須 |
| 益田市 | 益田市空き家改修事業補助金 | 50万円 (子育てU・Iターン世帯は70万円) |
・「益田市空き家バンクナビ」登録物件を利用するU・Iターン者が対象 ・5年以上の定住が見込まれること ・対象経費が30万円以上 |
| 大田市 | おおだに住もう移住者定住支援事業 | 50万円 | ・U・Iターン者またはU・Iターン者に入居させる所有者が対象 ・改修後5年以上の定住が必要 ・対象経費が25万円以上 |
| 安来市 | 空き家改修事業補助金制度 | 最大100万円 (利用者の条件により変動) |
・安来市空き家バンク登録物件のみ対象 ・3年以上の居住が見込まれること ・契約日から1年以内の改修が必要 |
| 江津市 | U・Iターンのための空き家改修費補助金 | 50万円 | ・空き家バンク登録物件を購入したU・Iターン者または貸し出す所有者が対象 ・5年以上の居住が必要 ・工事は原則市内業者が実施 |
| 飯南町 | 空き家改修助成金 | 50万円 | ・所有者がU・Iターン者等への賃貸・売却目的で改修する場合に対象 |
| 川本町 | 空き家改修助成 | 350万円 | ・所有者が定住希望者への賃貸目的で改修する場合に対象 ・耐震性能確認、水洗便所化、改修後10年間の協定締結が条件 |
| 津和野町 | 空き家改修補助金 | 50万円 | ・津和野町空き家情報バンクに登録された物件にのみ適用 ・改修費を助成 |
| 吉賀町 | 空き家活用集落担い手確保事業補助金 | 所有者50万円 利用者75万円 |
・空き家情報バンク登録物件が対象 ・所有者は10年以上、利用者は5年以上の登録・居住が原則 ・3親等以内の親族への賃貸は対象外 |
| 隠岐の島町 | 空家等改修・再生事業補助金 | コミュニティ用途250万円 賃貸用途350万円 |
・所有者がコミュニティ利用または空き家バンク経由の賃貸目的で改修する場合に対象 ・耐震性能確認と水洗便所が条件 |
| UIターン促進事業補助金 | 最大200万円 (世帯条件等により加算) |
・50歳未満のU・Iターン者が対象 |
島根県の多くの自治体では、移住者の呼び込みと地域活性化の両立を意識した補助制度が整備されています。
特に「空き家バンク登録」や「U・Iターン支援」を条件とするケースが多く、活用の目的や申請者の属性によって補助額が変動します。
申請はいずれも着工前が原則のため、改修を検討している場合は、早めに自治体へ相談し、必要書類やスケジュールを確認しておくことが重要です。
空き家の解体に関する補助金
老朽化が進み、倒壊の危険性がある空き家を解体・撤去する際に、その費用の一部を補助する制度です。
島根県内でも多くの自治体が同様の支援制度を設けており、特に「危険空き家」として行政が認定した物件を対象とするケースが一般的です。
また、解体後の跡地を活用する前提で、新築や利活用計画を条件とする制度も複数見られます。
以下に、主要な自治体の制度をまとめました。
| 市町村名 | 制度名 | 補助上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 松江市 | 老朽空き家除却支援事業補助金 | 50万円 | ・倒壊等の危険性がある老朽空き家が対象 ・市の事前調査が必要 ・家財や庭木等の撤去費用は対象外 |
| 浜田市 | 浜田市特定空家等除却促進事業補助金 | 50万円 | ・市に「特定空家等」として認定された危険な建物が対象 ・申請前の1年間、空き家であったことが条件 |
| 出雲市 | 出雲市老朽危険空家等除却支援補助金 | 100万円 | ・市の基準で危険度評点が100点以上の木造建築物が対象 ・事前調査が必要 |
| 益田市 | 益田市老朽危険空家除却支援事業補助金 | 危険度により30万円~50万円 (加算措置あり) |
・市の現地調査と危険度判定が必要 ・工事は市内業者が実施 |
| 雲南市 | 雲南市危険空き家除却事業補助金 | 100万円 | ・幹線道路等に影響を及ぼすおそれのある危険な木造空き家が対象 ・事前調査申請が必須 |
| 江津市 | 江津市老朽危険空家除却支援事業補助金 | 100万円 | ・住宅地区改良法に基づく不良住宅と認定されたものが対象 |
| 美郷町 | 美郷町:空き家解体撤去補助金 | 200万円 | ・跡地に新築住宅を建設することが条件 |
| 邑南町 | 跡地活用のための空き家解体支援事業 | 100万円 | ・解体後1年以内の新築(住宅・店舗)計画が必須 ・対象は空き家バンク1年以上登録物件または昭和56年5月31日以前に着工されたもの |
| 津和野町 | 老朽危険空家除却支援事業補助金 | 120万円 | ・市の基準で評点100点以上と判定された危険空き家が対象 ・工事は町内業者が実施 ・事前調査が必要 |
| 奥出雲町 | 奥出雲町老朽危険空き家除却支援事業補助金 | 120万円 | ・町の基準で評点100点以上の危険空き家が対象 ・事前調査が必要 |
| 西ノ島町 | 西ノ島町老朽危険空家等除却支援事業補助金 | 120万円 | ・危険度判定の基準値を超える木造住宅が対象 ・町内業者への発注と事前調査が必須 |
| 隠岐の島町 | 隠岐の島町危険空き家除却事業補助金 | 150万円 | ・事前診断で危険と判断された木造住宅が対象 |
島根県の解体補助制度は、多くが行政による「危険空き家」の認定を前提としています。
倒壊の恐れや周辺への影響がある建物が主な対象です。
また、邑南町や美郷町のように、解体後に新築住宅や店舗を建てることを条件とする自治体もあります。
補助上限額は30万円〜200万円と幅があり、危険度判定や耐震基準などに基づいて決まります。
いずれの制度も着工前の事前調査や相談が必須です。申請のタイミングを逃すと補助を受けられない場合があるため、早めに自治体窓口で確認しておくと安心です。
空き家の取得に関する補助金
島根県では、空き家の「購入」を支援する制度は一部の自治体に限られますが、移住・定住を促進する目的で、中古住宅の取得を補助する仕組みが整備されています。特に、新婚世帯や子育て世帯、若年層の定住支援を目的とした制度が中心です。
以下に、主な制度をまとめました。
| 市町村名 | 制度名 | 補助上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 出雲市 |
出雲市移住促進住まいづくり助成金 |
年間10万円を5年間 (総額50万円) |
・市外に5年以上在住の新婚・子育て世帯が、定住目的で住宅(中古含む)を購入する場合に対象 ・助成額は固定資産税相当額 |
| 飯南町 |
空き家購入助成金 |
50万円 | ・65歳以下の購入者が対象 |
空き家の取得補助は、若年層や移住者の定住促進を目的とした限定的な支援です。
いずれの制度も申請前の相談が推奨されており、契約前に対象条件を確認しておくと安心です。
空き家の家財処理に関する補助金
空き家の家財処理に関する補助金は、売却や賃貸の妨げとなる残置物の片付けや清掃にかかる費用を支援する制度です。
島根県では、空き家バンクへの登録や利活用を前提とした補助が多く、家財撤去だけでなく清掃や整理作業にも適用されます。
以下に、主要な自治体の制度をまとめました。
| 市町村名 | 制度名 | 補助上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 浜田市 | 空き家バンク活用促進事業補助金 | 5万円 | ・空き家バンク登録物件の所有者が対象 |
| 出雲市 | 空き家バンク登録支援事業補助金 | 5万円 | ・空き家バンクに2年以上掲載する所有者が対象 |
| 益田市 | 空き家バンク登録支援補助金 | 3万円 | ・空き家バンク登録物件の所有者が対象 |
| 大田市 | おおだに住もう移住者定住支援事業 | 15万円 | ・空き家バンク物件のU・Iターン者または所有者が対象 |
| 雲南市 | 空き家片づけ事業補助金 | 10万円 | ・空き家バンク登録前の物件片付けが対象 |
| 飯南町 | 空き家片付け助成金 | 10万円 | ・U・Iターン者居住用の片付けが対象 |
| 川本町 | 空き家バンク活用促進事業補助金 | 家財撤去20万円 清掃20万円 |
・空き家バンク登録が条件 |
| 邑南町 | 邑南町:空き家バンク活用促進事業 | 家財処分10万円 清掃10万円 |
・空き家バンク登録者が対象 |
| 吉賀町 | 空き家家財等処分推進事業補助金 | 10万円 |
・空き家バンク賃貸用物件の所有者が対象 ・家財運搬は所有者本人が行うことが条件 |
| 隠岐の島町 | 空家クリーニング事業補助金 | 20万円 | ・空き家バンク登録者が対象 |
家財処理に関する補助は、空き家を「活用につなげる」ための第一歩として設けられています。
多くの自治体で空き家バンク登録を条件としており、片付け後に賃貸や売却を進めやすくする狙いがあります。
制度によっては清掃費用まで支援対象となるため、放置空き家の整理を始めるきっかけとして活用しやすい補助金です。
申請時には、事前相談や登録手続きの有無を確認しておくとスムーズです。
その他の補助金
島根県では、リフォームや解体以外にも、空き家の流通や管理を後押しする補助制度が設けられています。
空き家バンクへの登録を促進する奨励金や、登記・維持管理費の補助など、幅広い支援が行われています。
以下に主な制度をまとめました。
| 市町村名 | 制度名 | 補助上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 益田市 |
益田市空き家バンク登録推進奨励金 |
3万円 |
・空き家バンクに2年以上物件を登録した所有者が対象 ・固定資産税相当額(上限3万円)を1回限り交付 |
| 川本町 |
空き家バンク活用促進事業補助金 |
10万円 |
・「相続登記」の費用を補助(上限10万円) ・家財処理、清掃費用も対象 |
| 邑南町 |
邑南町:空き家バンク活用促進事業 |
管理費: 年間12万円 調査費: 10万円 |
・空き家バンク登録者が対象 ・敷地の草刈り等の「維持管理費用」や専門家による「現況調査費用」を補助 |
| 江津市 |
江津市空き家バンク活用促進事業 登録支援補助金 |
10万円 |
・空き家バンク登録物件の所有者が対象 ・庭木の剪定等も含む |
こうした制度は、空き家をすぐに活用できない場合でも、維持・管理を続けるための負担軽減策として有効です。
登録奨励金や管理費補助を活用すれば、放置を防ぎながら次の利活用への準備を進めることができます。
また、相続登記などの初期手続きの支援を行っている自治体もあり、空き家を活用につなげるための環境づくりという点でも注目されています。
補助金を受けるための流れと注意点
補助金を活用するには、各自治体が定める手続きに従って申請を行う必要があります。申請から交付までには一定のステップがあり、制度ごとに準備すべき内容や注意点も異なります。
特に重要なのが、申請前の情報収集と事前相談です。制度によっては、着工前に交付決定を受けなければ補助の対象とならないケースもあります。
また、申請書の様式や提出先が市町村ごとに異なるため、自己判断で進めるのは避けましょう。
提出書類については、次項「申請に必要な主な書類」で詳しく解説します。申請準備を進める際の参考にしてください。
申請に必要な主な書類
申請時に必要となる書類は自治体や補助金制度で異なりますが、一般的に以下のものが求められます。
- 補助金交付申請書:自治体の窓口やウェブサイトで入手
- 事業計画書:工事の概要やスケジュールなどを記載
- 収支予算書:工事にかかる費用の見積書などを基に作成
- 工事の見積書の写し:複数の業者から見積もりを取ることを推奨される場合もあり
- 建物の登記事項証明書(登記簿謄本):法務局で取得
- 固定資産税納税証明書:市町村の税務課などで取得
- 工事箇所の写真:工事前の状況がわかる写真が必要
- 本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードなど
上記はあくまで一例です。申請を検討する際は、必ず募集要項を確認し、必要な書類をリストアップして準備を進めましょう。
申請する上での注意点や落とし穴
島根県内の補助金制度をスムーズに活用するためには、事前にいくつかの重要なポイントを把握しておく必要があります。
以下の点を見落としてしまうと、申請が無効になる、あるいは補助金が受け取れなくなる場合もあるため、十分に注意しましょう。
着工前に申請を行うこと
最も基本かつ重要な注意点です。補助金は、自治体から「交付決定通知」が出た後に契約・着工した工事のみが対象となります。通知前に着工してしまった場合、原則として補助金は支給されません。
予算の上限や申請期間を確認する
補助金制度には、年度ごとの予算枠が設定されており、申請が集中すると受付が早期に締め切られることもあります。先着順の制度もあるため、希望する方は早めに各市町村の公式情報を確認し、準備を進めましょう。
補助金は「後払い」が原則
工事完了後に検査や書類審査を経て、補助金が支給されるのが一般的です。そのため、一時的に全額を自己負担する必要があり、資金計画を明確に立てることが大切です。
施工業者の条件を確認する
島根県内の多くの自治体では、施工を担当する業者にも一定の条件が設けられています。たとえば「市内に本店を置く業者に限る」といった要件がある場合もあるため、契約前に必ず確認しましょう。
他の補助制度との併用可否を確認する
同じ事業で国の補助金や他の自治体支援を受けている場合、併用できないケースもあります。複数制度を検討している方は、併用可能かどうかを、申請前に確認しましょう。
補助金以外で空き家問題を解決する方法
補助金は空き家対策の有効な手段ですが、所有者の状況によっては最適な解決策でない場合もあります。補助金以外の選択肢も検討しましょう。
補助金だけでは難しいケースがある
補助金は決して万能ではなく、以下のようなケースでは利用が難しかったり、適さない場合があります。
そもそも空き家を活用する予定がない
補助金の多くは、リフォームや改修後の「活用」を前提としています。例えば、居住や賃貸、地域活動への提供などが条件となる場合もあり、今後使う予定がない空き家では対象外になることがあります。
「手放したい」「管理の負担から解放されたい」という方にとっては、補助金は根本的な解決策にはなりにくいのが実情です。
申請手続きの手間や時間が確保できない
申請には複数の書類を揃える必要があり、平日に市町村の窓口へ足を運ぶ機会も少なくありません。島根県外にお住まいの方や、高齢の所有者や忙しい社会人にとっては、申請の準備が大きなハードルとなることがあります。
自己負担分の資金を準備できない
補助金はあくまで「一部負担」の仕組みであり、解体・改修にかかる費用のすべてをカバーするものではありません。例えば工事費が100万円かかる場合でも、補助金が50万円であれば、残りの50万円は自己資金で賄う必要があります。
自己負担分の工面が難しいと、実際の着手に踏み切れないケースも多く見られます。
また、制度によっては「最低〇年間は賃貸物件として活用すること」などの利用制限が付くこともあります。将来的に売却や別用途を考えている場合には、こうした条件が制約となる可能性もあるため、十分に検討が必要です。
空き家を売却する
空き家を今後使う予定がなく、管理の負担や固定資産税の支払いから解放されたいと考えている場合、売却は非常に現実的な解決策のひとつです。
建物の維持や近隣への配慮といった精神的なストレスがなくなり、まとまった資金が得られる可能性もあります。
ただし、島根県のように人口が少ない地域では、老朽化が進んだ物件や立地条件の厳しい物件について、一般の不動産会社では「買い手が見つからない」として仲介を断られることもあります。
そうした場合は、空き家の買取に特化した専門業者への相談を検討しましょう。
「空き家パス」のような業者であれば、築年数の古い住宅や法的な制約を抱えた物件であっても、現状のままで買い取ってもらえるケースがあります。
仲介とは異なり、買い手を探す必要がないため、売却までの手間や時間を大きく減らすことができ、スムーズな現金化につながるのが特徴です。
誰も住まない家を持ち続けるストレスや費用に悩んでいる方にとって、「買い手を探さなくていい」という選択肢は、大きな安心感につながります。
まずは気軽に専門の窓口へ相談してみることをおすすめします。
関連記事:島根県の空き家・不用品買取業者8選|相場や買取のメリット・デメリットも解説
空き家バンクを活用する
「空き家バンク」は、空き家を「売りたい」「貸したい」所有者と、「買いたい」「借りたい」希望者をマッチングさせる、主に自治体が運営する情報提供の仕組みです。ウェブサイト上に物件情報が公開され、移住希望者などが閲覧します。
空き家バンクに登録するメリットは、自治体による情報発信を通じて、通常の不動産市場では見つけにくい買主や借主と出会える可能性がある点です。
また、バンク登録物件の購入者や賃借人がリフォーム補助金などを利用できる場合も多く、取引が成立しやすくなる効果も期待できます。
ただし、登録から成約までには時間がかかることもあり、必ずしもすぐに買い手や借り手が見つかるわけではない点は理解しておきましょう。
空き家を活用する
売却や賃貸といった方法以外にも、空き家を自らのアイデアで活用する選択肢があります。
たとえば、リフォームを行ってカフェや民泊として運営したり、地域の交流スペースとして活用したりする事例が一部で見られます。
島根県でも、空き家を活かした店舗やコミュニティ施設の事例が紹介されており、地域との関わりを深める場として活用されているケースもあります。
ただし、事業として活用するには、初期投資の費用や専門的なノウハウ、そして継続的な運営体制が求められます。
また、建築基準法・消防法・旅館業法などの関係法令をクリアする必要があるため、事前の計画と下調べが重要です。
うまく活用できれば、空き家が収益源や地域資源として生まれ変わる可能性もありますが、事業リスクもあることを念頭に置いた上で判断することが大切です。
【参考:空き家利活用事例集】
よくある質問とトラブル例
ここでは、空き家の補助金や処分に関して、所有者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q:補助金と売却、どちらが良いですか?
A:空き家を今後どのように扱いたいかによって、最適な選択肢は異なります。
たとえば、リフォームして住む予定がある、もしくは賃貸物件として活用したい場合には、補助金を利用して費用負担を軽減する方法が有効です。
一方で、「今後使う予定がない」「管理や固定資産税の負担をなくしたい」と考えている場合には、売却という選択肢がより現実的かもしれません。
特に、築年数が古かったり、立地条件が厳しいといった理由で通常の不動産仲介では売却が難しい空き家については、空き家の買取を専門とする業者への相談が有効です。
島根県では、空き家の状態や立地によっては、自治体の補助制度よりもスムーズに売却できるケースもあるため、どちらの方法が自分に合っているかを、目的や条件に応じて検討することが大切です。
Q:古い空き家や傷みがある空き家でも補助金は使えますか?
A:はい、古くなった空き家や傷みのある物件でも、補助金の対象となる場合があります。
実際、島根県内の多くの自治体では、老朽化が進んだ空き家を解体・除却するための補助制度や、リフォーム・改修に対する支援制度が用意されています。
特に、1981年(昭和56年)以前に建築された木造住宅などは、倒壊リスクのある「危険空き家」として認定される可能性があり、その場合は解体費用の一部が補助されるケースがあります。
また、一定の条件を満たせば、修繕・再活用のためのリフォーム費用に対しても補助金を受けられることがあります。
ただし、制度の内容や対象条件は自治体ごとに異なるため、まずは空き家の所在地を管轄する市町村の窓口に確認してみることをおすすめします。
Q:補助金申請が難しそう…誰かに頼めますか?
A:はい、大丈夫です。補助金の申請手続きが不安なときは、外部の専門家にサポートをお願いすることもできます。
島根県内の多くの自治体には、補助金に関する相談窓口があり、必要書類の準備や申請の進め方を丁寧に教えてもらえます。
また、地元の建築業者や工務店によっては、見積書や図面の準備はもちろん、申請書類の作成まで手伝ってくれる場合もあります。こうした業者は補助金制度にも慣れていることが多く、手続きをスムーズに進められるケースも少なくありません。
「一人で進めるのはちょっと不安…」という方は、まずは市町村の窓口で相談してみましょう。
Q:空き家を自治体に寄付できますか?
A:はい、ただし、すべての空き家が無条件で受け入れられるわけではありません。
たとえば、島根県浜田市では「特定空家等対策事業」において、まず空き家を特定空家等として認定したうえで、建物・土地が建築構造・税納付状況・防災リスク・維持管理可能性などの要件を満たす場合に限り、寄附申出を受け付ける制度を設けています。
このように、自らの自治体が寄付を受け入れるか否か、どのような条件かは自治体の制度設計によって大きく異なります。
老朽化が進んでいる建物や、活用用途が見込みにくい土地については、寄付を受けない判断をする自治体も多いため、事前に管轄自治体に制度有無と条件を確認することが不可欠です。
【参考:浜田市特定空家等対策事業】
まとめ
島根県では、空き家のリフォームや解体、取得などに使える補助金制度が多くの市町村で整備されており、状況に応じて費用負担を軽減しながら空き家の利活用を進めることができます。
一方で、すべての空き家が制度の対象となるわけではなく、申請のタイミングや条件、手続きの手間などに注意が必要です。
また、今後使う予定がない、管理や税金の負担を軽くしたいと考えている場合には、売却という選択肢のほうが現実的なケースもあります。
まずは、ご自身やご家族のライフプランと照らし合わせながら、空き家を「再生して残す」のか、「売却して手放す」のかを、無理のない範囲で検討してみてください。
もし、補助金の申請が難しい、解体やリフォームの費用が用意できない、売却先が見つからないといった悩みがある場合は、空き家の買取を専門とする業者に相談することもひとつの方法です。
空き家パスでは、相続物件や再建築不可物件、築年数が古い住宅など、他の不動産会社では敬遠されやすい物件でも対応可能です。
現状のままでの無料査定や買取にも対応しており、手間をかけずに空き家の問題を解決できます。島根県内で空き家に関するお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にご相談ください。