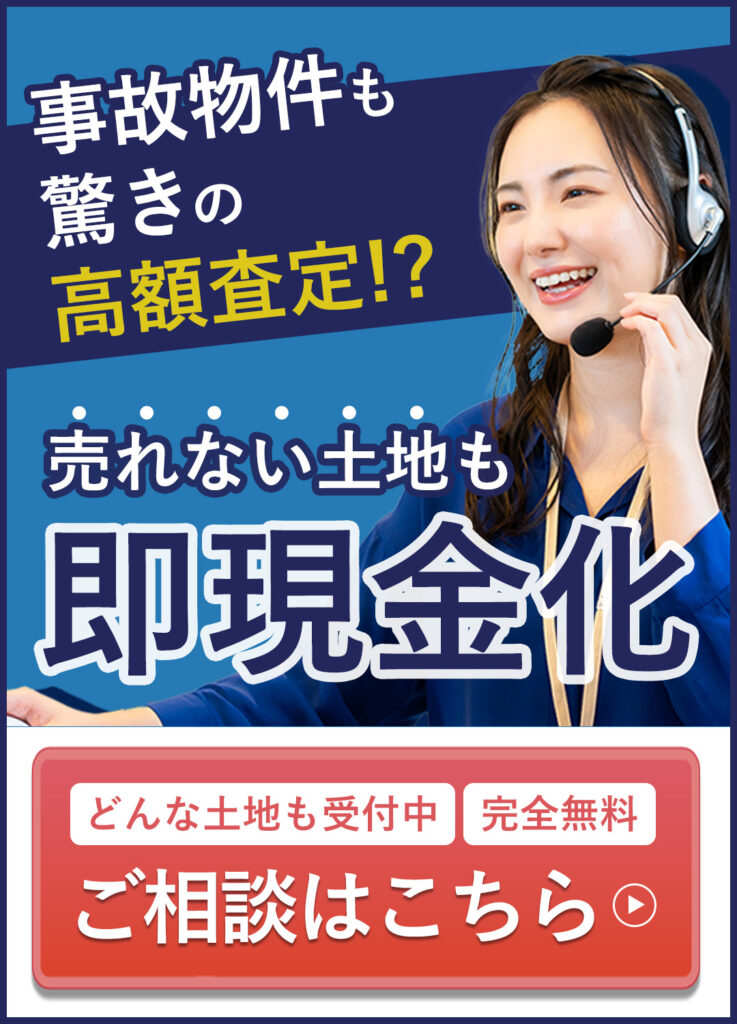建ぺい率オーバーの家は売却できる?適法になる基準や売却方法を解説!
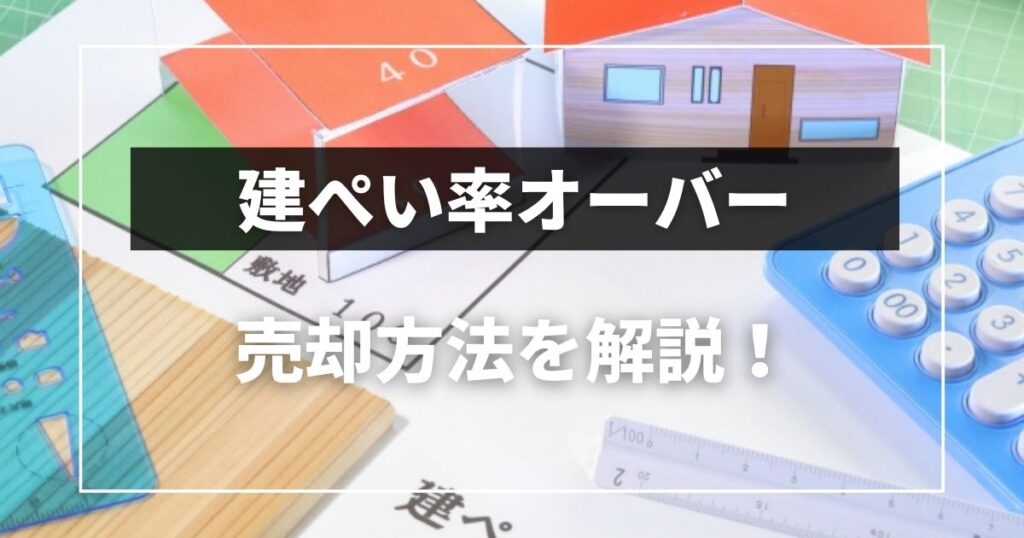
建ぺい率という言葉をご存じでしょうか。
建ぺい率とは、建築基準法で定められた建築上のルールで、土地の広さに対して建てられる建物の建築面積の割合のことです。建ぺい率をオーバーしている建物は、通常の物件に比べて売却しづらくなる可能性があります。
本記事では、建ぺい率オーバーの建物の売却が難しい理由と、建ぺい率オーバーしている物件の売却方法について解説します。
- 建ぺい率オーバー物件とは「敷地面積に対する建築面積の割合のことで、建物が土地の何割まで占めてよいかを定めた建築基準法上のルール」である
- 建ぺい率オーバー物件は「法改正の再確認」「土地の有効活用」などによって、基準内の物件と判断される可能性がある
- 建ぺい率オーバー物件は「適切な価格設定」と「物件のアピール」次第で売却できるため、困りごとがある方は不動産会社に相談することをおすすめする
目次
建ぺい率オーバー物件とは
はじめに、建ぺい率とは何かを知っておきましょう。
建ぺい率とは
建ぺい率とは、建築基準法第53条に定められている、敷地面積に対する「建築面積」の割合のことです。建物を上から見たときに、その土地の何割を占めているかで判断します。用途地域の指定がある場合は、用途地域に応じた建築基準法の規定の範囲で、都市計画が定める数値になります。
例えば、敷地面積100㎡の場合、建ぺい率50%の用途地域であれば、建築面積50㎡までが建築可能になります。
建ぺい率(%)=(建築面積÷敷地面積)×100
建ぺい率オーバーとは
建ぺい率オーバーとは、建ぺい率を超えて建物を建てることを指します。建ぺい率オーバーの建物は、建築基準法違反となります。
建ぺい率、容積率をオーバーしている物件は、違反建築物もしくは既存不適格建築物のどちらかに該当します。
違反建築物とは、現在の建築基準法や都市計画法に違反している建物のことです。例えば、新築時には適法に建てられていた建築物で、その後、車庫や物置などを増築したことで建ぺい率オーバーとなった場合の建築物を指します。
既存不適格建築物とは、当時は適法に建てられていた建築物で、建築基準法や都市計画法などの法令の改正により、その基準に合わなくなった建築物を指します。
建ぺい率オーバー物件の法的な問題
建ぺい率オーバーの物件は、建築基準法や都市計画法などの法律の観点から、さまざまな問題が生じます。
建ぺい率オーバーの物件の対策と活用方法も合わせて見ていきましょう。
建ぺい率オーバー物件の現行法による制限と罰則
建ぺい率オーバー物件は、違法建築物として扱われ、罰則を受ける可能性もあります。建築基準法との関係性を確認しておきましょう。
建築基準法との関連
建ぺい率オーバーの建物は、建築基準法に違反しているため、建物の解体や建ぺい率の縮小などの是正措置を要求される可能性があります。是正措置の要求に応じなかった場合、罰金や命令などの行政処分を受ける可能性もあります。
建ぺい率オーバーの建物を購入する際は、建物の状況をよく確認し、是正措置が必要な場合は、是正措置を行うことができるかどうかを事前に確認しておくことが重要です。
建ぺい率は、敷地内に一定の空地を設けることで、建築物の採光や通風の確保、そして、火災が起きた際に延焼しにくくする防火の観点から定められたルールです。
建物を建築する際は、建築基準法の規定を遵守し、建ぺい率を超過しないように注意しなければなりません。
既存不適格建築物の取扱い
既存不適格建築物の場合は、違反建築物とは異なり、適法な建築物と扱われるため、そのまま使用を続けることが可能です。また、現行法の建ぺい率に反していることを理由として、行政指導を受けることはありません。
ただし、再築や増改築をする際には、現行法の建ぺい率・容積率の制限割合に適合させる必要があります。
建ぺい率オーバー物件に対する法的な対策と今後
先述のとおり、建ぺい率オーバー物件のうち、違反建築物の場合は行政から是正命令を受ける可能性があります。
ただし、違反建築物であっても、法改正の再確認や土地の有効利用によって、建ぺい率オーバーに非該当と判断される可能性もあります。また、以下のような対策を講じることで、建ぺい率オーバー物件ではなくなるかもしれないため、念頭に置いておきましょう。
- 是正命令に従って、建ぺい率を下回るまで建物を縮小する
- 角地緩和や防火規制の適用要件を確認し、建ぺい率の緩和を受ける
建ぺい率オーバー物件か否かを判断するのは自治体ですが、調査自体は不動産会社でも行えるため、気になる方は不動産会社に問い合わせてみましょう。
法改正による影響の再確認
行政によっては土地の接道状況によっては角地緩和の適用により建ぺい率が10%緩和される場合があります。
また、2019年の建築基準法の法改正により、「準防火地域内の耐火建築物・準耐火建築物」についても建ぺい率が10%緩和されることになりました。
土地の有効利用の提案
建ぺい率オーバーの土地を有効利用するには、以下のような方法があります。
- 角地緩和や防火規制の適用要件を確認し、建ぺい率の緩和を受ける
- 建物を解体して、別の建物を建てる
土地の有効利用をする場合も、土地に対して建ぺい率緩和の適用が受けられないかを自治体窓口に相談しましょう。また、土地のある地域が建ぺい率80%とされている地域で、「防火地域」でかつ、「耐火建築物」の建物を建築する場合は、建ぺい率の制限がなくなります(建ぺい率100%になります)。
建ぺい率オーバー物件の売却が難しい理由
建ぺい率がオーバーした物件は、既存不適格建築物であっても売却しづらい特徴があります。主な理由としては、次の2つが挙げられます。
- 住宅ローンが組みづらい
- 建て替えがしづらい
以下にそれぞれの理由を解説します。
住宅ローンが組みづらい
建ぺい率をオーバーしている物件は、住宅ローンの審査が通りづらい傾向があります。既存不適格建築物の担保評価額は低いため、物件を担保に設定できないからです。
金融機関は融資を行う際に、対象の不動産を担保として抵当権を設定しますが、既存不適格建築物は担保としての価値が低いと判断されます。また、違反建築物の場合は、そもそも融資が下ろさない金融機関も数多く存在します。
将来の建て替え問題:規模保持への懸念
建ぺい率をオーバーしている物件は、将来的に建て替えしづらい特徴があります。老朽化が進んだ場合は建物の建て替えを行うのが一般的ですが、既存不適格物件の場合、現行の法令に適合するように建て替える必要があるので、建築物の建築面積が狭くなることが多いです。
そのため、建て替えをする際に、同規模の建築物を建築することができず、建て替えしづらくなる傾向があります。
建ぺい率オーバー物件の売却戦略と手順
建ぺい率オーバーしている物件であっても、適正価格の設定と物件の特徴を活かしたアピールの仕方によっては、売却しやすくなる傾向があります。
適切な価格設定と物件のアピール方法
建ぺい率オーバーの物件であっても、適切な価格設定とアピール方法によって失敗のない不動産売却が可能になります。
物件の価値評価
金融機関からの融資がされづらいとなると、キャッシュでの購入が検討できる価格帯まで物件価格を下げたり、投資用物件であれば周辺相場よりも高い利回り設定をすることで売却に至るケースがあります。
物件の特徴を活かしたアピール
建ぺい率オーバーの物件は、その状況が現行法の制限割合を満たしていないことから、買手にネガティブな印象を持たれるケースもありますが、物件のメリットを的確にアピールすることで売却につながる場合もあります。例えば、建ぺい率割合が現行法の制限を超えていれば、その分の建築面積が大きいため、他の物件より建物が広い場合もあります。
専門的な買取業者への売却
建ぺい率を現行法の制限割合に是正したり、売却方法を工夫したりしても、個人への売却が困難なケースもあります。このような場合は、買取業者への売却を検討しましょう。
買取業者は、仕入れた土地上の建物を解体後、新築した物件を販売する事業を行なっています。また、買取業者へ売却する場合、売主の契約不適合責任は免責になる場合もあるため、物件の引き渡し後に建物についての責任を追及されることもありません。
建ぺい率オーバー物件の改善策とその実例
建ぺい率オーバーの物件であっても、建ぺい率オーバーを現行の法規制に合わせて改善することで売却がしやすくなる可能性があります。改善策にはいくつかの方法があります。それぞれ見ていきましょう。
減築リフォームの実施
建物の一部を撤去するなど、家を狭くする減築リフォームを行えば、現行の建ぺい率を満たした状態で売り出せます。通常の建物と同様に売り出せるので、買手が見つかる可能性が高くなるといえます。
リフォームの費用
減築リフォームの費用は、減築する面積や建物の構造、工事内容などによって大きく異なります。例えば、10平方メートルの部屋を減築する場合、費用は100万円~200万円程度はかかることになるでしょう。そのため、減築リフォームの費用を抑えるためには、減築する面積をできるだけ小さくすることと、複数の業者から見積もりを取ることを必ず行いましょう。
リフォーム後の販売戦略
建ぺい率オーバー物件の減築リフォームを行った後の販売戦略は、以下のような方法が挙げられます。
- 減築リフォームの内容を明確に伝える
- 減築リフォーム後の価格を明確にする
- 減築リフォームを行ったことで現行の法規制に適合していることをアピールする
減築リフォームの内容を明確に伝えることで、購入希望者は物件の詳細を把握することができます。また、減築リフォームを行ったことで現行の法規制に適合していることをアピールすることで、買手は物件の価値を理解することができます。
再調査と見直し
建築当時の土地の敷地面積や建築物の建築面積が誤って計算されている場合があります。
再調査と建ぺい率の見直しを行うことで、建ぺい率オーバーを是正できる可能性があるため、土地測量や建ぺい率算入の見直しなどを行いましょう。
土地測量の誤差
昔から所有していた土地の場合、登記簿上の測量面積と実際の面積に誤差がある場合があります。
測量技術の差により、再度測量することで土地の敷地面積が広くなる可能性もあります。
建ぺい率算入の見直し
建ぺい率は各行政の用途地域ごとに上限が定められていますが、これらの上限は度々見直しが行われており、緩和されることがあります。緩和により建ぺい率の上限内となり、適合となる可能性があります。
現在の対象不動産が存する地域の建ぺい率の上限を、自治体の担当窓口で確認しましょう。
古家付き土地として売却する
建物の築年数が古い場合は「古家付き土地」として売却するのも一つの方法です。
古家付き土地とは、資産的な価値がない住居が建っている土地を指します。買手は土地の購入が主な目的となるので、建物を解体することを前提に購入してもらえます。売手としては、自身でリフォームする手間や費用が省けるメリットもあります。
まとめ
建ぺい率オーバー物件は、違反建築物と既存不適格建築物の2つの場合に分けられます。どちらの場合も、是正を行うことで売却がしやすくなります。
「空き家パス」では、特殊な物件や売却しにくいエリアの物件を数多く買取した実績があります。処分に困っている物件をお持ちの方はお気軽にご相談ください。