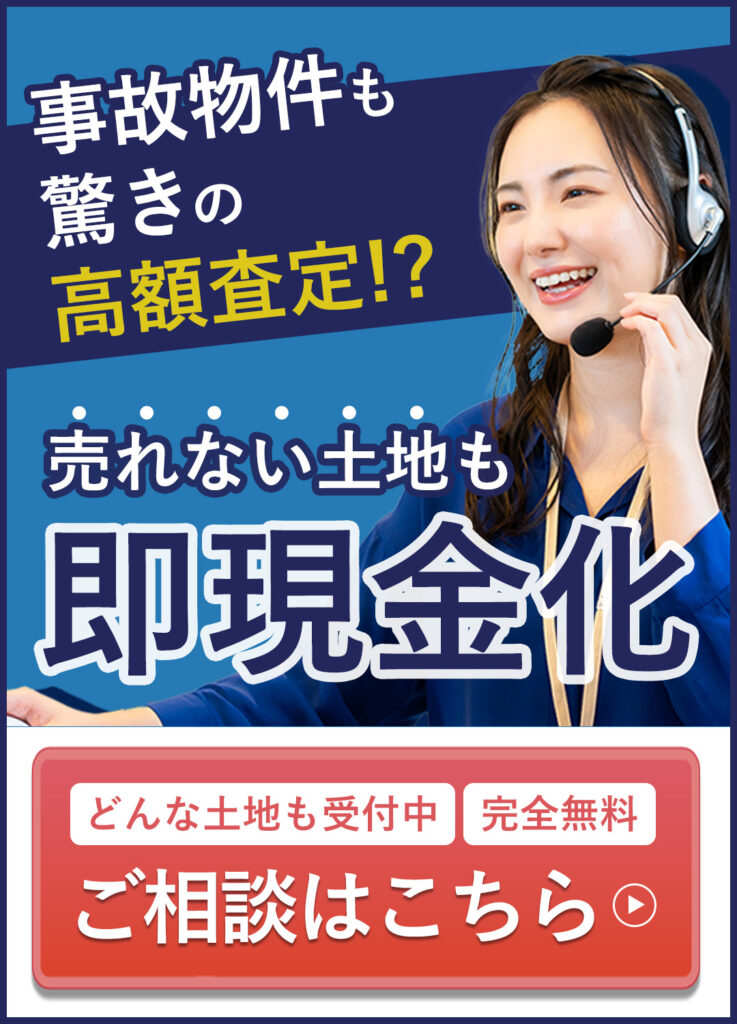不動産引き取りサービスとは?利用時の注意点と確認すべきポイントを解説
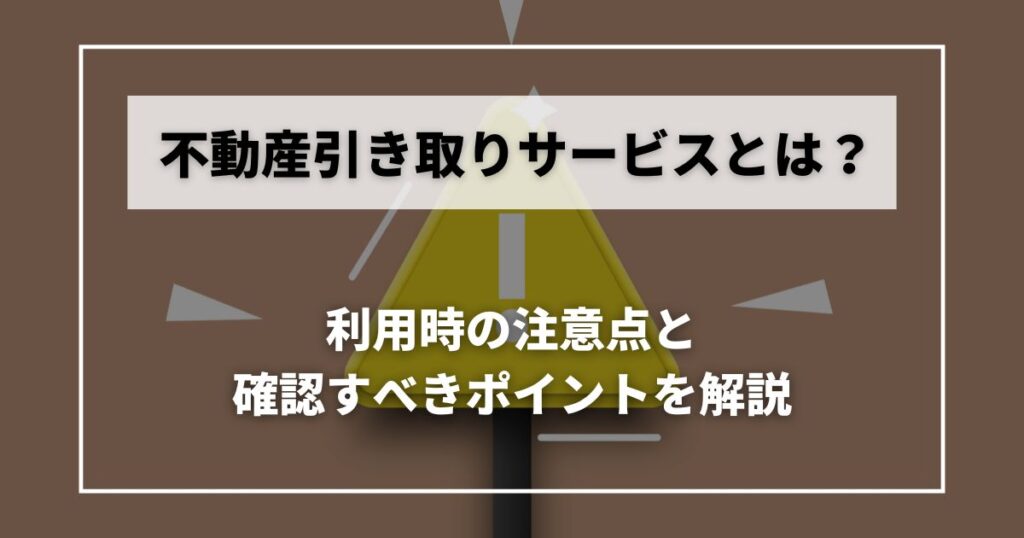
立地条件が悪い、建物の老朽化が進んでいるなどの理由で買い手が見つからず、売却が困難な空き家や不動産を所有している方にとって、維持管理の負担は年々大きくなります。こうした不動産は、売却を希望してもなかなか取引が成立せず、放置されてしまうケースも少なくありません。
売却が難しい不動産を手放す選択肢として、近年注目されているのが「不動産引き取りサービス」です。不動産引き取りサービスでは、売主が費用を支払う代わりに、不動産会社が物件を引き取ってくれます。処分が難しい不動産を所有している方にとって、有効な手段となります。
本記事では、不動産引き取りサービスの概要や利用する際の注意点、事前に確認すべきポイントについて解説します。不要な不動産の処分でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
- 不動産引き取りサービスの仕組みと必要性
- 利用する際のリスクと注意すべきポイント
- サービス利用前に確認すべき事項と対策方法 ・不動産を手放す他の選択肢と比較
相続によって取得した不動産に住む予定がない場合は、売却も選択肢に入れましょう。空き家パスは、相続不動産の買取を得意とした不動産会社です。
相続関係で複雑になっている物件や、田舎の築古物件、再建築不可物件、訳あり物件など、他の不動産会社に断られた空き家でも買取を行っています。ご相談、査定は完全無料です。お気軽にお問い合わせください。
目次
不動産引き取りサービスとは?
不動産引き取りサービスは主に、市場価値が低く売却が難しい物件や、維持管理の負担から早急に手放したい不動産の所有者向けに提供されているサービスです。国土交通省の調査によれば、全国で少なくとも59社(うち宅建業者38社)が不動産引き取りサービスを提供しています。
通常の売買では不動産を手放した側が代金を受け取りますが、不動産引き取りサービスでは逆に、不動産を手放す側が費用を支払う必要があります。
利用料金は物件の状態や立地、規模によって異なりますが、数十万円から数百万円が一般的です。引き取られた不動産は、再販、賃貸、解体後の土地活用など様々な形で運用されます。
空き家が増えている背景
日本では人口減少と高齢化に伴い、空き家の数が増加しています。総務省の調査によると、2018年時点で全国の空き家数は約849万戸、空き家率は13.6%に達しています。
空き家が増加している背景には、相続した実家を活用できない、住み替えで前の住居が売れない、賃貸需要が少ないなどの要因があります。特に地方や郊外の物件は需要が少なく、売却や活用が困難なケースが多いです。
また、空き家を所有していると、固定資産税や都市計画税、火災保険料など年間で数万円から数十万円の維持コストがかかります。こうした経済的負担を軽減するための選択肢として、不動産引き取りサービスが利用されています。
特定空家に指定されるリスク
空き家を適切に管理せずに放置すると、「特定空家等」に指定されるリスクがあります。2015年に施行された空家等対策特別措置法により、周辺環境に悪影響を及ぼす空き家は特定空家等に認定され、行政による強制措置の対象となります。
特定空家等に指定される主な条件は以下の通りです。
- 保安上危険となるおそれのある状態(建物の倒壊リスクなど)
- 衛生上有害となるおそれのある状態(ゴミの放置、害虫発生など)
- 著しく景観を損なっている状態
- 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
特定空家等に認定されると、行政からの助言・指導に始まり、勧告や命令、最終的には行政代執行による強制解体まで、段階的な措置が講じられます。この場合、解体にかかる費用は所有者に請求され、数百万円の負担となる可能性があります。さらに、住宅用地特例が適用されなくなることで、固定資産税が最大6倍に増額される恐れもあります。
有料で不動産を引き取るサービス
不動産引き取りサービスは、所有者が費用を支払って物件を手放す仕組みで、比較的短期間で所有権の移転が可能です。また、老朽化が進んだ建物や、立地条件が悪く売却が難しい物件も対象となります。
料金体系は物件の状態や引き取り後の活用可能性によって異なります。再販可能な物件であれば比較的安価ですが、山林や再建築不可の土地など活用が難しい物件では高額になる傾向があります。
特に相続した不動産や遠方の物件、管理が困難な物件の所有者にとっては、維持費や修繕リスクといった負担を手放す手段として有効です。
不動産引き取りサービスの注意点
不動産引き取りサービスは便利な選択肢ですが、法的なルールが整っていないケースもあるため、トラブルを避けるには、契約前に内容をしっかり確認するなど、慎重な対応が求められます。国土交通省の調査では、引き取りサービスに関して宅建業法等による規制が及ばない場合が多いと指摘されています。
特に気をつけるべきは、不適切な料金設定や契約内容、所有権移転後の管理状況です。通常の不動産取引と異なり、業者に支払う費用の適正さを判断するのが難しいため、十分な情報収集と比較検討が欠かせません。
悪質な業者に騙されないためには、契約前の業者調査と複数社からの見積もり取得が重要です。不安な点は法律の専門家への相談も検討しましょう。
詐欺など悪徳業者も存在する
不動産引き取りサービスの市場には、詐欺まがいの営業を行う悪徳業者も存在します。国土交通省は「第三の原野商法詐欺」と呼ばれるような問題が発生しないよう注意喚起を行っています。
典型的な悪質業者の手口としては、実際より極端に高い料金請求、不要な追加費用の請求、契約内容を曖昧にする、所有権移転登記をせずに料金だけ受け取る、引き取った不動産を放置するなどが挙げられます。
特に注意すべきは、「今なら特別価格」「期間限定キャンペーン」などと称して契約を急かす業者です。不動産取引は慎重に進めるべきであり、十分な検討時間が必要です。不審な点があれば、消費者ホットライン(188)や地域の消費生活センターに相談しましょう。
宅建免許を持たない業者もいる
不動産引き取りサービスを提供する業者の中には、宅地建物取引業(宅建業)の免許を持たない事業者も存在します。国土交通省の調査結果によれば、引き取りサービスを提供する59社のうち、宅建業免許を持たない事業者は19社(約32.2%)に上っています。
宅建業免許がない業者の利用は、宅建業法による規制や監督が及ばない、重要事項説明などの法定開示義務がない、トラブル発生時の行政指導や監督処分による是正が期待できないなどのリスクがあります。
宅建業免許の有無は、国土交通省の「宅地建物取引業者検索システム」で確認できます。業者選びの際には、免許番号の確認と有効期限のチェックを必ず行い、免許を持つ事業者を選ぶことで、より安全な取引が期待できます。
参考:国土交通省 | 宅地建物取引業者 検索
不動産引き取りサービスを利用する前にチェックすべきこと
不動産引き取りサービスを利用する際には、安全な取引のための事前確認が重要です。国土交通省のガイドラインでも、取引の安全性確保、適正価格での取引機会確保、引き取り後の適正管理確保という3つの観点から注意点が示されています。
特に重要なのは、業者の信頼性確認と契約内容の精査です。不動産の引き取りは高額なサービスとなるため、十分な調査と比較検討が欠かせません。以下では、サービス利用前に確認すべき項目について説明します。
複数の不動産会社に査定を依頼する
不動産引き取りサービスを検討する前に、まずは通常の売却可能性を探るため、複数の不動産会社に査定を依頼しましょう。市場での売却が可能であれば、引き取りサービスよりも経済的に有利になるケースが多いためです。
一般的な仲介会社だけでなく、買取専門の不動産会社にも査定を依頼し、可能であれば訪問査定も受けましょう。相続や再建築不可といった特殊な事情がある場合は事前に説明し、査定額の根拠や市場の動向についても具体的な確認が重要です。
宅地建物取引業の免許があることを確認する
不動産引き取りサービスを利用する際は、宅地建物取引業の免許を持つ業者かどうかを必ず確認しましょう。この免許は、法律に基づいた不動産取引を行うために必要なものであり、信頼性のある業者であるかを判断する重要な基準となります。
免許の有無は、業者のウェブサイト、名刺、契約書などに記載された「免許番号」で確認できます。免許番号の( )内にある数字は免許の更新回数を表し、数字が大きいほど営業年数が長いことを示します。
さらに確実を期すためには、国土交通省が提供する「宅地建物取引業者検索システム」で業者名や免許番号を入力し、実際に登録されているかを照会しましょう。検索結果には免許の有効期間や業者の所在地なども表示されるため、信頼性の判断に役立ちます。
宅建業免許を持つ業者は宅建業法に基づく規制や監督の対象となり、消費者保護の観点から安心できる要素となります。また、営業保証金の供託義務もあり、トラブル時の補償制度が整備されています。
契約内容を事前にしっかり確認する
不動産引き取りサービスの契約を結ぶ前に、契約書の内容を細部まで確認することが極めて重要です。契約書は法的拘束力を持つ文書であり、後のトラブル防止のためにも内容を十分理解する必要があります。
特に確認すべきは、引き取りサービスの正確な料金とその内訳、支払いのタイミングと方法、所有権移転登記の時期と手続き、契約後のキャンセル条件と違約金、物件内の残置物の取り扱いなどです。
契約内容に不明点や疑問点がある場合は、必ず契約前に質問し、納得のいく説明を受けることが大切です。不安がある場合は、契約前に司法書士や弁護士などの法律の専門家に契約書をチェックしてもらうことも検討しましょう。
契約不適合責任が免責であることを確認する
不動産取引では、引き渡された物件に欠陥があった場合に売主が責任を負う「契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)」が重要な要素となります。
しかし、不動産引き取りサービスの契約では、多くの場合、契約不適合責任が免責とされています。 この免責が適用されると、引き渡し後に見つかった不具合について売主が責任を問われることはありません。 そのため、不動産引き取りサービスを利用する際は、契約書に免責条項が明記されているかを事前に確認し、内容を十分に理解したうえでの契約が大切です。
万が一、免責条項がない場合や内容が不明確な場合は、後々トラブルに発展する可能性があるため、契約前に専門家への相談も検討しましょう。
料金支払い前に所有権移転登記が行われたか確認する
不動産引き取りサービスを利用する際は、料金の支払いと所有権移転登記の順序が最も重要な確認ポイントです。安全な取引のためには、所有権移転登記の完了を確認してから料金を支払うようにしましょう。
所有権移転登記の確認方法としては、法務局で登記事項証明書を取得する、司法書士から所有権移転登記完了の報告書を受け取る、オンラインの登記情報提供サービスを利用する、といった方法があります。
料金の支払いが先になると、所有権が移転されなかったり、第三者に転売されるといったリスクが生じる可能性があります。契約は「契約締結→所有権移転登記→支払い」の順で進めるのが理想です。やむを得ず同日に行う場合は、司法書士などの専門家に立ち会ってもらい、売買と所有権移転登記を同時に完了させる形を取りましょう。
参考:登記情報提供サービス – 法務省
相続土地国庫帰属制度という選択肢もある
不動産引き取りサービス以外にも、不要な土地を処分する制度として「相続土地国庫帰属制度」があります。これは2023年4月27日から施行された制度で、相続などで取得した土地を一定の要件のもとで国に引き渡すことができる仕組みです。
相続土地国庫帰属制度を利用するには、すべての土地が無条件に引き渡せるわけではなく、法令で定められた一定の要件を満たす必要があります。
主な条件は以下のとおりです。
- 相続または遺贈によって取得した土地であること
- 所有権以外の権利(地上権、賃借権、抵当権など)が設定されていないこと
- 建物、工作物、車両などが存在しないこと
- 管理や処分に過度の費用や労力を要する土地でないこと
- 土壌汚染や埋設物などがなく、安全性に問題がないこと
これらの条件を満たしていない土地については、制度の利用が認められない可能性があるため、制度の活用を検討する際は、土地の状態や権利関係を事前に確認し、専門家への相談をおすすめします。
申請から承認までは、法務局への審査申請、法務大臣による審査、承認・不承認の通知、負担金納付、国庫への帰属という流れで進みます。負担金は10年分の管理費相当額で、一般的な宅地で約20万円~30万円、更地なら約10万円〜20万円程度です。
制度の利点は確実に土地を手放せることと比較的低コストである点ですが、建物がある土地や問題のある土地は対象外で、申請から承認まで1年程度かかる点も考慮が必要です。
参考:法務省:相続土地国庫帰属制度について
まとめ:空き家パスなら他社に断られた物件でも対応
不動産引き取りサービスは、老朽化した建物や立地条件が悪く市場で売却が難しい物件を手放したい所有者にとって、有効な選択肢です。
ただし、サービスを安全に利用するためには、以下の点に注意が必要です。
- 宅建業の免許を持つ信頼できる業者を選ぶ
- 複数の不動産会社に査定を依頼し、相場を把握する
- 料金支払い前に所有権移転登記が完了しているか確認する
相続した土地については「相続土地国庫帰属制度」を活用できる場合もありますが、建物付きの物件や問題を抱える土地は対象外です。制度の適用条件を正しく理解し、物件の状況に応じた最適な処分方法を選びましょう。
空き家パスでは、再建築不可物件や相続トラブルを抱えた土地、山林、遠方の空き家など、他社で断られた物件でも柔軟に対応しています。
「こんな物件は売れないだろう」と諦めかけていたケースでも、現状のままでの査定・買取が可能です。残置物の撤去や解体の有無にかかわらずご相談いただけますので、手間なくスムーズに手放したい方に最適です。
全国対応で、査定や相談はすべて無料。LINEやオンラインフォームから簡単に申し込みができるため、忙しい方や遠方にお住まいの方でも安心してご利用いただけます。
不要な不動産でお悩みの方は、ぜひ一度空き家パスへご相談ください。