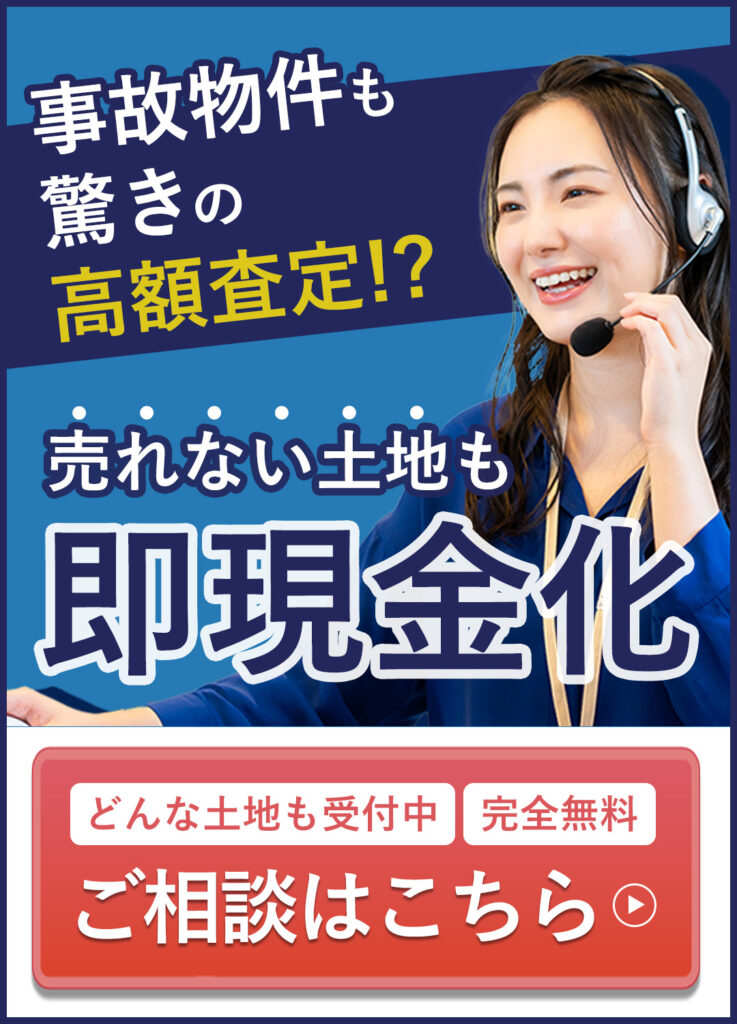不動産は個人間売買可能?メリット・デメリットと注意点、おすすめサイトを紹介
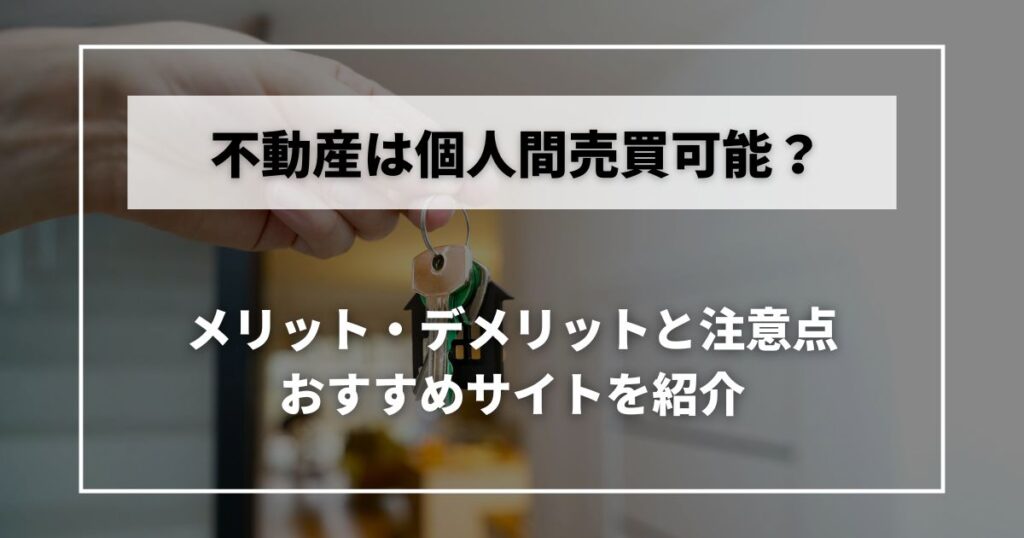
不動産の個人間売買では、不動産会社を介さないため仲介手数料が不要になり、売却費用を大幅に抑えられます。売主と買主が直接交渉できるため、価格や取引条件を柔軟に決められるのも大きな利点です。
しかし、契約書の作成や法的手続きには専門的な知識が求められ、必要な書類の準備や手続きの流れを正しく理解していなければ、取引後にトラブルへ発展するリスクがあります。適正価格の設定、必要書類の準備、登記手続きなど、すべてを自分で対応する必要がある点も注意が必要です。
近年は、個人間売買をサポートするオンラインサービスも増え、取引のハードルが下がっています。ただし、不動産は高額な取引であるため、契約内容の確認や手続きの進め方に十分注意しなければなりません。
本記事では、不動産の個人間売買のメリット・デメリット、注意点、取引の流れ、サポートサービスについて詳しく解説します。
- 不動産の個人間売買の仕組みと適している取引ケース
- 個人間売買のメリット・デメリットと費用面での影響
- トラブルを防ぐために押さえるべき注意点と対策
- 買手が見つからない訳あり物件の効果的な売却方法
相続不動産や長年住んでいない物件の買手が見つからない場合は買取サービスが有効です。空き家パスは相続不動産買取を専門とし、築古物件や再建築不可物件、訳あり物件も積極的に買取します。相談・査定は無料ですのでお気軽にご連絡ください。
目次
不動産の個人間売買は可能
不動産の個人間売買は宅地建物取引業法による制限がなく、民法に基づく一般的な売買契約として法律上認められています。
ただし、実際の取引では多くの専門的な手続きが必要となり、売主と買主の双方が不動産取引の流れを理解していることが重要です。不動産会社を介さない取引では、書類作成や法的手続きなどの負担と責任が当事者自身にかかる点が最大の特徴といえます。
個人間売買と仲介の違い
不動産の個人間売買と仲介取引では、コスト面だけでなく責任の所在やサポート体制に大きな違いがあります。両者の主な相違点は以下の通りです。
| 項目 | 個人間売買 | 仲介取引 |
|---|---|---|
| 取引の主体 | 売主と買主が直接契約 | 不動産会社が間に入る |
| 宅建士の関与 | 任意(義務なし) | 必須(法的義務あり) |
| 重要事項説明 | 法的義務なし | 宅建士による説明が必須 |
| 物件調査 | 自分で行う | 不動産会社が調査 |
| 価格設定 | 市場相場の把握が難しい | 豊富な事例に基づく適正価格 |
| 買主探し | 個人のネットワークが中心 | 広告・ポータルサイトの活用 |
| 契約書作成 | 自分で作成または専門家に依頼 | 不動産会社が準備 |
| トラブル対応 | 当事者間で解決 | 仲介会社が調整役に |
| 所有権移転 | 自分で手続きまたは司法書士に依頼 | 不動産会社がサポート |
仲介取引では、宅地建物取引業法に基づく規制があり、不動産会社には重要事項説明義務や契約内容の説明義務などが課せられています。これにより買主は物件の瑕疵やリスクについて十分な情報を得られる一方、個人間売買では物件の問題点や状況について、売主が持つ情報と正直に伝える姿勢に左右されます。
また、仲介取引では物件調査や境界確認、権利関係のチェックなど専門的な調査を不動産会社が実施しますが、個人間売買ではこれらを自分で行うか、別途専門家に依頼する必要があります。
個人間売買が行われるケース
不動産の個人間売買は特定の状況下で選択されることが多く、それぞれのケースに応じたメリットがあります。以下に代表的な事例を紹介します。
| ケース | 特徴 | 具体例 |
|---|---|---|
| 親族・知人間の取引 | 相互信頼があり、情報共有が容易 |
・親から子への住宅継承 ・親族間での実家売買 |
| 高額物件の取引 | 仲介手数料の節約額が大きい | 高級マンション、広大な土地の売買 |
| 特殊条件のある取引 | 標準契約では対応しにくい条件設定 | 売却後も居住継続、家具・設備込みの取引 |
| 訳あり物件の取引 | 通常の仲介では買主探しが困難 | 再建築不可物件、接道不良物件の売買 |
親族や知人間の取引では、相互の信頼関係があり、物件の状態や履歴について十分な情報共有ができる関係性では、仲介手数料を節約できる個人間売買が選ばれます。このケースでは契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)によるトラブルリスクが低く、取引後も良好な関係を維持しやすいのが特徴です。
高額物件の取引では、物件価格が高額になるほど、仲介手数料の絶対額も大きくなります。例えば1億円の物件では、仲介手数料が330万円(税込)以上になるため、コスト削減効果が顕著です。ただし、高額取引ほどリスク管理も重要になるため、司法書士や弁護士などの専門家関与は必須と考えるべきです。
特殊な条件や柔軟な取引が必要な場合、売買と賃貸を組み合わせる取引や家具・設備込みでの取引、修繕義務や将来の買戻し特約など複雑な条件を含む取引に個人間売買の柔軟性が活かされます。
また、一般的な市場では売りにくい「訳あり物件」の場合、状況を理解した特定の買主との個人間取引が選択されることがあります。ただし、このようなケースでは物件の問題点を明確に説明し、買主の十分な理解を得ることが特に重要です。
不動産を個人間売買するメリット
不動産の個人間売買には複数のメリットがあります。仲介手数料の節約から取引の自由度の高さまで、売主と買主の双方にとって大きな利点があります。ただし、メリットを最大限に活かすには適切な準備と知識が必要です。個人間売買の主なメリットを詳しく解説します。
仲介手数料がかからない
不動産の個人間売買で最も大きなメリットは、仲介手数料が発生しない点です。不動産会社に仲介を依頼すると、売買価格に応じた仲介手数料を支払う必要があります。一般的な計算方法は以下のとおりです。
-
・200万円以下:売買価格 × 5%
・200万円超~400万円以下:売買価格 × 4% + 2万円
・400万円超:売買価格 × 3% + 6万円
例えば、売買価格3,000万円の物件では、(売買価格 × 3% + 6万円)で合計96万円の仲介手数料が発生します(税別)。
個人間売買では、この仲介手数料を節約できるため、売主は手取り額を増やせるだけでなく、買主に対して仲介手数料分を価格から差し引いた提案も可能です。特に高額物件では、節約できる金額が大きくなります。
ただし、個人間売買でも所有権移転登記などの手続きは必要です。司法書士への報酬や契約書作成費用が発生するため、事前に必要な手続きを把握しておくことが大切です。
価格交渉を柔軟に行える
不動産の個人間売買では価格交渉を直接行えるため、両者にとって納得のいく価格設定が実現しやすくなります。仲介会社を通さないため、売主と買主が互いの事情や希望を直接伝え合いながら交渉できます。
例えば、買主が物件に強い関心を持ちながらも予算に制約がある場合、売主は修繕箇所や引き渡し条件の調整によって価格を調整する提案もできます。また、決済時期の調整や残置物の取り扱いなど、価格以外の条件も合わせて交渉できる点が大きな利点となります。
不動産会社を介した場合、交渉内容が仲介会社を通じて伝えられるため、細かなニュアンスが伝わりにくいケースもあります。個人間売買ではコミュニケーションを直接取れるため、スムーズな合意形成が期待できます。
ただし、感情的になりやすい交渉では冷静さを欠く恐れもあります。適正価格の把握や市場相場の理解など、価格交渉の前提となる情報収集は欠かせません。
取引の自由度が高い
不動産の個人間売買では、取引条件を自由に設定できる点が大きなメリットです。不動産会社を介した取引では、標準化された契約書が使用されることが一般的ですが、個人間売買では双方の合意に基づいた柔軟な条件を設定できます。
仲介利用時と個人間売買の比較
| 項目 | 不動産会社を介する取引 | 個人間売買 |
|---|---|---|
| 契約内容 | 既定のフォーマット | 双方の合意に基づき自由に設定可能 |
| 引き渡し時期 | 不動産会社の標準スケジュール | 柔軟に調整可能 |
| 設備・家具の譲渡 | 基本的に対象外 | 取引条件として自由に追加可能 |
| 賃貸契約との組み合わせ | 原則不可 | 売買後も一定期間住み続ける契約が可能 |
| 物件確認・打ち合わせ | 営業時間内のみ対応 | 休日や夜間など柔軟に対応可能 |
例えば、売主が一定期間住み続けたい場合、売買契約と賃貸契約を組み合わせることが可能です。また、物件の確認や打ち合わせも不動産会社の営業時間に縛られず、休日や夜間でも柔軟に対応できます。
ただし、自由度が高い分、法的に無効となる条件を設定しないよう注意が必要です。基本的な不動産取引のルールや法規制を理解した契約が必要です。
不動産を個人間売買するデメリット
不動産の個人間売買にはメリットだけでなく、注意すべきデメリットも存在します。専門知識の不足やトラブルリスクなど、認識しておくべき課題について解説します。
買主とトラブルになりやすい
個人間売買では仲介者がいないため、取引後にトラブルが発生するリスクが高まります。2020年4月の民法改正で導入された「契約不適合責任」により、売主の責任が強化されました。
契約不適合責任とは、物件が契約内容と異なる場合に売主が負う責任です。売買後に雨漏りや白蟻被害が発見された場合、買主は売主に対して修補請求や損害賠償を求められます。不動産会社を介した取引では重要事項説明などでリスク開示が徹底されますが、個人間売買では不動産会社による専門的なチェックが省かれがちです。
トラブル防止には、物件の状態を詳細に記録した資料を作成し、問題点も含めて買主に明示しましょう。
契約や手続きなどの専門知識が必要
不動産取引には法令や税制、契約書作成、所有権移転手続きなど幅広い専門知識が求められます。
特に契約書の作成は重要です。適切な契約書を作成しないと、後々のトラブルに発展したり、契約自体が無効となる場合があります。手付金の取り扱い、引き渡し条件、契約不適合責任などの条項を適切に盛り込む必要があります。
また、不動産取引に関わる税金(譲渡所得税、印紙税など)の知識も必要です。確定申告の方法や税額計算、特例適用の条件など、税制面での専門知識がないと思わぬ税負担が生じます。
書類作成や手続きが煩雑で面倒
不動産の個人間売買では多くの書類作成や手続きを自分で行う必要があり、多大な時間と労力がかかります。
売買契約書の作成では、物件情報、契約条件、特約事項などを正確に盛り込む必要があり、印紙税の計算と納付も必要です。所有権移転登記の申請は複雑な手続きを要し、一般の方には難しい作業となります。
住宅ローンを利用する買主の場合、金融機関が求める多くの書類を準備する必要があります。不動産会社を介した取引では仲介会社がサポートする部分も、個人間売買では自分たちで対応しなければなりません。
そもそも買手が見つからないことがある
個人間売買の大きなデメリットは、買主を見つけることの難しさです。不動産会社は豊富な顧客ネットワークと広告力を持っていますが、個人での販売活動には限界があります。
また、買主が住宅ローンを利用する場合、個人間売買では融資審査が厳しくなる傾向があります。不動産会社を通さない取引では、金融機関が求める重要事項説明書を用意することが難しく、審査に通らない状況が多く発生します。売買契約の内容や物件の詳細を証明する書類が不足すると、金融機関が担保評価を適正に行えず、融資の承認を得にくくなります。
さらに、再建築不可物件や接道不良物件、古い建物など、「訳あり物件」の場合は買主が特に見つかりにくくなります。物件の魅力を十分に伝えられない状況が頻繁に発生し、売却が長期化する傾向にあります。
不動産を個人間売買する流れ
不動産の個人間売買を円滑に進めるには、準備から引き渡しまでの流れを正確に把握することが重要です。基本的な手順を以下の表にまとめました。
不動産の個人間売買の流れ
| ステップ | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1. 売却不動産の調査 | 物件の所在地、面積、権利関係を確認し、登記簿謄本や固定資産税評価証明書を取得する。 | 登記内容と現状の相違を確認。未登記建物や越境がある場合は事前対応が必要。 |
| 2. 適正価格の確認 | 近隣の売買事例や査定サイトを参考に市場相場を調べる。 | 極端に安い価格は贈与と見なされ、贈与税の対象となる可能性がある。 |
| 3. 買主の募集 | 知人・親族への紹介や個人売買サイトを活用し、物件情報を発信する。 | 誇張表現や虚偽の情報は避ける。後のトラブルを防ぐため正確に記載する。 |
| 4. 物件の内覧対応 | 良い点だけでなく、補修が必要な部分も伝える。 | 問題を隠すと契約不適合責任を問われる可能性があるため注意。 |
| 5. 売買契約の締結 | 価格、支払方法、引渡日などを明記した契約書を作成し、司法書士に相談する。 | 口約束は避け、契約内容を明確にして双方が納得した上で締結する。 |
| 6. 手付金の受領 | 契約時に買主から手付金(売買価格の10%目安)を受け取る。 | 返還条件を契約書に明記し、契約解除時の扱いを確認する。 |
| 7. 住宅ローン手続き | 必要書類を確認し、金融機関に事前相談する。 | 個人間売買では融資が制限されることがあるため、早めに対応。 |
| 8. 最終決済と引き渡し | 残金を受け取り、物件と鍵を引き渡す。司法書士立会いで所有権移転登記を行う。 | 代金決済と登記申請は同時に進め、正式な所有者変更を確認する。 |
個人間売買では、各段階で専門知識が求められるため、不明点がある場合は司法書士や専門家に相談することを推奨します。
不動産の個人間売買で注意すべきポイント
不動産の個人間売買は専門知識と慎重な判断が求められる取引です。トラブルを防ぎ安全な取引を実現するために、特に重要なポイントを解説します。
買手をしっかり選ぶ
不動産の個人間売買では、取引相手の選定が最重要です。2020年4月の民法改正で「瑕疵(かし)担保責任」から「契約不適合責任」へと売主責任が変更され、売主リスクが高まりました。契約不適合責任とは、物件が契約内容に適合しない場合に買主から追完請求や損害賠償を求められる責任です。
個人間売買は「敵対的な責任追及をしない相手」に限定すべきです。親族や知人など信頼関係がある相手との取引が安全です。買主にとっても「買主自身がよく知っている物件」に限定するのが重要で、不測の損害を避けられます。
全く知らない第三者とインターネット経由で高額物件を売買する状況は回避すべきです。互いの信頼関係が構築できない状況では契約不適合責任によるトラブルリスクが高まります。
適切な価格設定を行う
個人間売買では適正価格での取引が必須です。著しく低廉な価格での売却は贈与とみなされ、買主に贈与税が課されるケースもあります。法人が代表者に不動産を安く売り意図的に売却損を出すと、脱税行為とみなされるリスクもあります。
適正価格の把握には複数の不動産会社に査定依頼するか、不動産鑑定士による鑑定評価書の取得が効果的です。鑑定評価額に基づいた取引は贈与認定リスクを減らせます。
物件状態や立地、市場動向を考慮し、売主・買主双方が納得できる価格設定を心がけましょう。
物件に合致したひな形を用いる
不動産売買契約書は物件種類に合った適切なひな形を使用するのが重要です。土地売買契約書、建物売買契約書、土地建物売買契約書など、物件に合致した契約書を選ぶ必要があります。
2020年4月の民法改正に対応した最新の契約書ひな形を使用しましょう。古い契約書を使うと売主に不測の損害が生じる可能性があります。契約不適合責任を適切に回避するには、免責事項を特約に明記するのが重要です。
契約書には物件詳細情報、取引条件に加え、特約事項として契約不適合責任の範囲や期間を明確に記載しましょう。
必要に応じて専門家に依頼する
個人間売買でも専門家サポートは重要です。特に登記手続きは司法書士への依頼が推奨されます。所有権移転登記や抵当権抹消手続きは専門知識が必要で、ミスがあると大きなトラブルになります。
住宅ローンが関わる取引では、銀行が司法書士を通じた登記手続きを求めることが一般的です。「買主による金銭支払い」と「売主による権利証引渡し」は利害が対立する行為なので、第三者である司法書士の立会いがトラブル防止になります。
税金関連の相談は税理士に、契約書作成や法的アドバイスは弁護士への依頼も検討しましょう。
かかる税金を把握しておく
不動産の個人間売買では様々な税金が発生します。売主側の主な税金は譲渡所得税であり、不動産の保有期間が5年以下の場合は39.63%、5年超では20.315%の税率が適用されます。居住用不動産の売却には3,000万円特別控除や居住用財産の買換え特例などが利用可能なため、適用条件を確認すれば税負担を軽減できる場合があります。
買主側では不動産取得税、登録免許税、印紙税などの支払いが必要です。
個人事業主が事業用不動産を売却する場合、建物部分に消費税が発生する点にも注意が必要です。一般的な居住用不動産売却は非課税となりますが、アパートなど事業用不動産は消費税の課税対象となります。
不動産の個人間売買におすすめのサイト
不動産の個人間売買を進める際には、適切なプラットフォームの選択が重要です。近年はインターネット上で個人間取引をサポートするサービスが充実しており、物件掲載から契約サポートまで多様なサービスが提供されています。物件の特性や希望する支援内容に応じて最適なサイトを選びましょう。
e-物件情報
e-物件情報は、不動産の個人間売買および賃貸を支援するサイトです。売主は有料で物件を掲載でき、掲載期間に制限がないため、成約まで情報発信ができます。個人だけでなく、不動産仲介業者やエージェントも閲覧するため、良い条件での取引が期待できます。
物件情報の掲載・管理がしやすく、自由度の高い取引ができます。基本的に当事者同士で直接交渉や手続きを行いますが、必要に応じてプロへのサポート依頼もできます。法的手続きや価格設定など、専門的なアドバイスを受けられるサービスも提供されています。
e-物件情報
家いちば
家いちばは、個人間での不動産直接取引を支援するプラットフォームです。空き家や古民家、山林など幅広い物件を扱い、売主と買主が直接やりとりできるのが特徴です。物件掲載は無料で、成約時のみ手数料が発生します。
セルフサービスが基本ですが、契約段階では宅建士による調査や書類作成、重要事項説明などのサポートがあり、安全な取引を実現しています。また、取引の各段階で専門スタッフに相談できる体制も整っています。
家いちばとは
ジモティー
ジモティーは、地域密着型のクラシファイドサイトで、不動産の個人売買を含む幅広い情報交換プラットフォームです。掲載料は無料で、個人間での直接取引ができます。地域別の物件情報や相場情報を提供しており、特に地元の買主へのアピールに効果的です。
27万件以上の不動産情報が掲載されており、個人だけでなく不動産業者も利用しています。取引の安全性を高める「あんしん決済機能」も提供していますが、契約手続きなどは基本的に当事者同士で進める必要があります。
ジモティー
不動産直売所
不動産直売所は、仲介手数料なしで個人間の不動産売買ができるプラットフォームです。売主と買主が直接交渉でき、掲載料や広告費も一切かかりません。相続した土地や売却が難しい不動産の処分にも対応しており、山林や地方の空き地の引き取りサービスも提供しています。売却手続きを簡単に進めたい場合や、不動産業者に断られた物件を手放したい場合に便利です。
不動産直売所
チョクウリ・チョクカイ
チョクウリ・チョクカイは、空き家や相続不動産、訳あり物件などの売却を支援します。掲載料や購入手数料は無料で、売却が成立した場合のみ25万円(税込)の費用が発生します。
売買契約書のダウンロードや司法書士への依頼も可能で、安心して手続きが進められる仕組みを提供しています。
チョクウリチョクカイ
不動産個人間売買サポートPRO
不動産個人間売買サポートPROは、株式会社ホームスタッフが運営する個人間不動産取引専門のサポートサービスです。契約書作成を中心に、物件調査代行、測量・登記手配など幅広いサポートを提供しています。
契約書作成は29,800円からと業界最安値クラスの料金設定で、必要なサポートを選択できる柔軟なプラン構成が特徴です。住宅ローン利用可能なプランや、個人間買取交渉の代行など、多様なニーズに対応しています。不動産取引の経験豊富な専門家が、安全で円滑な個人間取引をサポートします。
不動産個人間売買サポートPRO
買手が見つからない訳あり物件なら買取がおすすめ
不動産の個人間売買では、再建築不可物件や接道不良物件、築年数が古い建物など「訳あり物件」の買主を見つけることが困難です。2020年4月の民法改正による契約不適合責任の影響も大きく、特に物件状態を完全に把握できない空き家では、売主は引き渡し後のトラブルリスクを抱えることになります。
トラブルリスクを回避する有効な方法が「買取」です。買取専門の不動産会社は物件の状態や立地に関わらず、現状のままで購入するケースが多いです。空き家パスは相続不動産の買取に特化しており、築古物件や再建築不可物件、接道不良物件など、一般の不動産会社で断られるような訳あり物件も積極的に買取しています。
買取では物件の状態に関する責任も買取会社が負うため、契約不適合責任によるトラブルを心配する必要がありません。また、残置物の撤去や解体費用を売主が負担せずに売却できることも多く、手間とコストを削減できます。
遠方にある実家や相続した空き家など、管理が難しい物件は早期売却をおすすめします。空き家パスは全国対応で、ご相談・査定は完全無料です。お気軽にお問い合わせください。