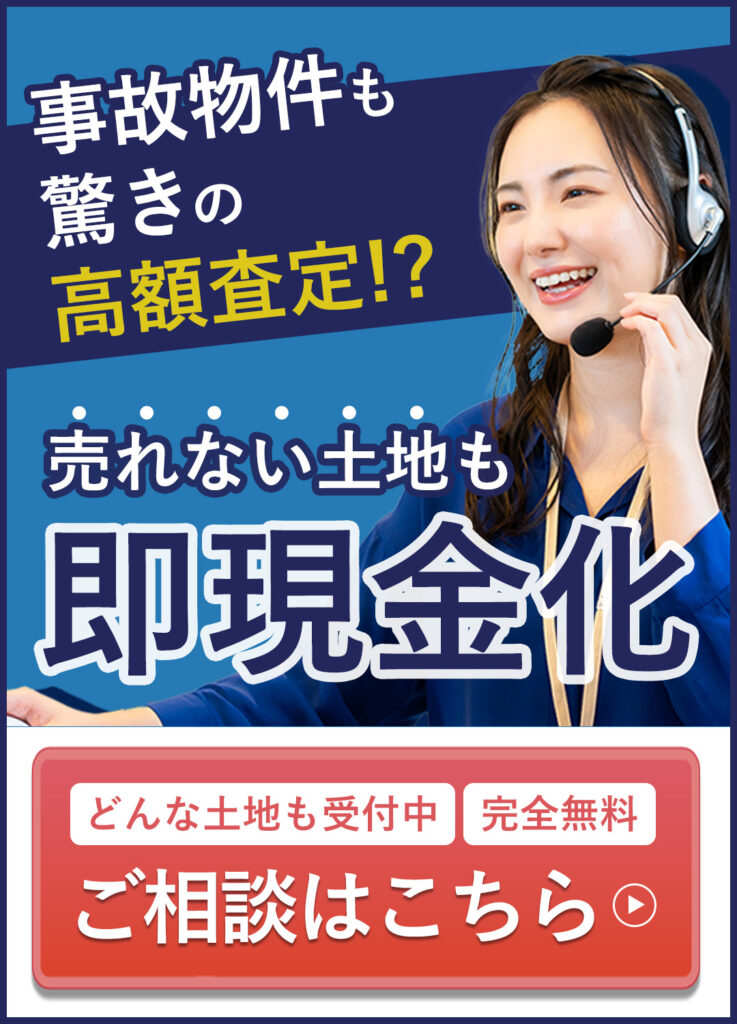京都府の空き家補助金を解説-解体・リフォームなどで活用!申請の流れや注意点も
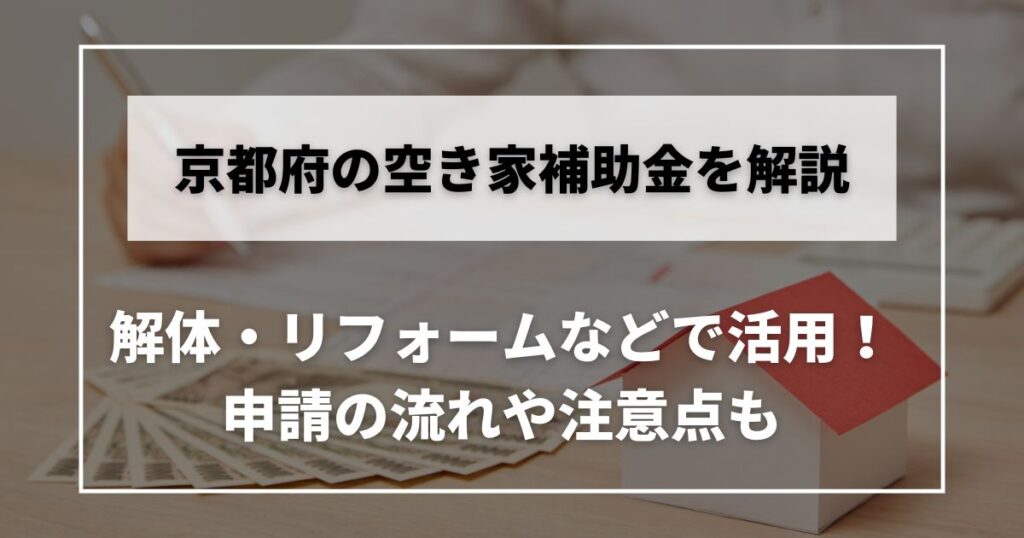
「京都府で空き家を所有している方にとって、令和11年から課税開始予定の『空き家税(非居住住宅利活用促進税)』は無視できないリスクです。
現在、府内では解体や家財撤去に最大100万円単位の補助金が出るケースもありますが、実は『耐震基準を満たさないと対象外』『指定業者以外の施工は不可』など、受給ハードルが非常に高いのが現実です。
本記事では、京都府内主要自治体の補助金情報を整理するとともに、補助金に頼らずに『今すぐ実家を現金化する最短ルート』を分かりやすく解説します。」
- 京都府の空き家問題
- 京都府で使える空き家関連補助金制度
- 補助金を受けるための流れと注意点
- 補助金以外の空き家対策
- よくある質問とトラブル例
補助金の活用とあわせて、空き家の売却も重要な選択肢のひとつです。
空き家パスは、相続不動産や訳あり物件の買取に強みを持つ不動産会社です。
都心から離れたエリアの物件や、再建築不可・老朽化物件など、他社では断られるケースでも積極的に対応しています。ご相談や査定は完全無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
京都府の空き家問題、現状は?
総務省が公開している「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計結果概要」によると、令和5年時点における京都府の総住宅数は137万9,000戸となっており、空き家は18万200戸となっています。
空き家率は13.1%と全国平均の13.8%を下回っているものの、居住世帯がない建物は昭和48年から増加しています。
空き家は放置しておくと経年劣化が進んでしまうため倒壊のリスクが高くなり、台風や洪水などの自然災害によって家屋の一部が飛散し、隣地に被害が及ぶこともあります。
また、管理されていない空き家は害虫や害獣が発生し、犯罪の拠点に使われてしまうことも考えられます。
このように空き家の増加は街の治安や安全に大きく影響してしまうことから、京都府でも大きな問題として扱われています。
平成27年には「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され危険な状態の空き家を所有している人に対し、自治体は管理の是正や指導を行えるようになりましたが、所有者と連絡が取れないなど全ての問題をカバーできていないのが現状です。
【引用サイト:令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計結果概要】
空き家問題解決策のひとつ「補助金制度」
空き家の増加は街の資産価値を低下させる大きな問題といえますが、活用することで移住者促進や危険な家屋を減少させる効果を期待することができます。
そこで京都府では空き家のリフォーム、解体、取得に対して補助金制度を公開しており、空き家の所有者や購入者の負担が少なくなることで利活用が促進されることを目的としています。
特に空き家バンクと組み合わせた制度は補助金額も増えることから、空き家の売買を検討する人はまず自治体や空き家相談窓口に電話で問い合わせし、利用できる制度について理解を深めることがポイントです。
京都府で使える空き家関連補助金
この章では京都府の自治体が2025年10月時点で募集している補助金制度を紹介します。
なお、補助金制度は予算が設定されているため、予算達成と同時に終了してしまいます。
そのため利用を検討している人はなるべく早く申請することをおすすめします。
空き家のリフォーム・改修に関する補助金
空き家のリフォーム・改修に関する補助金は次の通りです。
| 自治体名 | 制度名 | 補助金の上限額 |
|---|---|---|
| 長岡京市 |
木造住宅耐震改修補助 |
本格改修:165万円/戸あたり 簡易改修:耐震補強工事費用の5分の4かつ40万円/戸あたり 簡易シェルター:費用の4分の3かつ30万円 |
| 舞鶴市 |
舞鶴市まちなかエリア定住促進事業 |
売買契約締結時に住所が市内かつ空き家に65歳以上:改修工事費用の2分の1かつ60万円 売買契約締結時に住所が市内かつ空き家に65歳未満:改修工事費用の4分の1かつ30万円 売買契約締結時に住所が市外:改修工事費用の2分の1かつ100万円 |
| 木津川市 |
木津川市移住促進事業補助金 |
改修工事費用の2分の1かつ180万円 |
| 福知山市 |
福知山市移住促進事業補助金 福知山市農山村地域空き家改修費補助金 |
180万円 空き家バンク利用登録者が契約後1年以内:80万円 上記以外:40万円 |
| 京丹後市 |
移住促進・空家改修支援事業補助金 |
京丹後市移住促進計画策定地区かつ水洗化工事:140万円 上記地区で水洗化工事なし:90万円 京都府移住促進特別区域かつ水洗化工事:230万円 上記地区で水洗化工事なし:180万円 |
| 綾部市 |
綾部市定住促進事業費補助金 |
登録空き家:180万円 登録外空き家:90万円 |
| 宮津市 |
移住・定住支援空き家改修補助制度 |
定住支援空き家等改修補助:改修経費の2分の1かつ100万円 移住促進事業補助:180万円 |
空き家の解体に関する補助金
空き家の解体に関する補助金は次の通りです。
| 自治体名 | 制度名 | 補助金の上限額 |
|---|---|---|
| 京都市 |
京都市空き家等の活用・流通補助金 |
解体工事費の3分の1かつ60万円 |
| 宇治市 |
宇治市狭小地等解消推進補助金 宇治市老朽空き家等解体補助金 |
50万円 基準額の3分の1かつ30万円 ・工事費の見積額 ・老朽空き家の延べ面積×33,000円/㎡(木造)または47,000円/㎡(非木造) |
| 舞鶴市 |
空き家除却支援 |
対象工事費用の3分の1かつ40万円 |
| 京丹後市 |
京丹後市老朽空家等除却費補助金交付要綱 |
補助対象経費の3分の1かつ20万円 |
| 宇治市 |
宇治市狭小地等解消推進補助金(空き家取得用) |
上限10万円 ・1年以上使われていない空き家かつ敷地が狭小地の物件を売買する際、再建築できる土地面積を確保したうえで売買 ・対象経費は仲介手数料や登記費用など |
空き家の家財処理に関する補助金
空き家の家財処理に関する補助金は次の通りです。
| 自治体名 | 制度名 | 補助金の上限額 |
|---|---|---|
| 亀岡市 |
空き家流動化促進事業 |
10万円 |
| 舞鶴市 |
舞鶴市まちなかエリア定住促進事業 |
10万円 |
| 木津川市 |
空家流動化促進事業 |
対象費用の2分の1かつ10万円 |
| 城陽市 |
空き家の家財処分等費用の補助制度 |
対象費用の2分の1かつ10万円 |
| 京丹後市 |
空家の所有者向け補助金 |
10万円 |
| 南丹市 |
空家流動化促進事業 |
10万円 |
| 宮津市 |
空き家バンク登録時等に家財道具の処分費用を補助 |
家財撤去費用の2分の1かつ5万円 |
その他の補助金
京都府では前述した補助金制度以外にも、次のような制度が公開されています。
| 自治体名 | 制度名 | 補助制度の内容 |
|---|---|---|
| 京都市 |
京都市空き家等の活用・流通補助金 |
空き家を売却する際の仲介手数料を補助する制度。補助金額は仲介手数料の2分の1かつ上限25万円。 |
補助金を受けるための流れと注意点
補助金制度は空き家の利活用を予定している人にとってコストダウンの効果がありますが、全ての補助金制度は「申請して受理され、補助金交付」というステップがあります。
つまり、補助金を受けるためには申請の流れを理解する必要があるといえ、さらに制度によって申請の手順は異なります。
特に改修や解体、家財処分関連の補助金は手順を間違えると申請自体ができなくなってしまいますので、注意が必要です。
この章では補助金を受けるための基本的な流れと注意点について、解説します。
申請に必要な主な書類
補助金を申請するためには各自治体が指定する必要書類を全て用意する必要があります。
主に指定される書類は次のようになりますので、事前に準備しておくことをおすすめします。
- 指定様式の補助金交付申請書
- 建物の全部事項証明書
- 運転免許証
- 住民票
- 印鑑証明書
なお、上記以外にも不動産取得の補助金であれば売買契約書、リフォームの場合は建物の平面図や立面図が必要になるケースがあります。
必要書類によってはすぐに準備できないこともありますので、不明点があれば自治体に相談することがポイントです。
特に印鑑証明書は印鑑登録が必要となり必ず一度は市役所へ出向くことになりますので、注意が必要です。
申請する上での注意点や落とし穴
補助金の申請で起きやすい失敗事例として、申請書類の不備や適用条件の見落としがあります。
たとえば改修工事の場合、工事前の現況画像が必要書類となっているケースがあり、撮影し忘れると申請自体ができなくなってしまいます。
また申請者と不動産の所有者が同一人物でなければならないという制度もあり、法定相続人では条件を満たすことができず相続登記後に申請しようとしたら制度が終了していたというケースも少なくありません。
これ以外にも賃貸として活用してしまうと二度と利用できない制度もありますので、自治体が公開している制度は詳細まで把握しておくことが大切です。
補助金以外で空き家問題を解決する方法
利用できる制度をチェックし、漏れなく申請することで空き家の利活用にかかる費用を抑えることができますが、補助金制度だけで空き家問題を全て解決できるわけではありません。
不動産の立地や状態によっては制度を利用しない方が適しているケースもあります。
この章では補助金以外で空き家問題を解決する代表的な方法を紹介しますので、制度を利用する前にチェックしてください。
補助金だけでは難しいケースがある
補助金制度だけでは解決できない問題として、利用者の費用負担があります。
ほとんどの制度に上限額と割合が設定されており、費用の全額をカバーできるわけではありません。
たとえば補助金額について「工事費用の2分の1、上限額50万円」と記載されている場合、工事費用が40万円だと20万円しか交付されず、70万円の場合は50万円までとなります。
つまり、どちらのケースであっても20万円は自己負担となります。
さらに補助金の交付よりも工事費用の支払いが先になるケースも多く、一旦全ての費用を自己資金で対応しなければならないことも少なくありません。
このことからも、空き家を利活用することが決まっている人であれば負担を軽減できる効果がありますが、活用する予定がない人にとってはメリットを活かすことができない制度といえます。
これ以外にも、制度の申請手続きが複雑で必要書類を全て準備できないという利用者も多く、申請自体を諦めてしまう人もいます。
自治体や制度によって申請書類が異なるという点は、補助金制度の注意点です。
空き家を売却する
空き家を利用しないのであれば補助金制度を利用するのではなく、売却してしまうのも代表的な方法です。
空き家を自己利用することなく放置していると自治体によって「特定空家」に指定されることもあり、指定されてしまうと自治体の指導に沿った管理をしなければなりません。
従わない場合は固定資産税の税制優遇撤廃や行政代執行による建物解体といった措置を講じられることもあり、大きなリスクといえます。
そのため将来にわたって有効活用する予定がない空き家は不動産会社に査定を依頼し、なるべく早く売却することが重要です。
なお、不動産売却には「仲介」と「買取」の2つがありますが、空き家の場合は買取がおすすめです。
仲介は不動産会社に販売を委託し、インターネットや紙媒体を使って買い手を募集する方法ですが、空き家の状態や立地が悪ければ販売が長期化してしまいます。
また、販売条件によっては解体費や測量費、残置物の撤去費用がかかってしまい、売主にとって大きな負担となります。
その点、買取は不動産会社が直接買主となって契約するため解体や残置物の撤去をすることなく引き渡すことができます。
さらに仲介手数料もかからず、業者によっては最短1週間で現金化できるという点もメリットです。
このように空き家は買取の方がメリットが大きいとされていますが、買取価格は仲介よりも安くなるなどのデメリットもあるため、複数の業者に相談して決めることが重要です。
関連記事:京都府の空き家・不用品買取業者おすすめ8選|売却相場やすぐに買い取ってもらうためのポイントを解説
空き家バンクを活用する
空き家バンクは各自治体が情報を把握し、提供している空き家等のポータルサイトです。
インターネットで物件情報を検索することができ、空き家を売りたい人や貸したい人は空き家バンクに登録して買い手や借り手を募集することになります。
一般的に不動産ポータルサイトと違って空き家に特化しており、費用もかかりません。
また、京都府の場合、制度によって空き家バンクに登録されている空き家を活用することで補助金額が増えることもありますので、補助金と併用したい場合でも空き家バンクは利用すべきといえます。
なお、空き家バンクは市町村民税を滞納していないなど利用するための要件があります。
さらに撮影した画像や物件コメントに虚偽があると物件情報自体が削除されてしまうこともありますので、正しい情報を入力することが重要です。
空き家を活用する
空き家を売却すると管理の手間や費用負担から解放されますが、所有権を放棄することになるため将来利用できなくなってしまいます。
そのため利用する予定がある空き家であれば適切に管理し、運用することも検討すべきといえます。
たとえばリフォーム工事をして賃貸に出したり、敷地が広ければ解体して駐車場用地として活用する方法があります。
どちらの方法も補助金制度を併用できるケースもありますので、自治体に相談しながら判断することが大切です。
ただし、都市計画区域によっては解体してしまうと再建築できないエリアがあり、知らずに解体してしまって土地の資産価値が大きく減少してしまったという失敗事例もあります。
これ以外にも賃貸に出すことで将来の相続や売却時に使えなくなる節税制度もありますので、注意が必要です。
よくある質問とトラブル例
この章では空き家関連の補助金制度を利用する際によくある質問とトラブル例を紹介します。
Q:補助金と売却、どちらが良いですか?
補助金を使って空き家を活用するか売却してしまうのかはどちらにもメリットとデメリットがありますが、選ぶ際には「空き家の使い道」というポイントで判断するのがおすすめです。
空き家を自己利用する場合や将来相続させるために所有し続けるのであれば、改修費用や解体費用を少なくできる補助金の方が向いているといえます。
一方、自己利用も将来まで所有するつもりもないのであれば、売却してしまった方が維持管理費も手間もかからないためメリットが大きいです。
このように空き家をどのように活用・所有するかによって、補助金か売却かを決めることが重要です。
ただし補助金制度によっては売却のケースであっても利用することができますので、有効活用する場合でも売却する場合でも自治体に相談する必要があるといえます。
Q:古い空き家や傷みがある空き家でも補助金は使えますか?
補助金制度によっては旧耐震の家屋が対象になるなどの条件がありますが、原則家屋の見た目が適用条件に影響することはありません。
そのため経年劣化が激しい建物であっても補助金を使える可能性は高いといえますが、制度の目的を達成できない状態になっている場合は申請を却下されることもあります。
たとえば改修工事や解体工事、家財処分費用を対象とした補助金制度の場合、工事そのものが実施できなければ補助金の交付を受けることができません。
道が狭く車両が通行できない立地や建物が既に基礎部分しか残っていないケースでは申請を却下されることもありますので、注意が必要です。
このように、申請が通らない可能性がある場合は必ず事前に自治体の担当者に相談し、現地確認してもらうことがポイントです。
Q:補助金申請が難しそう…誰かに頼めますか?
補助金の申請は解体業者やリフォーム業者が代行することも可能ですが、自治体や制度によっては委任状が必要になったり本人申請しか受け付けていないこともあります。
また、代行で申請ができたとしても本人しか用意できない書類はありますので、所有者しか用意できない書類についてあらかじめチェックしておくことも大切です。
Q:空き家を自治体に寄付できますか?
京都府では自治体によって空き家の寄付について相談窓口を開設しており、条件が合えば寄付することも可能です。
なお、京都市では個人が所有する空き家等を特別養護老人ホーム等の整備を目的として寄付する場合、「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」を利用することができます。
これにより空き家の譲渡にかかる税金を少なくすることができます。
【引用サイト:京都市:住まいの活用、社会福祉法人への土地建物の寄附のご相談について】
まとめ
空き家の増加は全国的な問題となっており、京都府においても増加を食い止めるために様々な補助金制度が設けられています。
空き家は適切に管理したり解体することで倒壊のリスクを防ぐことができ、改修工事をすることで居住できる建物になります。
また空き家を有効活用して移住者を増やすこともできることから、放置されている空き家を減少させることは街の活性化に不可欠といえます。
ただし補助金制度の利用だけでは解決できないこともあり、所有者によっては売却してしまう方がメリットが大きいこともあります。
空き家の所有者は補助金と売却、補助金を利用して売却するなど様々なパターンを検討する必要がありますので、なるべく早い段階で自治体や不動産会社などに相談することをおすすめします。