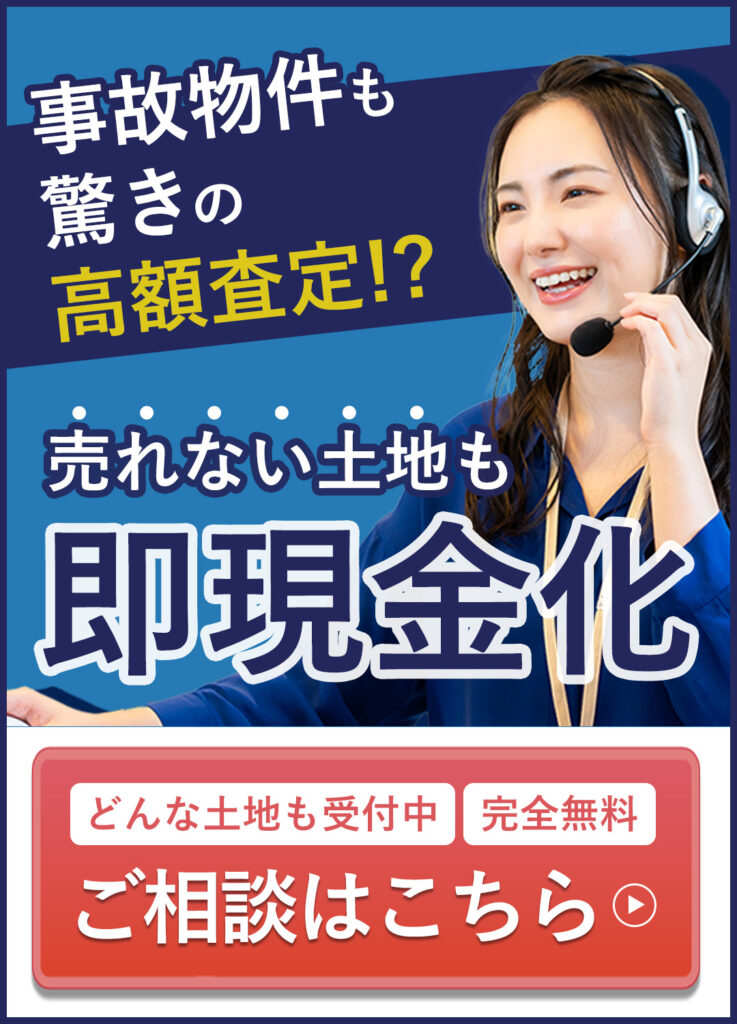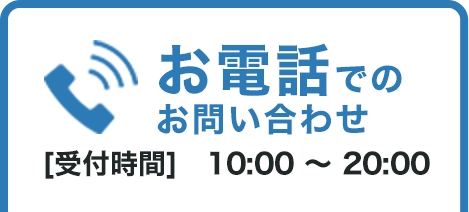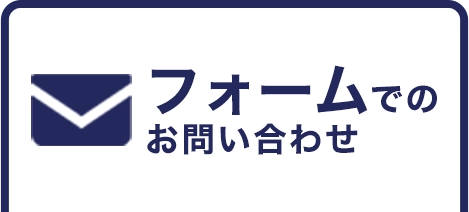愛媛の空き家補助金を解説ー解体・リフォームなどで活用!申請の流れや注意点も
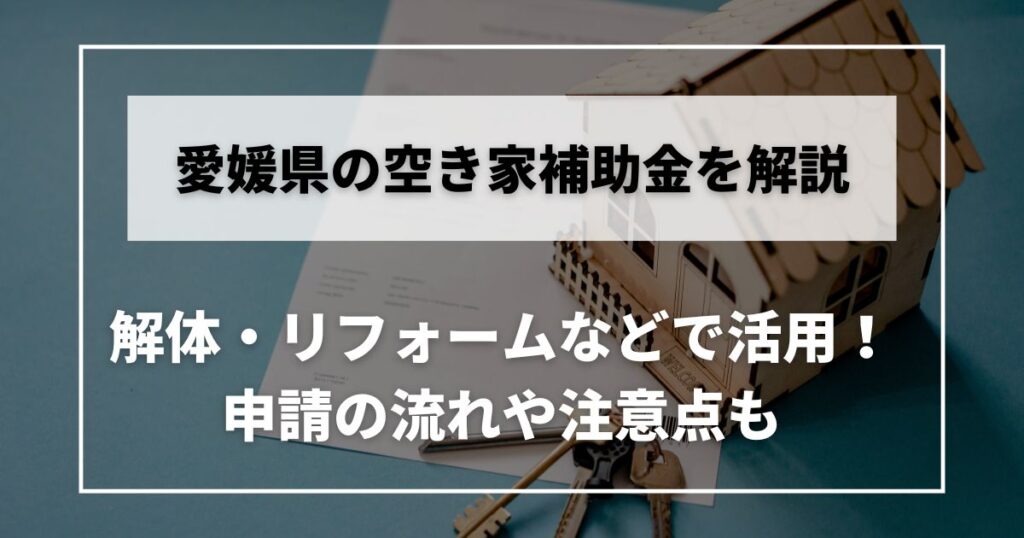
「相続した実家をそのままにしている」「解体費用が高くて手をつけられない」
愛媛県でも、そうした空き家の悩みを抱える方が増えています。放置された空き家は老朽化が進み、倒壊や近隣トラブルの原因となるだけでなく、固定資産税などの費用も発生し続けます。所有しているだけで負担が増えていく空き家は、早めに対策することが大切です。
愛媛県内では、空き家のリフォーム・解体・取得・片付けなどに活用できる補助金制度が各自治体で用意されており、条件を満たせば数万円~数十万円の支援を受けられる場合もあります。たとえば、老朽化した屋根の修繕費用や家財の片付け費用の一部に充てられることもあります。
補助金を効果的に活用することで、空き家の活用や売却にかかるコストを抑え、負担を減らしながらスムーズに手放すことも可能です。
この記事では、愛媛県の空き家事情や補助金制度の概要、申請の流れ・注意点、そして補助金以外の選択肢までをわかりやすく解説します。
相続や空き家の管理に悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
この記事でわかること
- 愛媛県における空き家問題の現状と背景
- 活用できる補助金制度の種類と支援内容
- 補助金を申請する際の流れと注意点
- 売却など補助金以外で空き家を手放す方法
- よくある質問とその解決策
相続した空き家に住む予定がない場合は、売却も選択肢のひとつです。
「空き家パス」は、相続不動産や築年数の古い物件、再建築不可物件、訳あり物件などの買取を得意とする不動産会社です。
他社で断られた物件でも、独自のノウハウで対応できるケースが多くあります。査定・相談はすべて無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
愛媛県の空き家問題、現状は?
愛媛県では、都市部・郡部を問わず空き家の増加が深刻な問題となっています。
総務省が公表した「令和5年住宅・土地統計調査(速報値)」によると、愛媛県の空き家率は19.8%に達し、全国平均(13.8%)を大きく上回っています。県内の空き家総数は約14万6,000戸にのぼり、全体の約5戸に1戸が空き家という割合になります。
特に松山市や今治市などの都市部では、相続後に活用されず放置された住宅が目立ちます。一方、中山間地域では、高齢化や人口減少により住む人がいなくなり、地域ごと空き家が増えているケースも見られます。
老朽化した空き家は、景観の悪化や治安リスクだけでなく、倒壊や火災といった重大なトラブルにつながる恐れもあります。
このような状況の背景には、以下のような要因が複合的に影響しています。
- 高齢化に伴う居住者の減少と、相続後の管理放棄
- 若年層の都市部流出による住宅需要の低下
- 活用されない住宅の長期放置による空き家の蓄積
愛媛県や各市町村では、こうした空き家問題に対応するため、補助金制度の導入や相談窓口の設置など、支援体制の整備を進めています。
空き家を「活かす」か「手放す」か、選択肢を整理して早めに行動することが、所有者だけでなく地域全体にとっても重要です。
【参考:令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果】
空き家問題解決策のひとつ「補助金制度」
空き家をそのままにしていると、老朽化による倒壊や近隣トラブル、景観の悪化など、さまざまな問題が発生する可能性があります。
こうしたリスクを防ぎ、空き家の利活用や処分を後押しするために、国や自治体では補助金制度を整備しています。
補助金制度では、主に次のような目的に対して支援が行われています。
- 老朽化した空き家の解体
- 中古住宅のリフォームや耐震改修
- 空き家を取得・活用する際の費用補助
- 家財道具の撤去や清掃にかかる費用
- 空き家売却前のインスペクション(住宅状況調査)費用の一部補助
愛媛県内でも、市町村ごとにさまざまな補助制度が用意されており、条件を満たせば数万円~数十万円規模の支援を受けられるケースがあります。
補助金を活用することで、空き家の解体やリフォームにかかる自己負担を大きく軽減できます。
ただし、補助対象となる事業の内容や申請条件、支給額の上限、必要書類などは自治体ごとに異なります。
申請を検討する際は、各市町村の公式サイトや窓口で最新情報を確認し、手続きの流れを事前に把握しておくことが大切です。
愛媛県で使える空き家関連補助金
愛媛県では、移住・定住の促進や地域の空き家対策を目的に、各市町村が実施する多様な補助制度が整備されています。
空き家の改修・解体、取得費用の一部、家財の片付けにかかる費用まで支援対象が広がっており、条件を満たせば手厚い補助が受けられます。
この章では、愛媛県内で利用できる主な補助制度について、目的別に分かりやすく解説します。
空き家のリフォーム・改修に関する補助金
愛媛県では、移住促進や空き家活用の一環として、空き家のリフォームや改修に対する補助制度が各市町村で整備されています。
特に多くの自治体が「空き家バンク」に登録された物件を対象とし、県外からの移住者に向けて手厚い支援を行っています。
松山市・今治市・西条市などでは、子育て世帯に対して最大400万円の補助が設定されており、子どもの人数に応じて加算される仕組みもあります。
また、伊予市や上島町では「働き手世帯」も対象となり、年齢や居住年数の要件を満たすことで、改修費用の2/3以内が補助されます。
制度の多くは、改修費用が50万円以上であることを条件とし、交付決定前の工事着手は対象外とされるため、申請手続きのタイミングにも注意が必要です。
施工業者を市内業者に限定しているケースもあり、事前の確認が欠かせません。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 松山市 | 令和7年度 移住者住宅改修支援事業(空き家の改修) |
|
|
| 今治市 | 住もういまばり!空き家リフォーム補助金(住宅改修) |
|
|
| 西条市 | 西条市移住者住宅改修支援事業費補助金 |
|
|
| 伊予市 | 伊予市移住者住宅改修支援事業費補助金 |
|
|
| 東温市 | 東温市空き家等活用定住支援事業補助金(空き家改修事業) |
|
|
| 上島町 | 上島町移住者住宅改修支援事業 |
|
|
| 上島町 | 上島町: 空き家活用事業 |
|
|
| 松前町 | 移住者住宅改修事業費補助金制度 | 空家等の改修: 100万円 |
|
| 松野町 | 移住者住宅改修支援事業(愛媛県連携) | 子育て世帯で最大400万円など(条件による) |
|
| 松野町 | 移住促進空き家改修費補助金 | 100万円(住宅改修、家財道具搬出費用) |
|
空き家の解体に関する補助金
愛媛県内では、倒壊や災害リスクのある老朽化した空き家に対し、除却費用の一部を支援する制度が複数の自治体で実施されています。
解体工事を行う所有者や相続人が対象で、費用負担を軽減しつつ、地域の安全確保と景観保全を図ることが目的です。
たとえば松山市や八幡浜市では、最大80万円〜100万円の補助があり、条件により上限が引き上げられるケースもあります。
補助率はいずれも80%前後と高く、不良度判定が一定以上の危険空き家であること、税金の滞納がないことなどが主な要件です。
一方で、東温市のように移住者向けの建替支援として解体費用を補助する制度もあり、老朽化による除去と区別する必要があります。
申請にあたっては、工事着手前であることや、不良度の診断書類の提出が求められる場合もあるため、事前に自治体窓口で詳細を確認しましょう。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 大洲市 | 空き家取得補助金 |
・県外移住:100万円 ・県内移住:75万円 ・大洲市民:50万円 ・補助率1/10 |
・18〜60歳の人がいる世帯 ・移住条件(県外/県内/市内)で要件あり ・取得住宅に5年以上居住 |
| 今治市 | 住もういまばり!移住者住宅取得事業費補助金 |
・最大50万円 ・基礎:取得費10%(上限30万円) ・加算:18歳未満の子1人につき10万円 |
・市外からの転入者(5年以内) ・取得住宅に5年以上定住 ・日本国内からの転入に限る |
空き家の家財処理に関する補助金
空き家の利活用や売却に向けては、内部に残された家具や生活用品の撤去が大きな負担になることがあります。
こうした課題に対応するため、愛媛県内の多くの自治体では、家財道具の搬出や処分に関する補助制度が設けられています。
特に松山市、今治市、西条市などでは、県外からの移住者を対象に、家財処分費用の2/3を補助し、上限額はおおむね20万円です。
対象となるのは「空き家バンク」に登録された一戸建てが中心で、5年以上の居住意志や市町村税の滞納がないことなどが共通の条件となっています。
また、内子町や上島町では、所有者も対象に含め、物件の再活用を目的とした処分費の支援制度が設けられています。
補助金の適用には、処分費用が一定額以上であることや、町内業者の利用といった細かな条件があるため、事前確認が重要です。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 松山市 | 移住者住宅改修支援事業(家財道具の搬出等) |
・20万円 ・補助対象経費の2/3以内 |
・令和2年4月1日以降に愛媛県外から転入した「移住者」。 ・補助対象の空き家に5年以上居住する意思があること。 ・対象住宅は「空き家バンク」登録の一戸建て(購入または賃借)。 ・「子育て世帯」または「働き手世帯」に該当。 |
| 今治市 | 住もういまばり!空き家リフォーム補助金(家財道具搬出等) |
・20万円(指定地域は25万円) ・補助対象経費の2/3以内(家財搬出5万円未満は対象外) |
・令和2年4月1日以降に県外から移住した方(または予定者)。 ・空き家バンク経由で購入または賃借した空き家に5年以上居住する意思。 ・市町村税の滞納なし。 ・原則、市内業者を活用。 |
| 西条市 | 西条市移住者住宅改修支援事業費補助金(家財道具の搬出等) |
・20万円 ・補助対象経費の2/3以内 |
・令和2年4月1日以降の移住者で5年以上の居住意思。 ・空き家バンク等経由で購入した一戸建てが対象。 ・働き手世帯または子育て世帯。 ・市町村税(前住所含む)滞納なし。 ・市内施工業者が行うこと。 ・交付決定前の着手は不可。 |
| 伊予市 | 伊予市移住者住宅改修支援事業費補助金(家財道具の搬出等) |
・20万円 ・補助対象経費の2/3以内 |
・令和2年4月以降に県外から移住し転入後3年以内(予定者可)。 ・5年以上の居住意思。 ・申請日に60歳未満がいる世帯。 ・空き家バンク登録物件(一戸建て)。 ・市税滞納なし。 ・原則、市内業者が実施。 |
| 東温市 | 東温市空き家等活用定住支援事業補助金(家財道具の搬出等) |
・20万円 ・5万円未満は対象外 |
・東温市へ定住する意思のある移住者等。 ・自治会へ加入し地域活性化へ寄与すること。 ・市税等滞納なし。 ・工事前の申請が必要。 |
| 上島町 | 上島町移住者住宅改修支援事業(家財道具の搬出等) |
・20万円 ・補助対象経費の2/3以内 |
・令和2年4月1日以後の移住者。 ・5年以上居住すること。 |
| 上島町 | 上島町空き家活用事業(家財道具等の処分) |
・10万円 ・対象経費の1/2以内 |
・処分費総額1万円以上。 ・対象者は空き家バンク登録者または利用者。 |
| 松前町 | 移住者住宅改修事業費補助金制度(家財道具の搬出など) |
・20万円 ・補助率2/3以内(5万円未満対象外) |
・空き家バンク等の空家を購入または賃借する移住者。 ・5年以上居住意思。 ・申請日に60歳未満がいる世帯。 ・税滞納なし。 ・県の補助を過去に受けていないこと。 |
| 松野町 | 移住促進空き家改修費補助金 |
・100万円(住宅改修費との合計) ・補助率2/3以内 |
・所有者または移住者。 ・2年間移住者が入居すること(令和4年4月以降)。 ・売買または賃貸契約が必要。 |
| 内子町 | 内子町空き家有効活用促進補助金 |
・10万円 ・対象経費の1/2以内(低い額) |
・家財搬出・処分・清掃が対象。 ・1万円未満は対象外。 ・空き家バンク登録者(所有者)。 ・2年以上登録する意思。 ・町税滞納なし。 ・原則、町内業者を利用。 |
その他の補助金
空き家の取得や改修に加えて、愛媛県内では登記費用や引っ越し費用、住宅ローン金利の優遇などを支援する制度も用意されています。
上島町では、空き家バンク登録物件を取得・賃借する移住者を対象に、登記や引っ越しにかかる費用の一部(上限10万円)を補助しています。
今治市では、「フラット35 地域活性化型」との連携により、一定の移住支援補助金を受けた方を対象に、住宅ローン金利を年0.25%引き下げる制度を提供しています。
いずれも移住・定住を後押しする制度であり、補助金と組み合わせて活用することで、よりスムーズな空き家活用が可能になります。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 上島町 |
上島町空き家活用事業(所有権移転登記申請・引越し関連) |
・10万円 ・対象経費の1/2以内 |
・対象者は、空き家バンク登録物件を借りる・購入する方(移住者)。 |
| 今治市 |
フラット35地域活性化型 連携 |
・フラット35借入金利から年0.25%を引き下げ | ・今治市の移住支援に関する補助金の交付対象者であること |
補助金を受けるための流れと注意点
空き家に関する補助金を活用するためには、各自治体が定めた申請手順や条件に従う必要があります。
対象となる工事や物件の要件を満たしていても、手続きを誤ると補助金が受けられない場合があるため、事前準備が不可欠です。
多くの制度では、「補助金の交付決定後に着工すること」が条件となっており、事前に工事を始めてしまうと対象外になる場合があります。
また、必要書類や申請期間、施工業者の条件も制度により異なるため、早めに情報収集を行うことが重要です。
ここでは、補助金を受ける際に必要となる主な書類と、申請時によくある注意点について詳しくご紹介します。
申請に必要な主な書類
空き家補助金の申請には、対象となる物件の状況や工事内容を証明するための書類が必要です。
制度や自治体により若干異なる場合がありますが、一般的に求められる書類は以下のとおりです。
- 申請書(自治体所定の様式)
- 対象空き家の登記事項証明書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 施工業者作成の、工事内容がわかる見積書および図面
- 工事前の現況写真
- 固定資産税の課税証明書や納税通知書の写し
- 委任状(代理人が申請する場合)
自治体によっては、空き家であることの証明として「一定期間の未使用を示す資料」や、「空き家バンクへの登録証明」などの追加書類が求められることがあります。
申請にあたっては、各自治体のホームページや窓口で提出書類のリストを入手し、チェックリストで確認しながら準備を進めましょう。
申請する上での注意点や落とし穴
補助金を活用することで空き家の費用負担を大きく減らせますが、手続きに不備があると交付が取り消されたり、対象外となったりすることもあります。
以下のようなうっかりミスには特に注意が必要です。
工事を始めるタイミングに注意
多くの制度では、「交付決定通知」が届いた後で工事を始めることが条件です。通知が出る前に着工してしまうと、ほとんどの場合、補助金の対象外となります。
予算の上限に注意
補助金は自治体の年度予算に基づいて交付されます。受付期間中であっても、予算が上限に達すると受付が終了することがあります。人気のある制度は早めの申し込みが肝心です。
施工業者の指定があることも
自治体によっては「地元業者のみ」や「登録業者に限る」といった条件が設けられている場合があります。工事を依頼する前に、対象業者かどうかを事前に確認しておく必要があります。
申請後の変更には注意
申請後に工事内容や業者を変更すると、補助の対象外になることがあります。どうしても変更が必要な場合は、事前に自治体へ相談するようにしてください。
自治体ごとのルールを確認
申請書の様式や審査の基準、補助率・上限額などは市町村によって異なります。必ず該当する自治体のガイドラインや公募要領をよく確認しておきましょう。
制度を効果的に活用するためには、
・早めに相談すること
・必要書類をしっかり準備すること
・工事前の条件確認を怠らないこと
この3点が特に重要です。
不安な場合は、自治体の相談窓口や専門業者にサポートを依頼すると安心できます。
補助金以外で空き家問題を解決する方法
空き家対策として補助金制度を活用するのは有効な手段ですが、補助対象にならないケースや、補助金を使っても費用負担が大きいままのケースもあります。
また、手続きの複雑さや期間の長さがネックとなり、制度の利用を断念するケースも見られます。
こうした背景から、補助金に依存せずに空き家を手放す/再生する方法も、現実的な選択肢として注目されています。
近年では、現状のまま空き家を買い取る専門業者や、空き家の利活用をサポートする仕組みも整備されつつあり、状況に応じた柔軟な対応が可能です。
ここでは、補助金に頼らずに空き家問題を解決するための具体的な方法として、「売却」「空き家バンクの活用」「利活用による再生」の3つの方向性をご紹介します。
補助金だけでは難しいケースがある
空き家対策として補助金制度を活用するのは確かに有効な方法ですが、すべてのケースに適しているとは限りません。
築年数が極端に古い物件や、再建築ができない土地に建つ空き家などは、補助の対象外となる場合があります。
また、補助金を受けても自己負担額が大きく、費用面であまりメリットを感じられないという意見も見られます。
申請手続きの煩雑さや、交付決定までの期間の長さがネックとなり、利用を断念する方も一定数います。
さらに、「今後も住む予定がない」「活用の見込みがない」といった理由から、補助金を使って再生する意義を感じられないケースもあります。
実際、所有者の中には「修繕や活用ではなく、できるだけ早く手放したい」と考える方も少なくありません。
こうした背景から、補助金にこだわらず空き家を手放す/再生する方法を検討する人も増えています。
最近では、現状のまま空き家を買い取る専門業者や、空き家の活用を支援する制度やサービスも充実してきました。
状況に応じて柔軟に選べる選択肢が広がっています。
空き家を売却する
補助金の活用が難しい場合や、空き家を今後使う予定がない場合には、売却により早期に手放すことが現実的な解決策です。
特に建物の劣化が進んでいる空き家では、維持管理の手間や固定資産税などの費用負担が年々増加するため、長期間保有することで損失リスクが高まります。
近年では、老朽化した建物や再建築不可の土地といった「一般的には売れにくい」とされる物件でも、買取に対応する不動産業者が増えています。
こうした専門業者は、空き家の状態にかかわらず、現況のままでの査定や買取に応じるケースも多く、片付けや修繕を行わずに済む点も大きなメリットです。
たとえば、空き家パスのように「訳あり物件の買取」に特化した不動産会社であれば、築古物件や相続後の放置物件、権利関係が複雑な空き家でも相談が可能です。
無料での査定や相談サービスを提供している会社も多いため、まずは専門業者へ相談することで、状況に応じた売却プランを検討できます。
関連記事:愛媛県の空き家・不用品買取業者おすすめ7選|売却相場やすぐに買い取ってもらうためのポイントを解説
空き家バンクを活用する
空き家をすぐに売却せず、少しでも活用したいと考えている場合には、自治体が運営する「空き家バンク」の活用も一つの選択肢です。
空き家バンクとは、空き家を所有する人と、購入や賃貸を希望する人をマッチングする制度で、全国の市町村で導入が進められています。
空き家バンクに物件を登録すると、自治体のホームページや移住促進サイトなどを通じて情報が広く発信されます。
地域に興味を持つ移住希望者や、古民家再生に関心のある層との接点が生まれ、一般の不動産市場では出会えない層とつながるチャンスがあります。
ただし、空き家バンクは「すぐに売れる」「必ず売れる」という制度ではなく、成約までに時間を要するケースもあります。
また、登録条件や必要書類、売買・賃貸の仲介手数料の有無や条件は自治体によって異なるため、事前の確認が必要です。
空き家を地域資源として活かしたい、地域とのつながりを大切にしたいといった目的がある場合には、空き家バンクを活用することも有効です。
空き家を活用する
空き家は、売却や解体だけでなく、自ら活用するという選択肢もあります。
たとえば、リフォームを施して賃貸住宅として貸し出したり、事務所や店舗として再生したりと、用途によっては収益物件として活用できる場合もあります。
愛媛県内でも、古民家をカフェや宿泊施設にリノベーションした事例や、地域コミュニティの拠点として再生された空き家など、地域資源としての活用が進んでいます。
特に観光地や移住希望者の多いエリアでは、活用の可能性が高い傾向にあります。
ただし、空き家を活用するには、改修費用や用途変更に必要な手続き、近隣との調整など、一定の準備やコストが必要です。
リフォームの内容によっては補助金を利用できる場合もあるため、自治体の制度をあわせて確認することが重要です。
空き家を手放すのではなく、自らの資産として再生させたい場合は、専門家や自治体の相談窓口に相談しながら、無理のない活用方法を検討することをおすすめします。
【参考:古民家再生が描く、持続可能な観光地の未来】
よくある質問とトラブル例
空き家に関する補助金制度や売却・活用方法は、制度の数が多く、手続きも複雑なことから、具体的に何から始めればよいか分からないという声も多く寄せられています。
また、「申請したものの対象外だった」「手続きを進めたが途中で断念した」といったトラブル事例も見受けられます。
ここでは、空き家の所有者から寄せられるよくある疑問や、つまずきやすい点をQ&A形式でわかりやすく整理しました。
補助金の利用を検討している方や、空き家の今後の扱いについてお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
Q:補助金と売却、どちらが良いですか?
A:空き家の状態や今後の活用予定によって、最適な方法は異なります。
活用予定がある場合や、賃貸・自宅として使用する計画がある場合には、補助金を活用してリフォーム・改修することが有効です。
補助金を使うことで費用負担を軽減でき、空き家の資産価値を高めることにもつながります。
一方で、「今後使う予定がない」「管理が負担になっている」といった場合には、補助金による再生よりも、売却を検討する方が現実的です。
特に建物の老朽化が進んでいる空き家では、補助金を活用しても自己負担が大きく、費用対効果が見込めないケースもあります。
まずは空き家の状態を確認し、将来的な活用意向があるかどうかを明確にしたうえで、補助金と売却のどちらが適しているかを判断することが大切です。
Q:古い空き家や傷みがある空き家でも補助金は使えますか?
A:老朽化が進んだ空き家でも、一定の条件を満たせば補助金を活用できる場合があります。
たとえば、「倒壊の危険がある」と判断された場合には、解体費用に対する補助が適用されるケースがあります。
また、「空き家バンクに登録する予定がある」「移住者によって活用される予定がある」といった条件を満たすことで、リフォーム補助を受けられることもあります。
ただし、築年数や構造、立地条件などによっては、安全性や再活用の可能性が低いと判断され、補助対象とならないことがあります。
再建築不可の土地にある建物や、権利関係が複雑な物件なども対象外となる可能性がありますので、注意が必要です。
不明な点がある場合は、あらかじめ自治体の担当窓口や補助金の実施要綱を確認し、自分の空き家が対象に含まれるかを調べておくと安心です。
Q:補助金申請が難しそう…誰かに頼めますか?
A:補助金の申請は、制度や自治体によって必要書類や手続きが異なるため、煩雑だと感じる方もいます。
しかし、多くの地域では、申請をサポートしてくれる専門家や窓口が設けられています。
たとえば、行政書士や地元の建築業者、不動産会社が申請支援を行っているケースもあります。特に、高齢の所有者や遠方に住む相続人にとっては、専門家に依頼することで負担を大きく軽減できます。
また、自治体によっては「空き家相談窓口」や「移住定住支援センター」などが設置されており、補助金の申請方法や活用事例について相談できることもあります。
一人で手続きを抱え込まず、まずは連絡可能な相談先を調べてみることをおすすめします。
Q:空き家を自治体に寄付できますか?
A:原則として、空き家をそのまま自治体に寄付することは困難です。
多くの自治体では、老朽化した建物や再建築不可の土地などを無償で引き取る対応を行っておらず、寄付を申し出ても断られることが多くあります。
その背景には、解体費用や管理にかかるコスト、将来的なリスクの引き受けが自治体の負担となるという事情があります。
ただし、地域整備や道路拡幅などの事業に関連して、特定の条件を満たす土地であれば寄付が受け入れられる場合もあります。
たとえば、建物を解体して更地にし、一定の基準を満たす場合に限り、寄付を受け入れている市町村も存在します。
寄付を検討する際は、まず自治体の都市計画課や空き家対策課などの担当窓口に問い合わせ、条件や可能性について事前に確認しておくことが大切です。
なお、寄付が難しい場合には、専門業者による売却や買取を検討することも有力な選択肢です。
まとめ
愛媛県内では、空き家のリフォーム・解体・取得・片付けなど、さまざまな目的に応じた補助金制度が整備されています。
条件に合えば費用負担を大きく軽減できるため、まずは自治体の制度内容を確認し、自分の空き家が対象になるかどうかを確認しておきましょう。
一方で、補助金だけでは対応が難しいケースもあります。
築年数が極端に古い場合や再建築不可、またはそもそも活用予定がない場合には、売却という選択肢も視野に入れることが重要です。
専門業者に相談することで、現状のままでも手間なく手放せる可能性があります。
空き家の扱いに悩んでいる方は、補助金の活用以外にも、状況に応じた柔軟な判断を意識することが大切です。
空き家パスでは、築古物件や再建築不可、権利関係に課題がある物件などの他社で断られたケースでも柔軟に対応しています。相談・査定は完全無料ですので、空き家の処分にお悩みの方はお気軽にご相談ください。