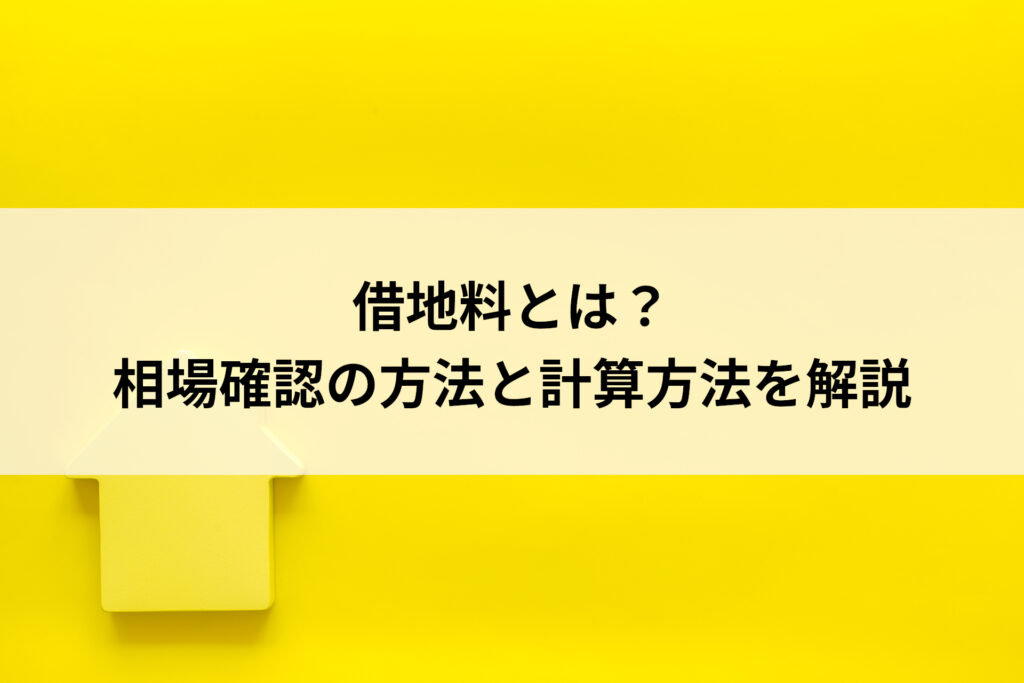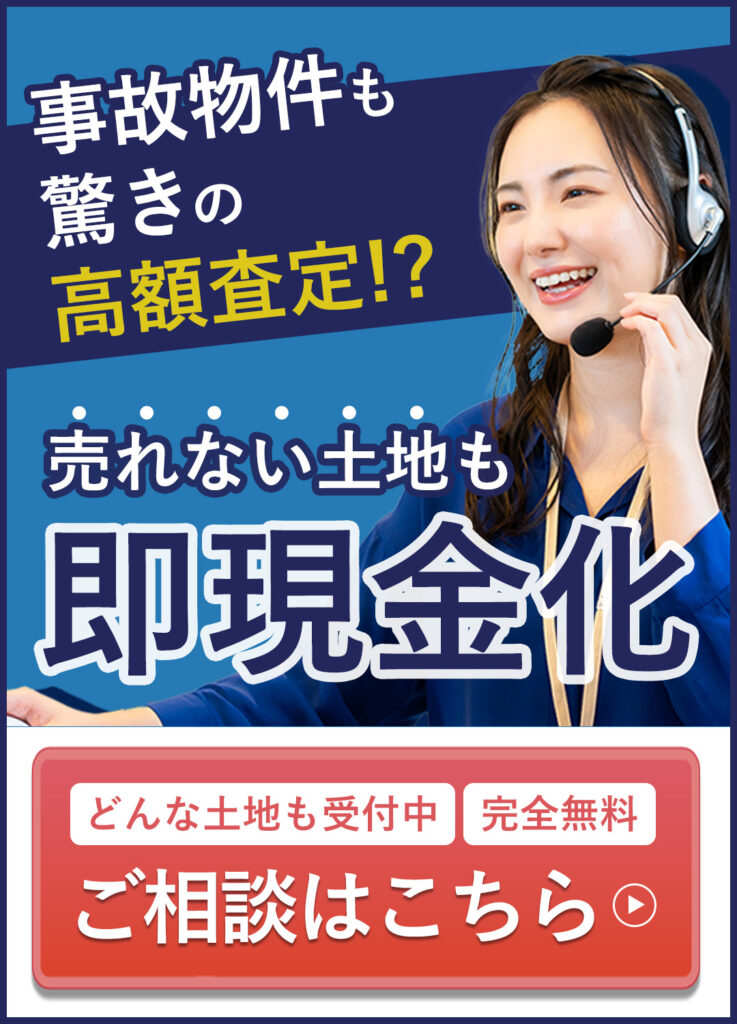借地の固定資産税を払う義務はある?借地にかかる税金やよくあるトラブルの解決策
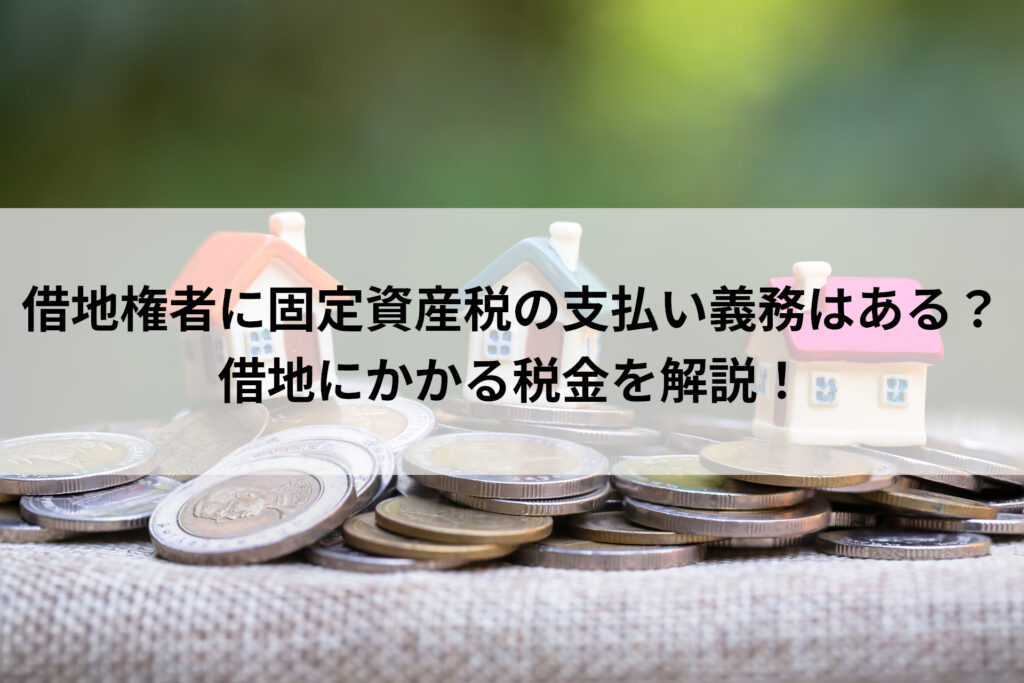
「借地(他人から借りた土地)」の上に建物を所有している方、つまり「借地権付き建物」を所有している「借地権者(借地人)」の方もいらっしゃることでしょう。そういった方の中には、「借地の固定資産税の支払い義務は誰にあるのか?」という疑問をお持ちの方も多いと思います。結論から言うと、借地の固定資産税の支払い義務は、土地の借主(借地権者・借地人)ではなく地主(借地権設定者・底地人)にあります。
しかし、借地権者の方も借地の固定資産税と全くの無関係というわけではありません。また、その他にも注意しなければいけない点や、借地権者が支払わなければいけない税金もあります。
そこでこの記事では、借地権者が知っておくべき固定資産税をはじめとした税金について解説していきます。ぜひ参考にして、借地に関するトラブルを回避するようにしましょう。
- 借地の固定資産税は誰が支払うのか
- 借地の地代と固定資産税の関係について
- 借地権者が負担しなければいけない借地の税金
前述したように、借地権者には借地自体の固定資産税の支払い義務はありません。しかし、その他の税金はかかる上に、地代もかかってしまいます。そのため、所有・管理していく上では、とても大きな負担がかかることでしょう。
そこで、借地権付き建物は売却してしまうというのも選択肢の一つです。空き家パスでは、借地権付き建物の買取に力を入れております。売却を検討する際には、ぜひお気軽に空き家パスにご相談ください。
目次
そもそも「固定資産税」とは?

そもそも「固定資産税」とは一体どういったものなのでしょうか?
「固定資産税」とは、土地や建物といった不動産を所有する者に市町村自治体から課税される税金です。地域によって課税される「都市計画税」と並んで、不動産所有者が支払わなければいけない税金の一つとなっています。また、固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している者に必ず課税されます。
その税額の計算方法は以下の通りです。
固定資産税=課税標準額(評価額)×標準税率(1.4%)
「課税標準額」とは、税額を計算する際の基礎となる金額のことを指します。一般的には「評価額(固定資産税評価額)」と同額であることが多いです。しかし、負担調整措置の対象となっている土地などの場合は一致しないこともあるので注意しましょう。
「評価額(固定資産税評価額)」の目安は、土地の場合は公示価格の約70%、建物の場合は再建築価格の50~70%程度となっています。この評価額は各自治体が決定しており、3年に1度見直しがおこなわれるのも特徴です。
そのため、固定資産税額も3年ごとに変更されることがあり、詳細は後述しますが、借地の地代に影響することもあるということを覚えておきましょう。
なお「標準税率」に関しては、自治体によって1.5%や1.6%など、異なる場合があるのでこちらもあわせて注意が必要です。
借地権者に固定資産税の支払い義務はあるのか

それでは、土地を借りている借地権者に固定資産税の支払い義務はあるのでしょうか?詳しく見ていきましょう。
借地自体の固定資産税は借地権者ではなく地主が負担する
前述の通り、固定資産税は土地や建物の「所有者」に課税される税金です。そのため、土地を借りているだけの借地権者(借地人)には、借地の固定資産税の支払い義務はありません。マンションやアパートを借りていても固定資産税を請求されることがないのと同様のイメージです。借地の固定資産税の支払い義務があるのは地主、すなわち借地権設定者(底地人)になります。また、都市計画税に関しても同様で、借地権者には支払い義務はありません。
その代わり、借地権者は地主に対して地代(借地料)を支払わなければいけません。そして、詳しくは後述しますが、借地の地代は固定資産税などを考慮して設定されることが多いため、借地権者は間接的に固定資産税を負担しているとも言えます。そのため、もし地主から地代と別に固定資産税の支払いを要求されることがあった際には、自身には支払い義務がない旨を明確に主張するようにしましょう。
【要注意】地主から固定資産税の支払いを求められたら?正しい対処法
万が一、地主から固定資産税の支払いを求められても、慌てずに対応しましょう。固定資産税は土地の所有者に課される税金であり、借地権者に支払い義務はありません。
まずは賃貸借契約書を確認し、税負担に関する特約があるかを確かめましょう。特約がない場合は支払う必要はなく、応じてしまうと今後も支払うのが当然と見なされるリスクがあります。
地代の中に固定資産税相当額が含まれているケースもありますが、それとは別に請求された場合には、法的根拠をもとに丁寧に断ることが重要です。話し合いで解決が難しい場合は、不動産トラブルに詳しい弁護士など専門家への相談を検討しましょう。
建物の固定資産税は借地権者が負担する
しかし、あくまで借地権者に支払い義務がないのは「借地」の固定資産税のみで、「建物」の固定資産税に関しては借地権者が支払わなければいけません。
ここで、借地借家法第2条の内容を確認してみましょう。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
引用: 借地借家法 | e-Gov法令検索
この記述の通り、借地とは「建物の所有」を目的として借りた土地のことを指すため、借地上に建築された建物の「所有者」は借地権者ということになります。そのため、建物の固定資産税に関しては、所有者である借地権者が支払わなければいけません。
また、建物の都市計画税に関しても、同様に借地権者に支払い義務がありますので、あわせて覚えておきましょう。
借地権者も借地の固定資産税と全く無関係というわけではない!

さて、ここまでに述べてきたように、借地権者には借地自体の固定資産税や都市計画税の支払い義務はありません。しかし、だからといって全くの無関係というわけでもありません。
それでは、一体どういった関係があるのでしょうか?詳細に見ていきましょう。
借地の地代は固定資産税額を目安に設定されることが多い
借地の地代(借地料)は、「公租公課(固定資産税額+都市計画税額)」を目安に設定されることが多いです。具体的には以下の表の通りで、借地上に建築された建物の用途によって相場が変わります。
| 借地上の建物の用途 | 公租公課(固定資産税額+都市計画税額)に乗ずる倍率 |
|---|---|
| 住宅用 | 3~5倍 |
| 商業用 | 5~8倍 |
この表から分かる通り、借地上の建物の用途が「住宅用」の場合には3~5倍、「商業用」の場合には5~8倍の倍率を公租公課の額に乗ずることで、おおよその借地の地代(借地料)を計算することができます。
例えば、「課税標準額(評価額)」が1,000万円の借地の場合を見てみましょう。
固定資産税額は前述の通り、課税標準額(評価額)に標準税率を乗ずることで算出できます。ここでは仮に標準税率を1.4%としましょう。すると、固定資産税額は14万円となります。
そして、都市計画税額に関しては以下の計算方法にて算出できます。
都市計画税=課税標準額(評価額)×制限税率(~0.3%)
都市計画税額の計算に用いる税率の上限(制限税率)は0.3%と定められており、多くの自治体では制限税率と同じ0.3%が税率として採用されています。しかし、自治体によっては異なる税率を採用しているところもあるので、よく確認するようにしましょう。
ここでは、仮に0.3%として計算します。すると、都市計画税額は3万円になり、固定資産税と都市計画税の合計額は14万円+3万円=17万円となります。
したがって、借地上の建物の用途が「住宅用」の場合は17万円×3~5倍=51万円~85万円、「商業用」の場合は17万円×5~8倍=85万円~136万円が借地の地代の相場になります。
このように、借地の固定資産税や都市計画税は借地料の相場を知るためにも重要です。相場を知り、もしそれよりも明らかに高額の請求を地主(借地権設定者)からされた場合には、損をしないように地主に確認を取るようにしましょう。
固定資産税額が上がると地代を値上げされる可能性もある
また前述しました通り、評価額(固定資産税評価額)は3年に1度見直しがおこなわれます。すなわち、それを元に算出される固定資産税額も3年に1度変わる可能性があるのです。そして固定資産税額が上がった際には、借地の地代も値上げされる可能性があります。
借地借家法第11条には以下のような記述があります。
(地代等増減請求権)
第十一条 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
引用: 借地借家法 | e-Gov法令検索
これによると「土地に対する租税その他の公課の増減」、つまり固定資産税などの増減があった際には、地主はそれに応じて地代を変更することが認められています。
このように、借地の固定資産税の増減は自身が支払う地代にも影響があるため、自分には無関係だとは考えずその増減についてもしっかりと把握しておく必要があります。
固定資産税上昇による地代値上げ…通知を受けたらどう対応すべき?
地主から「固定資産税が上がった」として地代の値上げを通知された場合、借地権者はどう対応すれば良いのでしょうか。借地借家法では、地代の増減について一定のルールが定められており、冷静に対処することが大切です。
ここでは、値上げ通知を受けた際の具体的な対応手順を解説します。
自分の借地の固定資産税額、どうやって知る?確認方法を紹介
固定資産税の上昇が本当にあったのかを確かめるためには、実際の税額を確認する必要があります。以下の方法で調査が可能です。
地主に固定資産税・都市計画税の納税通知書のコピーを見せてもらう
もっとも正確な確認方法は、地主に「納税通知書」の写しを見せてもらうことです。通知書には税額や評価額が明記されており、地代の算出根拠を把握する手がかりになります。
ただし、地主が個人情報であることを理由に、提示に協力してくれない場合もあります。
その場合には、「地代の交渉に必要な資料である」と丁寧に説明し、信頼関係を保ったままお願いしてみましょう。
地代交渉の際に、地代の根拠として固定資産税額の提示を求める
固定資産税を根拠に地代の値上げが求められた場合には、値上げの根拠を具体的に示してください」と求めるのが自然な流れです。 地代は「公租公課(固定資産税+都市計画税)の〇倍」という形で算出されることが多く、提示された固定資産税額と倍率が妥当か確認することで、無用なトラブルを避けることができます。
役所の固定資産課税台帳の閲覧
市区町村の税務担当窓口では、「固定資産課税台帳」の閲覧が可能です。ただし、閲覧できるのは原則として納税義務者本人かその代理人、または利害関係者(借地権者・借家人)などに限られるため、閲覧の際には借地契約書や本人確認書類などの提出が必要です。
借地権者と地主間での固定資産税・地代に関するよくあるトラブルと予防策
固定資産税と地代の関係は複雑であるため、借地権者と地主の間でトラブルが発生することも少なくありません。代表的な事例とその対処法を紹介します。
また、こうしたトラブルが繰り返される場合や精神的負担が大きいと感じる場合には、「借地権付き建物を売却する」という根本的な解決策も選択肢のひとつです。売却によって管理の手間や交渉のストレスから解放され、資産を現金化することも可能です。
詳しい方法や注意点については、以下のガイド記事で詳しく解説しています。
【実家が「土地は借地で、家は持ち家」だった!相続・処分する前に知っておきたいポイント】
例1:地主が法律を知らず、借地権者に固定資産税の支払いを要求してくるケース
固定資産税は、土地の「所有者」である地主が支払うべき税金です。しかし、なかには誤った認識のまま、借地人に支払いを求めてくるケースも見受けられます。このような場合は、冷静に法的根拠を説明し、借地人に支払い義務はないことを丁寧に伝えることが重要です。
固定資産税の上昇を理由に、相場より大幅に高い地代値上げを一方的に通告されるケース。
固定資産税の上昇を理由に、実際の上昇額を大きく上回る地代の値上げが一方的に通告されるケースがあります。こうした場合には、まず金額の根拠を確認し、交渉により調整を図ることが重要です。それでも折り合いがつかない場合には、調停など法的手続きの活用も検討しましょう。
地代の計算根拠が不明確で、固定資産税相当額が二重に請求されている疑いがあるケース。
すでに固定資産税相当額が地代に含まれているにも関わらず、固定資産税分として別途請求されるケースも存在します。このような場合は、過去の支払い明細や契約書を確認し、重複請求がないかチェックすることが大切です。曖昧な請求が続くようであれば、専門家に相談し適切に対処しましょう。
借地権者が負担すべき借地にかかる税金

ここまで借地の固定資産税などについて解説してきました。
それでは、借地権者が支払わなければいけない税金は、建物の固定資産税と都市計画税の他にはどういったものがあるのでしょうか?詳しく解説していきます。
借地権取得の際にかかる「印紙税」
借地権を取得する際には、「土地賃貸借契約書」を地主と締結します。この契約書は、印紙税の課税対象として印紙税法で定められています。
税額は「契約金額」に応じて定められており、これには地代や契約終了時に返還される敷金などは含まれません。つまり、権利金や保証金などの金額に応じて印紙税額が決まることになります。借地権を取得する際には、印紙税額の確認をしっかりとおこない、該当の収入印紙を貼るように気を付けましょう。
不動産登記の際にかかる「登録免許税」
不動産を登記する際には「登録免許税」がかかります。借地の場合だと、借地上の建物の登録免許税が必要です。
また、借地権の中でも土地を使用する権利である「賃借権」も登記することができます。しかし、賃借権の登記には地主の協力が必要で、なおかつ地主にその義務はないため、実際にこれが登記されることは稀です。そうなると、地主が勝手に第三者にその土地を売買・譲渡してしまうことが懸念されますが、借地借家法第10条では以下のように定められています。
(借地権の対抗力)
第十条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
引用: 借地借家法 | e-Gov法令検索
つまり、借地上の建物さえ登記されていれば、借主は借地権に関しても第三者に権利を主張できることになります。そのため、必要なのは建物の登録免許税のみという認識で問題ありません。
また、税率に関しては新築するか中古の借地権付き建物を購入するかで異なりますので、こちらも注意しましょう。
不動産を取得した際にかかる「不動産取得税」
不動産を取得した際には、各都道府県より「不動産取得税」が課税されます。
これに関しては固定資産税や都市計画税と同様、借地にかかる税金の支払い義務は借地権者にはありません。借地自体は「取得」したわけではなく、あくまで借りているだけだからです。ただし、これも固定資産税や都市計画税と同じで、建物にかかる不動産取得税は支払わなければいけないので注意しましょう。
借地権を贈与された際にかかる「贈与税」
「贈与税」は個人から財産をもらった際にかかる税金で、借地権に関しても贈与された際には必要になります。贈与税の額は以下の計算式にて求めることができます。
贈与税=(贈与額-基礎控除額(110万円))×贈与税率-控除額
「贈与額」とは借地権の「相続税評価額」にあたり、借地の「更地価格」に「借地権割合」を乗ずることで算出可能です。なお、借地権割合は国税庁のHPで調べることができます。
そして、贈与額(相続税評価額)から「基礎控除額」である110万円を差し引いた額が「課税価格」となります。
さらに、課税価格ごとに定められた「贈与税率」と「控除額」に基づいて、上記式の通り贈与税額を算出することが可能です。なお、課税価格ごとの贈与税率や控除額については、国税庁が公開している速算表にてご確認ください。
相続の際にかかる「相続税」
また、借地権を相続する際には「相続税」がかかります。相続税に関しては、借地権単体ではなく他の課税対象の相続財産も合算し、その額から基礎控除を引いた金額に対して課税されます。
このように、相続税額の計算は借地権単体ではできず、他の税金に比べて煩雑であるため、税理士などの専門家に任せるといいでしょう。
借地権の売却益にかかる「譲渡所得税」
借地権を売却して利益を得た際には、その利益(=「譲渡所得」)に対して所得税と住民税が課税されます。なお、譲渡所得税を算出する際の税率は、借地権の所有年数によって異なるため注意が必要です。その税率は以下の表の通りです。
| 所有年数 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 5年以内(短期譲渡所得) | 30% | 9% |
| 5年超(長期譲渡所得) | 15% | 5% |
借地権を所有していた期間が5年以内か5年を超えるかで税額が大きく変わってくるので、しっかりと確認する必要があります。
まとめ

ここまで、借地権者が知っておくべき固定資産税などの税金について解説してきました。確かに、借地権者には借地自体の固定資産税の支払い義務はありません。しかし、その他の税金はかかる上に、地代もかかってしまいます。そのため、所有・管理していく上では、とても大きな負担がかかることでしょう。
そこで、借地権付き建物は売却してしまうというのも選択肢の一つです。空き家パスでは、借地権付き建物の買取に力を入れております。売却を検討する際には、ぜひお気軽に空き家パスにご相談ください。