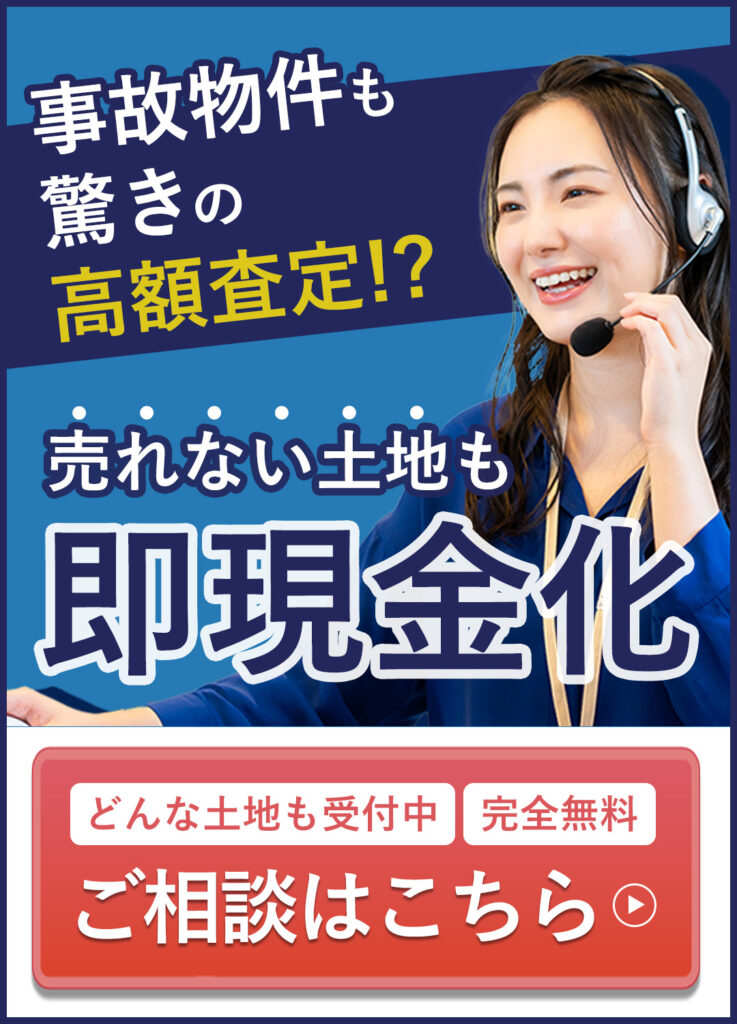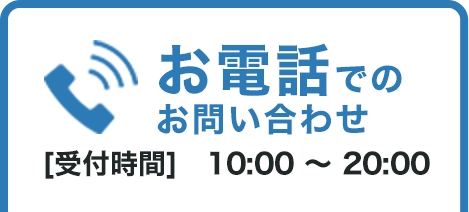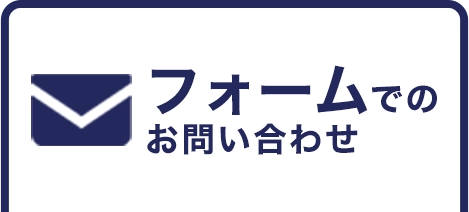福岡県の空き家補助金を解説ー解体・リフォームなどで活用!申請の流れや注意点も
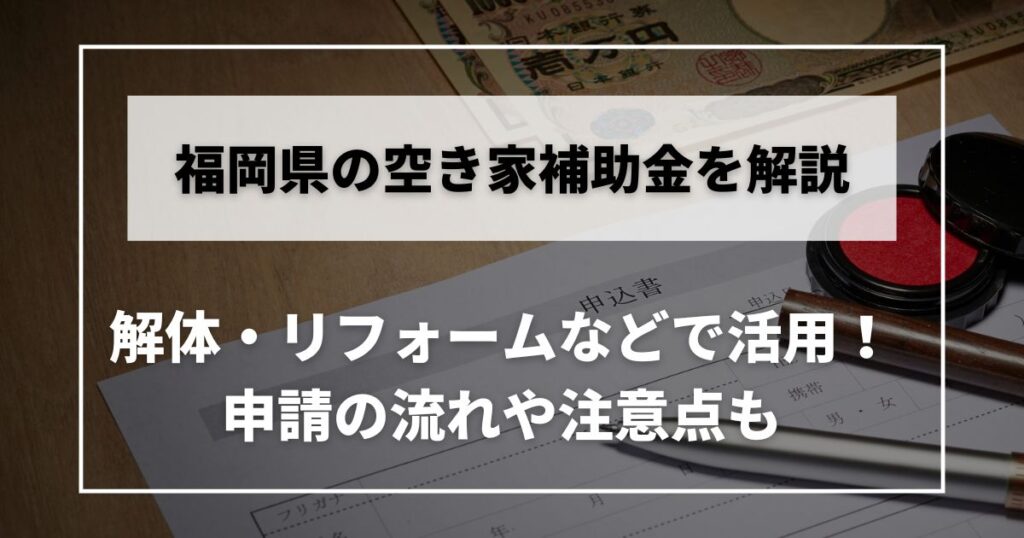
「福岡県にある空き家をなんとかしたいが、解体やリフォームの費用がネックで手付かずになっている」そんなお悩みを抱えていませんか。
福岡県では、多くの自治体が空き家の解体やリフォーム、さらには新たに取得する際にも利用できる補助金制度を整えています。これらの制度を上手に活用すれば、自己負担を軽減しながら、地域で深刻化する空き家問題の解決に具体的な一歩を踏み出せます。
しかし、補助金の種類は多岐にわたり、申請条件も複雑なため、ご自身の状況に最適な制度を見つけるのは容易ではありません。
本記事では、福岡県内で利用できる空き家関連の補助金を目的別に整理し、申請の流れや注意点を具体的に解説します。補助金の活用が難しい場合の対策についても紹介します。空き家の処分や活用でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。
- 福岡県が抱える空き家の現状と課題
- 空き家の解体・リフォーム・取得に使える福岡県の補助金制度
- 補助金を申請する際の具体的な流れと注意点
- 補助金以外の方法で空き家問題を解決する選択肢
相続によって取得した不動産に住む予定がない場合は、売却も選択肢に入れましょう。空き家パスは、相続不動産の買取を得意とした不動産会社です。
相続関係で複雑になっている物件や、田舎の築古物件、再建築不可物件、訳あり物件など、他の不動産会社に断られた空き家でも買取を行っています。相談・査定は完全無料で対応していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
福岡県の空き家問題、現状は?
福岡県は、空き家問題への対策が急務となっている地域の一つです。
総務省の「令和5年住宅・土地統計調査」によると、福岡県の空き家数は約335,000戸、空き家率は12.4%と報告されています。全国平均(13.8%)と比較するとやや低いものの、総数では全国9位と非常に多く、安心できる状況とは言えません。
特に深刻なのが、「その他の住宅」に分類される空き家の増加です。これは、賃貸・売却・別荘といった明確な用途がなく、長期間放置されたままの住宅を指します。
こうした空き家は、建物の老朽化による倒壊リスク、不法投棄による衛生環境の悪化、さらには放火や犯罪の温床になるといった問題を引き起こすおそれがあります。
結果として、地域の治安や景観にまで影響を及ぼしかねない状況です。
このような背景を受け、福岡県と県内の各市町村では、空き家の発生を抑え、適切な管理と活用を進めるための支援策を打ち出しています。
【参考:令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果】
【参考:福岡県内の空き家対策のご案内】
空き家問題解決策のひとつ「補助金制度」
空き家問題の解決を後押しするため、国や自治体では「補助金制度」を設けています。
補助金制度は、空き家の所有者が解体やリフォームなどを行う際に、その費用の一部を国や自治体が支援する仕組みです。経済的な負担を軽減することで、所有者が具体的な対策に踏み出しやすくなることを目的としています。
補助金の対象となる内容は、建物の解体やリフォーム、耐震補強工事、さらには家財道具の処分費用まで多岐にわたります。支給される金額や条件は自治体によって異なりますが、制度を適切に活用することで、本来発生するはずだった費用を数十万円単位で削減できるケースも少なくありません。
ただし、補助金は基本的に後払いであり、申請すれば必ず受給できるとは限りません。予算の上限に達した時点で受付が終了する場合もあるため、活用を検討する際には、早めに自治体の担当窓口に相談することが重要です。
福岡県で使える空き家関連補助金
福岡県内の多くの市町村では、空き家の有効活用や危険な空き家の除却を促進するため、補助金制度を設けています。これらの制度は、リフォームや解体にかかる経済的な負担を軽減し、所有者が抱える問題の解決を後押しするものです。
ただし、補助金の名称、申請条件、内容、予算額は自治体によって大きく異なります。予算の消化状況によっては、年度の途中で受付が終了する場合もあるため、活用を検討する際は、必ず事前に各自治体の担当窓口や公式ホームページで最新情報を確認してください。
以下では、代表的な市町村の制度を目的別に紹介します。
空き家のリフォーム・改修に関する補助金
空き家のリフォーム・改修に関する補助金は、老朽化した空き家を修繕し、再び居住可能にする場合や、地域の公共施設などとして活用する場合に利用できる制度です。
福岡県内の主要都市では、移住促進や子育て支援と連携させた、特色ある補助金制度が整備されています。
以下に、主要な市の制度をまとめました。
| 自治体名 | 制度名 | 補助金の上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 福岡市 | 福岡市空き家活用補助金(市街化調整区域における定住化促進) | 100万円 | ・物件が指定の市街化調整区域内にあること ・申請者が市外からの転入者または市内での新世帯であること ・1年以上空き家であり、10年間の活用が条件 ・家財道具の処分費も対象 |
| 福岡市 | 福岡市地域貢献等空き家活用補助金(子育て居住型) | 100万円 | ・市街化調整区域へ移住する子育て世帯(18歳未満の子がいる等)が対象 ・10年間の活用義務など、基本条件は上記と同様 |
| 福岡市 | 福岡市地域貢献等空き家活用補助金(地域貢献型) | 250万円 | ・子ども食堂、福祉施設等の地域貢献施設への改修が対象 ・1年以上空き家であり、施設として10年間の活用が条件 ・市街化調整区域の限定はなし |
| 久留米市 | 久留米市空き家活用リフォーム助成事業 | 居住誘導区域内:50万円 区域外:30万円 |
・6ヶ月以上の空き家(空き家バンク登録物件は要件免除) ・所有者(自己・親族居住・賃貸目的)および賃借人が対象 ・税抜10万円以上の工事で、市内業者が施工 |
| 北九州市 | 北九州市 空き家リノベーション促進事業 | 40万円(補助率1/3) | ・申請者が39歳以下、または18歳未満の子がいる等の「若者・子育て世帯」であること ・耐震性の確保が必要 ・※2025年度制度は改正準備中 |
| 飯塚市 | 飯塚市定住促進住宅改修補助金制度 | 8万円 (15歳未満の子1人につき2万円加算) |
・所有者自身が居住し、5年以上の定住が条件 ・税抜8万円以上の工事で、市内業者が施工 ・市の住宅取得補助金と併用可能 |
| 直方市 | 直方市空き家リフォーム工事費補助金 | 市内業者:20万円 市外業者:15万円 (補助率は工事費の1/2) |
・所有者または三親等以内の親族がリフォーム後に居住すること ・税抜10万円以上の工事が対象 ・着工前の申請が必要 |
| 八女市 | 八女市空き家改修費等補助金制度 | 改修:50万円 家財撤去:10万円 |
・市の空き家バンクへの登録が必須条件 ・所有者とバンク経由の契約者が対象 ・3年間の活用が求められる ・市内業者の施工が必要 |
空き家のリフォーム・改修に関する補助金は、自治体ごとに対象となるエリアや申請者の条件、施工業者の指定など、細かな違いがあります。
たとえば、「市街化調整区域内のみ対象」「空き家バンク登録が必須」「市内業者での施工が条件」など、制度ごとに独自の要件が設けられているため、事前の確認は不可欠です。
申請は着工前が原則のため、活用を検討している場合は、早めに各自治体へ相談しておくことがスムーズな活用につながります。
空き家の解体に関する補助金
倒壊の危険性があるなど、周辺環境に悪影響を及ぼす可能性のある老朽化した空き家を解体・撤去する際の費用を補助する制度です。多くの自治体で、補助を受けるためには市の事前調査で「危険な空き家」であると認定される必要があります。
以下に、主要な市の制度をまとめました。
| 自治体名 | 制度名 | 補助金の上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 北九州市 | 北九州市老朽空き家等除却促進事業 | 30万円 | ・1981年5月31日以前の建築で、市に危険と判定された1年以上の空き家が対象 ・所有者等が申請可能で、市の事前相談が必須 |
| 久留米市 | 久留米市老朽危険空家等除却促進事業 | 65万円 | ・市の危険度判定基準を満たす木造の建物が対象 ・所有者または相続人が申請でき、市内業者の施工が必要 |
| 宗像市 | 老朽空き家等除却促進事業補助金 | 空家等対策促進区域内:60万円 その他の区域:30万円 |
・1981年5月31日以前の建築で、倒壊等の危険があると判定された1年以上の空き家が対象 ・申請前の事前相談が必要 |
| 大牟田市 | 大牟田市老朽危険家屋等除却促進事業 | 60万円 (中心市街地内は75万円) |
・1981年5月31日以前に建築された木造または鉄骨造で、市に「老朽危険家屋」等と認定された物件が対象 |
| 飯塚市 | 飯塚市老朽危険家屋解体撤去補助金制度 | 50万円 | ・申請者自身による建て替えを目的としない、危険家屋の解体が対象 |
| 筑後市 | 筑後市老朽危険家屋等除却促進事業補助金 | 50万円 | ・解体後の更地を市の空き家バンクに登録するか、利活用を図ることが条件 |
| 田川市 | 田川市老朽危険家屋等解体撤去補助金 | 20万円 | ・1981年5月31日以前に建築された木造建築物が対象 |
| 柳川市 | 柳川市老朽危険家屋等除却促進事業補助金 | 45万円 | ・木造または軽量鉄骨造の建物が対象 |
| 八女市 | 老朽危険家屋等除却促進事業補助金 | 50万円 | ・八女市内の業者による解体が条件 |
解体に関する補助金制度は、「危険度の高い老朽空き家」であるかどうかの事前判定が重要になります。
多くの自治体では、1981年(昭和56年)以前の建物を対象とし、市が実施する調査で「倒壊の恐れがある」と認定された物件でなければ補助対象にならないケースがほとんどです。
また、解体後の土地の利活用方針(空き家バンク登録や建て替え有無)によって、補助の可否や上限額が変わる場合もあります。
申請には着工前の事前相談が必須なため、自己判断で解体工事を進める前に、必ず自治体窓口で確認を行うことが大切です。
空き家の取得に関する補助金
福岡県内では、空き家の「取得」そのものを直接補助する制度は限られています。しかし、複数の自治体では移住・定住の促進を目的として、中古住宅(空き家)の購入費用や、それに伴うリフォーム費用を支援する制度を設けています。
これらの制度は、特に子育て世帯や若者世帯を手厚く支援する内容が多くなっています。
| 自治体名 | 制度名 | 補助金の上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 飯塚市 | 飯塚市戸建て中古住宅取得補助金制度 | 基本30万円(購入価格の10%) +15歳未満の子1人につき10万円加算 |
・築10年以上の物件が対象 ・購入住宅に5年以上定住することが条件(転入・転居問わず) ・二親等以内の親族間売買は対象外 |
| 直方市 | 直方市住宅取得費補助金 |
【中古購入/土地購入+新築】 ・転入者:100万円 ・市内転居者:50万円 【中古購入+解体新築】 ・転入者:150万円 ・市内転居者:100万円 ※空き家バンク物件等で5万円の加算あり |
・夫婦合計年齢80歳以下、または中学生以下の子がいる世帯が対象 ・5年以上の定住が条件 |
| 宗像市 | 古家購入建替え補助制度 | 最大100万円 (市内業者の利用や子の人数で加算) |
・古家付き土地を購入し、解体・新築して居住することが一連の条件 ・中学生以下の子がいる世帯、または夫婦合計年齢80歳未満の若年夫婦が対象 ・購入から2年以内の居住開始が必要 |
空き家の取得費用に対する補助は、すべての自治体で実施されているわけではなく、支援対象や条件が限定的です。
とくに「定住年数」や「家族構成(子育て世帯かどうか)」「購入物件の築年数・立地」など、自治体ごとに細かな要件が設定されている点に注意が必要です。
また、親族間売買は対象外とされるケースもあり、制度を利用して取得を検討する場合は、契約前に市役所等で制度の適用可否を確認しておくことが重要です。
取得後のリフォーム補助と併用できる場合もあるため、総合的に活用プランを立てることが、費用負担を抑えるポイントとなります。
空き家の家財処理に関する補助金
空き家の家財処理に関する補助金は、空き家を売却・賃貸に出す際の障壁となりがちな、室内に残された家財道具の片付けや清掃にかかる費用を補助する制度です。
単に家財を処分するだけでなく、整理後に空き家バンクへ登録するなど、空き家の利活用を促進することを補助の条件としています。
| 自治体名 | 制度名 | 補助金の上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 大牟田市 | 大牟田市空き家家財道具整理等支援事業 | 20万円(対象経費の1/2) | ・家財整理を目的とした独立補助金 ・整理後、媒介契約や市のサイト「住みよかネット」への登録など、物件を市場に戻すための行動が必要 |
| 柳川市 | 空家家財道具等撤去促進事業補助金 | 10万円(対象経費の1/2) | ・市の空き家バンク「住まえるバンク」への登録が前提条件 ・敷地内の樹木伐採や草刈り、屋内清掃も対象経費に含まれる |
| 八女市 | 八女市空き家改修費等補助金制度 | 10万円(上限まで費用の10/10補助) | ・リフォーム補助金の一部として提供 ・市の空き家バンクへの登録が前提条件 |
売却や賃貸の検討以前に、「家財が残っていて片付けられない」という理由で空き家を放置してしまうケースは少なくありません。
こうした制度は単に処分費用を補助するのではなく、補助の条件として「空き家バンクへの登録」や「媒介契約の締結」など、次のアクションを求めているのが特徴です。
そのため、空き家を本格的に手放す・活用する前段階として、家財処理補助をきっかけに動き出すことも現実的な選択肢です。
その他の補助金
自治体によっては、リフォームや解体への補助だけでなく、空き家流通を促す奨励金制度や、金融機関と連携した支援制度を取り入れている例も見られます。
| 自治体名 | 制度名/連携 | 奨励金/優遇内容 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 宗像市 | 宗像市空き家・空き地バンク利用促進奨励金 | 3万円(一時金) | ・所有者が市内業者と媒介契約を結び、市の空き家バンクに物件を登録することが条件 ・物件は指定された誘導区域内にある必要がある |
| 福岡市 | 市の補助金と【フラット35】の連携 | 【フラット35】の金利を当初5年間、年0.5%引き下げ | ・市の空き家活用補助金を利用して住宅を購入する申請者が対象 ・【フラット35】地域連携型を適用した場合に金利優遇が受けられる可能性がある |
こうした制度も併用すれば、負担を減らせるケースもあるため、あわせて確認しておきたいポイントです。
また、福岡県が設置した「福岡県空き家活用サポートセンター(愛称:イエカツ)」も活用したい支援窓口の一つです。
イエカツは、補助金のように直接費用を支援するわけではありませんが、空き家の売買、賃貸、相続、税金といったあらゆる悩みについて、専門家による無料相談が可能です。どこに相談すれば良いか分からない場合や、複数の問題を抱えている場合に、適切な専門家へ繋いでくれるワンストップの相談窓口として活用されています。
【参考:福岡県空き家活用サポートセンター】
補助金を受けるための流れと注意点
空き家に関する補助金制度は、活用すれば経済的なメリットが大きい一方で、申請から受給までの手続きが複雑な場合もあり、いくつか注意すべき点があります。
ここでは、一般的な申請の流れと、特に注意が必要なポイントについて解説します。
申請に必要な主な書類
申請時に求められる書類は自治体や制度によって異なりますが、一般的には以下のようなものが必要となります。
- 交付申請書:自治体の窓口やホームページで入手します。
- 事業計画書・収支予算書:工事の内容や費用がわかる書類です。
- 工事の見積書の写し:施工業者から取得します。
- 建物の登記事項証明書:所有者を証明する書類です。
- 固定資産税の納税証明書:税金の滞納がないことを証明します。
- 申請者の本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードの写しなどです。
- 空き家の現況写真:工事前の建物の状況を示す写真です。
- 誓約書:制度の条件を遵守することを誓約する書類です。
これらはあくまで一例です。申請を検討する際は、必ず事前に各自治体の担当窓口へ問い合わせ、必要書類の最新情報を確認することが重要です。
申請する上での注意点や落とし穴
補助金の申請で失敗しないために、以下のポイントはしっかり確認しておく必要があります。
・着工前に申請を行うこと:
これは最も重要なポイントです。補助金は、自治体から「交付決定通知」を受けた後に契約・着工した工事だけが対象です。申請前に工事を始めると補助金を受け取れなくなるため、注意が必要です。
・予算の上限や申請期間を事前に確認:
補助金には年度ごとの予算枠があり、上限に達すると受付が終了します。先着順となっている場合も多いため、早めの情報収集と申請準備が重要です。
・補助金は「後払い」が原則:
工事完了後に自治体の検査を経て支払われるのが一般的です。一時的に自己負担が発生するため、資金計画に組み込んでおく必要があります。
・業者選びにも注意が必要:
自治体によっては、「市内に本店を置く業者」が補助対象となるケースがあります。施工業者が条件を満たしているかどうかを確認しておきましょう。
・他の補助金との併用可否を確認する:
国や自治体の他の補助制度と併用できない場合もあります。複数の制度を検討している場合は、必ず事前に併用の可否を確認してください。
補助金以外で空き家問題を解決する方法
自治体の補助金制度は空き家対策として有効な方法の一つですが、すべての空き家が制度の対象となるわけではありません。また、手続きの煩雑さや一時的な自己負担の発生などから、利用が難しいケースも見られます。
まずは、補助金の活用が難しい代表的なケースを整理し、そのうえで代替となる3つの解決策をご紹介します。
補助金だけでは難しいケースがある
以下のような状況では、補助金制度の利用が難しい、または最適ではない場合があります。
- 空き家が補助金の条件を満たしていない(例:築年数が浅い、危険家屋に該当しない、対象地域外にある)
- リフォームや解体に必要な費用を、一時的にでも自己負担するのが難しい
- 申請に必要な手続きに時間や労力をかけられない
- 空き家を活用する予定がなく、今後の管理を続ける意思がない
このような場合は、無理に補助金制度を利用しようとせず、売却など他の選択肢もあわせて検討してみましょう。
空き家を売却する
空き家を今後利用する予定がなく、管理の負担や固定資産税の支払いから解放されたいと考えているなら、売却は最も現実的で有効な解決策です。
売却してしまえば、建物の維持管理や近隣への配慮といった精神的なストレスがなくなり、まとまった現金を得られる可能性もあります。
ただし、一般的な不動産会社では、老朽化が激しい物件や辺鄙な場所にある物件は、仲介を断られるケースも少なくありません。
もし、そのような「売りにくい」空き家でお困りであれば、専門の買取業者に相談することをおすすめします。「空き家パス」のような買取業者は、築年数が古い物件や法的な問題を抱えた物件でも、現状のまま買い取ることが可能です。仲介と異なり、買主を探す必要がないため、スピーディーに現金化できる点も大きなメリットです。
関連記事:福岡の空き家買取専門業社5選|戸建て売却相場や選び方、不用品回収業者も合わせて紹介
空き家バンクを活用する
「空き家バンク」は、空き家の売却や賃貸を希望する所有者と、それを希望する利用者をマッチングする仕組みで、自治体が運営しています。営利を目的としていないため、通常の不動産情報サイトでは扱いにくい物件も登録されている点が特徴です。
地域への移住者を呼び込み、地域活性化を目指す役割もあるため、空き家を社会貢献に活かしたいと考える方に適しています。
ただし、登録してもすぐに買い手や借り手が見つかるとは限らない点には注意が必要です。
空き家を活用する
売却せずに空き家を資産として活用したい場合は、賃貸物件として貸し出す、カフェや民泊などの施設に再生する、といった方法が考えられます。
特に立地条件が良好な空き家であれば、リフォームやリノベーションを行うことで、安定的な収益源として活用できる可能性もあります。
ただし、事業化するには初期投資がかかるうえ、継続的な管理や運営の負担も発生します。採算性や地域のニーズをよく見極めたうえで、無理のない範囲で進めることが大切です。
よくある質問
空き家の補助金活用や処分方法については、多くの方が共通の疑問を抱えています。ここでは、特に問い合わせの多い4つの質問にお答えします。
Q:補助金と売却、どちらが良いですか?
A:空き家を今後どう活用したいかによって、最適な選択肢は変わってきます。ご自身で住む予定がある、あるいはリフォームして賃貸などに活用したい場合は、補助金を利用して費用を抑える方法が有効です。
一方、活用の予定がなく、管理や固定資産税の負担から解放されたい場合には、売却が現実的な手段です。老朽化が進んだ物件や立地が不利な「売りにくい」空き家でも、「空き家パス」のような専門の買取業者であれば、現状のまま買い取ってもらえるケースがあります。
Q:古い空き家や傷みがある空き家でも補助金は使えますか?
A:はい、利用可能です。むしろ、老朽化した空き家ほど補助対象となりやすい傾向にあります。補助金制度の目的の一つが、倒壊リスクのある建物の除却や再活用にあるためです。
建物の状態によっては、リフォームではなく「危険空き家」として解体費用の補助が適用されることもあります。利用できる補助金の種類は自治体ごとに異なるため、まずは所有する空き家がある市町村の担当窓口に問い合わせて確認してください。
Q:空き家を壊すのにかかるお金は?
A:建物の構造や面積、立地条件によって異なりますが、一般的な木造住宅では1坪あたり3万〜5万円程度が目安です。
たとえば延床面積30坪の木造住宅であれば、解体費用はおおよそ90万〜150万円程度になります。
ただしこれは建物本体の解体費用のみで、アスベストの除去や庭木・ブロック塀の撤去などが必要な場合は、追加費用が発生する点にも注意が必要です。
正確な費用を把握するためには、複数の解体業者から見積もりを取り、内容を比較することが推奨されます。
Q:空き家を解体すると固定資産税はどうなる?
A:多くのケースで、翌年以降の固定資産税が増額されます。これは、住宅が建っている土地に適用される「住宅用地の特例措置」が、解体によって適用外になるためです。
場合によっては、税額が従来の最大6倍程度にまで増える可能性があります。そのため、解体費用だけでなく、解体後に発生する税負担も含めて、事前に総合的な検討を行うことが大切です。
まとめ
福岡県では、空き家のリフォームや解体、取得などに使える補助金制度が多くの自治体で整備されており、状況に応じて費用負担を軽減しながら空き家の利活用を進めることができます。
一方で、すべての空き家が制度の対象となるわけではなく、申請のタイミングや手続きの手間など、注意すべき点も少なくありません。そもそも空き家を活用する予定がない方にとっては、売却という選択肢のほうが現実的なケースもあります。
まずは、ご自身やご家族のライフプランと照らし合わせながら、空き家を「再生して残す」のか「売却して手放す」のかを、無理のない範囲で検討してみてください。
もし「補助金の申請が難しい」「解体やリフォームの費用が捻出できない」「売却先が見つからない」などの悩みがあれば、空き家の買取を専門とする業者への相談もひとつの手です。
空き家パスでは、相続物件や再建築不可物件、築年数が古い住宅など、他社では敬遠されやすい物件でも対応可能です。現状のまま査定・買取を行っているため、手間をかけずに空き家の問題を解決できます。
相談・査定は無料です。福岡県で空き家のお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にご相談ください。


この記事の監修者 高祖広季
株式会社ウィントランス 代表取締役 高祖広季
空き家パスを運営している株式会社ウィントランスの代表です。日本の空き家問題を解決するため空き家専門の不動産事業を展開中。「空き家パス」と「空家ベース」というサービスを運営しています。これまで500件以上の不動産の売買取引に携わってきました。空き家でお困りの方の力になりたいと思っています。