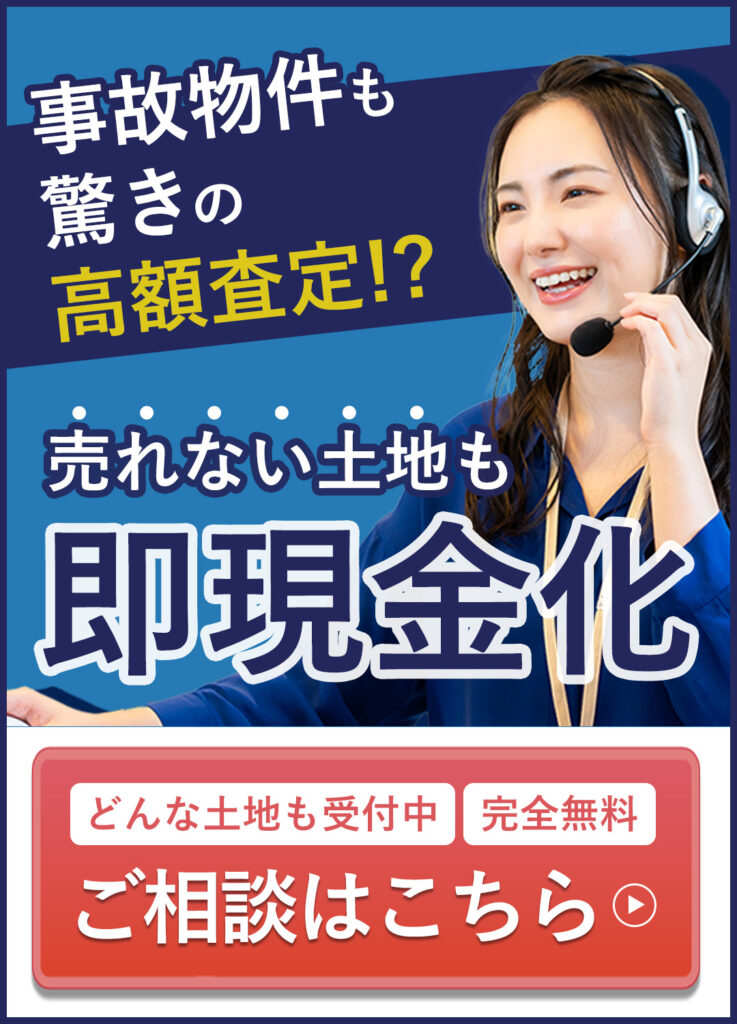東京都の空き家補助金を解説ー解体・リフォームなどで活用!申請の流れや注意点も
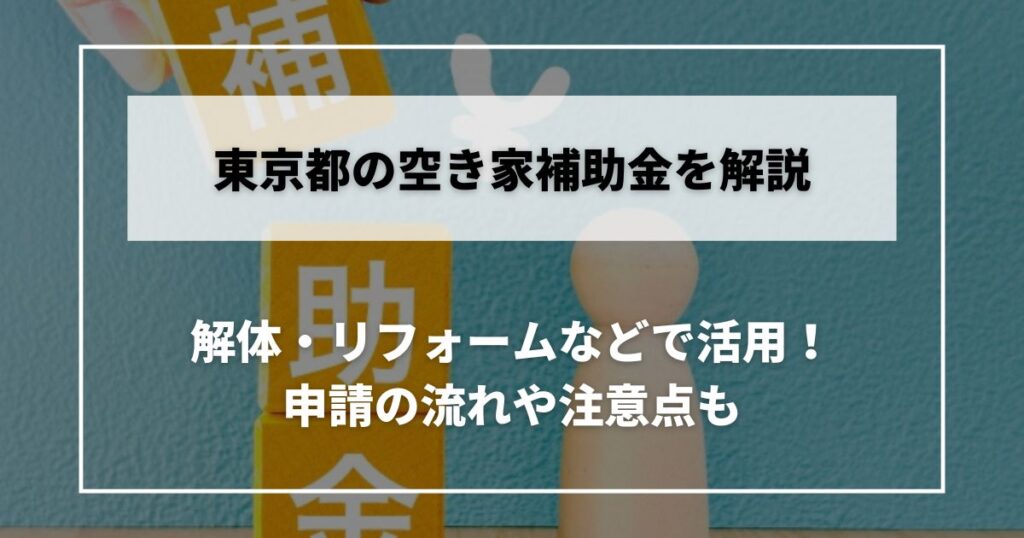
東京都内に空き家を所有している方の中には、固定資産税や老朽化による修繕・解体費用の負担に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。こうした費用負担を軽減する方法のひとつが、自治体が提供する補助金や助成金制度の活用です。
東京都や区市町村では、空き家のリフォーム・解体・家財整理などに対して、条件を満たせば数十万円から数百万円の補助を受けられる制度が設けられています。
本記事では、東京都および各自治体の代表的な補助金制度を目的別に紹介し、申請の流れや注意点も詳しく解説します。さらに、補助金が使えない場合でも検討できる、空き家の売却やバンク登録といった代替策についても取り上げます。
この記事でわかること
- 東京都の空き家事情と課題
- リフォーム・解体・取得・家財整理に使える補助金制度
- 補助金申請の流れと注意点
- 補助金を使えない場合の代替策(売却・バンク登録・活用)
補助金の活用とあわせて、空き家の売却も重要な選択肢のひとつです。
空き家パスは、相続不動産や訳あり物件の買取に強みを持つ不動産会社です。
都心から離れたエリアの物件や、再建築不可・老朽化物件など、他社では断られるケースでも積極的に対応しています。ご相談や査定は完全無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
東京都の空き家事情、現状は?
東京都の空き家に関する令和5年(2023年)の住宅・土地統計調査において、東京都内の空き家数は約90万戸(89.8万戸)、空き家率は10.9%に達しています。この数値は、平成30年(2018年)の約81万戸、空き家率10.6%から増加しており、都内の住宅全体における空き家の割合が高まっていることがわかります。
東京都の空き家率は、全国平均の13.8%よりは低いものの、空き家の絶対数が全国で最も多く、都市部においても空き家問題が進行していることが明らかになっています。今後は、より一層の対策が求められる状況です。
空き家問題は地方特有のものと考えられがちですが、都市部でも増加していることが明らかになっています。
参照:統計局ホームページ/令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果
空き家問題解決のひとつ「補助金制度」
空き家のリフォームや解体、家財の処分などには、まとまった費用がかかります。こうした金銭的な負担を軽減する方法のひとつとして、東京都や各区市町村では補助金制度を設けています。
補助金制度は、空き家の適切な管理や活用を後押しすることを目的とした制度で、条件を満たせば数十万円から数百万円の支援を受けられる場合もあります。
補助金の内容や対象となる工事、申請条件などは自治体によって大きく異なります。空き家が所在する地域の公式ホームページを確認し、詳細を確認してから申請を検討しましょう。
東京都で使える空き家関連補助金
ここでは、東京都の主な補助金制度を目的別に分けて紹介します。制度の名称、内容、補助額、要件は変更される可能性があるため、申請を検討する際は、必ず各自治体の公式ホームページで最新の情報を確認するか、担当窓口にお問い合わせください。
空き家のリフォーム・改修に関する補助金
老朽化した空き家を再利用するには、バリアフリー化、省エネルギー化などの改修が必要です。東京都内の自治体では、こうしたリフォーム工事に対する補助制度が設けられています。
以下は、代表的な補助金の一覧です。
| 制度名(運営主体) | 対象者 | 対象工事(リフォーム内容) | 補助率・上限額 | 申請時のポイント |
|---|---|---|---|---|
| 東京都既存住宅省エネ診断・設計支援事業 | 都内在住で、個人が所有する住宅空き家のリフォームを予定している者 | 省エネ診断および設計(工事費は対象外) | 診断:費用3分の2(上限21万円) 設計一般:5分の2(上限18万円) ZEH設計:5分の4(上限36万円) |
工事前に申請必須。リフォーム設計のための支援制度 |
| 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業(既存住宅省エネ改修促進事業) | 個人が所有し、自ら居住または利活用予定の都内空き家 | 内窓・外窓・窓ガラス・玄関ドアの交換、壁・屋根などへの断熱材設置、高断熱浴槽設置 | 内窓:0.7~5.3万円 箇所外窓:2.5~11万円 箇所ガラス:0.2~3.6万円/枚 ドア:5.2~11万円/戸 断熱材:上限100万円/戸または費用の1/3 浴槽:上限9.5万円/戸または費用の1/3 |
工事前申請・設置前契約が原則。複数工事の併用が可能。補助受付は年度内先着順 |
| 戸建住宅省エネ等リフォームアドバイザー派遣 | 都内の住宅所有者(耐震・省エネ検討者) | 建築士等による現地診断や省エネ・再エネ改修提案 | サービス自体は無料(派遣)※工事費は対象外 | リフォーム前の相談段階で利用可能。制度全体を把握するのに便利 |
補助制度を活用することで、空き家のリフォームにかかる初期費用を大幅に抑えることができます。
ただし、制度によっては改修後の利用目的や入居者の条件など、細かな要件が設けられている場合もあるため、事前に内容を十分に確認しておくことが大切です。
空き家の解体に関する補助金
倒壊や火災などのリスクが高い老朽化した空き家は、解体によってリスクを取り除き、土地を活用しやすくなります。多くの自治体では、管理不全な空き家や危険建築物の除却(解体)に対する補助制度を設けています。
以下に、代表的な制度をまとめました。
| 自治体 | 制度・事業名 | 主な補助内容 | 補助額・補助率 | 主な要件・特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 品川区 | 不燃化特区支援事業ほか | 老朽建築物の解体(区域・状態により異なる) | 上限1550万〜2200万など(補助率:全額等) | 区の指定区域・判定が必要。昭和56年5月31日以前など建築基準も要件。 |
| 墨田区 | 不燃建築物建築促進助成金 | 老朽建築物の解体費用 | 上限150万円〜全額助成(条件あり) | 指定地区(不燃化特区)内・区職員の現地調査・指定要件 |
| 葛飾区 | 不燃化特区老朽建築物除却助成金 | 老朽危険建築物の解体 | 最大200万円定額ほか | 事前区相談・特定地区限定・指定建築物 |
| 府中市 | 木造住宅耐震診断・改修助成/老朽危険空き家解体促進 | 管理不全空家・危険空家の解体 | 解体費の1/2(上限50万円) | 市の認定・補助金交付決定後に着工 |
解体補助金の申請には、着工前の申請と事前相談が必須です。工事を始めてからでは補助の対象外となるため、計画段階から自治体との連携が重要です。
また、建物を解体すると、固定資産税の優遇措置が適用されなくなります。更地として評価されることで、税額が上がることが一般的です。解体後の土地の活用方法や税金負担についても、あらかじめ検討しておく必要があります。
空き家の取得に関する補助金
若年層や子育て世帯の定住を促すために、空き家の取得費用を補助する制度を設けている自治体もあります。特に、都心から離れたエリアでは、移住支援の一環として手厚い補助を受けられることがあります。
以下は、東京都内の代表的な制度の一覧です。
| 自治体 | 制度名・事業名 | 主な補助内容 | 補助額・補助率 | 主な要件・特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 青梅市 | 青梅市移住支援金(住宅取得応援金・子育て応援加算等) | 市外から転入し住宅取得(新築・中古・空き家再生含む)の支援 | 基準10万円+各種加算、最大100万円(例:若者加算、子育て加算、空き家加算等) | ・転入時もしくは転入後2年以内の住宅取得 ・世帯で5年以上定住意思 ・中学生以下の子1人につき加算10万円等 |
| 奥多摩町 | 奥多摩町移住・定住応援補助金 | 定住目的の住宅購入・新築・リフォーム支援 | 工事費用の1/2、上限200万円 | ・世帯の場合:夫婦いずれかが45歳以下or18歳未満の子ども含む世帯等 ・補助メニュー複数 |
空き家の取得に関する補助金を利用する場合は、多くの制度で「購入後に一定期間以上その地域に定住すること」が条件とされています。途中で転居した場合には、補助金の返還を求められるケースもあるため、長期的なライフプランを見据えた検討が重要です。
また、補助金の対象となる物件には、築年数や面積、耐震基準などの細かい条件が定められている場合があります。空き家の購入とあわせてリフォームを行う計画がある場合は、前述のリフォーム補助金と併用できる可能性もあるため、事前に自治体の窓口で確認することをおすすめします。
空き家の家財処理に関する補助金
空き家の売却や賃貸、解体を進める際に大きな負担となるのが、室内に残された家財やごみの処分です。
こうした課題に対応するため、東京都では、空き家の利活用を促進する目的で、家財整理にかかる費用を補助する制度を設けています。
家財整理に特化した補助金は少なく、多くの場合、解体やリフォーム、地域貢献活動といった空き家全体の利活用・管理とセットで支援される傾向にあります。
| 制度名・事業名 | 主な補助内容 | 補助額・補助率 | 主な要件・特記事項 |
|---|---|---|---|
| 東京都空き家家財整理・解体促進事業 | 空き家の家財整理または解体に係る費用の一部を補助 | 家財整理: 対象経費(税抜)の1/2、上限50,000円(1,000円未満の端数切り捨て) 解体: 対象経費(税抜)の1/2、上限100,000円 |
東京都空き家ワンストップ相談窓口への相談が必須条件。都内の空き家1軒につき、家財整理か解体のいずれか一方が対象。 |
家財整理に関する補助金は、単なる処分目的では対象外となる場合が多く、空き家の利活用や地域貢献といった目的が求められます。補助申請は作業前が原則で、着手後は対象外になることがほとんどです。
特に東京都では「空き家ワンストップ相談窓口」で制度の案内や申請方法の相談が可能ですので、まずは自治体窓口や公式サイトで、制度の有無や条件を確認しましょう。
以下の記事で、東京都の不用品回収業者もご紹介しています。
東京で空き家売却に強い買取業者5選|選び方やすぐに買い取ってもらうためのポイントを解説
その他の補助金
リフォーム、解体、取得、家財整理のほかにも、東京都や各区市町村では、空き家問題に対応するための補助制度や支援事業が展開されています。
たとえば、空き家の活用方法や法律・税金に関する課題について、専門家のアドバイスを受けるための相談費用を補助する制度や、建物の安全性を確認するための特定調査に対する補助などがあります。
また、空き家を地域交流の場や店舗として活用する場合の改修費用を支援する事業も実施されています。
| 自治体 | 制度名・事業名 | 主な補助内容 | 補助額・補助率 | 主な要件・特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 目黒区 | 空家無料専門相談 | 弁護士・司法書士・税理士・建築士等への専門相談費用 | 無料(区が全額負担) | 区内の空き家を所有・管理する区内在住者が対象 |
| 東京都(各区市) | 民間建築物アスベスト調査・除去等助成制度 | 吹付けアスベスト等の調査、除去、封じ込め工事 | 調査:全額補助(上限有) 除去:経費の2/3(上限有) | 対象の建材や着工年度などに条件。申請窓口は各区市 ※要公式確認 |
| 練馬区 | 空き店舗等活用支援事業補助金 | 空き店舗等を改修して新たな事業を始める際の工事費 | 経費の2/3(上限100万円) | 商店街活性化など、区が対象とする事業であること |
| 新宿区 | 空家等の適切な管理及び有効活用に係る協定 | 区と事業者が協定を結び、空き家管理や活用の支援(補助金ではなく支援体制) | – | 区が窓口となり、協定事業者の案内やワンストップ管理支援、相談受付等 |
空き家に関する悩みは、一軒ごとに異なります。そのため、自治体の支援策も多岐にわたります。
まずは、所有する空き家が所在する自治体の建築指導課や住宅政策課などの担当窓口へ相談することが大切です。
補助金を受けるための流れと注意点
補助金制度を利用するには、所定の手続きと書類提出が必要です。スムーズに申請を進めるために、必要な書類や注意点を事前に把握しておきましょう。
申請に必要な主な書類
補助金の申請には、本人や物件の情報を証明するための書類が必要です。制度によって要求される書類は異なりますが、一般的に以下のようなものが求められます。
一般的な必要書類
- 補助金交付申請書
- 本人確認書類
- 登記事項証明書
- 固定資産評価証明書や名寄帳
- 工事の見積書
- 工事前の現況写真
- 工事内容を示す図面
- 納税証明書
- 住民票
書類の取得には時間がかかるものもあるため、利用したい補助金制度が決まったら、まずは自治体のホームページや窓口で必要書類の一覧を確認し、早めに準備を始めることが大切です。
申請する上での注意点や落とし穴
補助金申請でありがちな失敗を避けるため、以下の点に注意しましょう。
工事契約・着工前に申請が必要
補助金制度では、交付決定通知を受け取る前に工事を始めた場合、原則として補助の対象外となります。「工事後の申請」は認められないため、必ず着工前に申請を行いましょう。
年度予算には上限がある
自治体の補助金には、年度ごとの予算上限が設けられています。申請が集中すると、早期に受付が終了するケースもあります。
人気の高い制度では、毎年4月から6月の間に予算が消化されることもあるため、申請はできるだけ年度の早い段階で行うのが理想です。
補助金は後払いが原則
補助金は、原則として「工事完了後」に支給されます。費用は一度自己負担で全額を支払い、その後に実績報告を行い、補助金が支給される仕組みです。
あらかじめ資金計画を立てた上で、手続きを進める必要があります。
補助対象となる経費や業者を要確認
「市内業者を利用すること」や「耐震診断付き工事に限る」といった要件が設けられている場合があります。
また、設計費や消費税が補助の対象外となる制度も存在するため、見積もりを取る際には、自治体と業者の双方に確認することが重要です。
他の補助金との併用制限に注意
国や東京都、各区市町村が実施する補助制度には、併用が認められるものと認められないものがあります。複数の制度を利用したいと考えている場合は、必ず事前に各窓口へ確認してください。
補助金以外で空き家問題を解決する方法
補助金制度は有効な支援策ですが、全てのケースに適用できるわけではありません。制度の要件に合わない、資金が足りない、申請の手間がかけられないといった理由から、別の解決策を選ぶ方も多くいます。
補助金だけでは難しいケースがある
補助金制度の利用を検討する前に、ご自身の状況が本当に補助金の活用に適しているかを確認する必要があります。
以下のような状況では、補助金以外の方法を検討した方が現実的です。
・空き家を活用する予定がない場合
→ 賃貸や再利用が前提となる補助金には、該当しない可能性があります。
・工事費を一時的に立て替えることが難しい場合
→ 補助金は原則事後精算方式のため、初期費用を自己負担できないと申請の実行が困難です。
・書類作成や役所とのやり取りが負担になる場合
→ 補助金の申請には、複数の書類提出や現地確認、相談対応などが必要になります。
・建物や所有者が制度の条件を満たしていない場合
→ 旧耐震基準に該当しない建物や、税金の滞納がある物件などは対象外となることがあります。
空き家を売却する
補助金の活用が難しい場合、最も現実的な解決策として挙げられるのが「売却」です。空き家を売却することで、所有者としての経済的・管理上の負担を根本的に解消する手段となります。
売却の主なメリット
- 固定資産税や火災保険料、修繕費といった維持管理コストがゼロになる。
- 建物の倒壊や不法投棄など、所有者としての管理責任がなくなる。
- まとまった現金が手に入る。
◾️売却方法の比較
| 方法 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 仲介 | 市場価格で売れる可能性あり/買主が見つかるまで時間がかかる/内覧・清掃が必要 | 時間に余裕があり、なるべく高く売りたい人 |
| 買取 | 早期現金化/内覧・清掃不要/価格はやや低め | すぐに売りたい人、訳あり物件を持つ人 |
関連記事:東京で空き家売却に強い買取業者5選|選び方やすぐに買い取ってもらうためのポイントを解説
空き家バンクを活用する
自治体が運営する空き家バンクは、空き家を売却・賃貸したい人と、購入や賃借を希望する人をマッチングする制度です。登録に費用はかからず、補助金の申請条件となる場合もあります。
ただし、一般的に不動産会社に比べて集客力や成約率は低く、契約までの手続きも原則として所有者自身が対応する必要があります。そのため、一定の労力と時間がかかることを理解しておく必要があります。
空き家を活用する
売却ではなく、収益化を目指して空き家を「活用する」という選択肢もあります。主な活用方法は以下の通りです。
| 活用法 | 概要 | 注意点 |
|---|---|---|
| 賃貸住宅 | 改修後に貸し出して家賃収入を得る | 空室リスク、管理費用が継続的に発生 |
| シェアハウス/民泊 | 複数人向けに貸し出す/短期貸しで高収益を狙う | 運営ノウハウ・許可が必要 |
| 更地にして活用 | 駐車場や資材置場などに転用 | 解体費用がかかり、固定資産税が増額される可能性あり |
いずれの活用方法も、初期投資や専門知識が必要となり、必ず成功するとは限りません。メリットとデメリットを比較した検討が不可欠です。
よくある質問とトラブル例
空き家の補助金活用や処分を検討する中で、多くの方が同じような疑問や不安を抱えます。ここでは、よくある質問と、起こりがちなトラブル例についてQ&A形式で解説します。
Q: 補助金と売却、どちらが良いですか?
A:どちらが適しているかは、空き家の状態や所有者の事情によって異なります。リフォームや解体などに補助金を活用して再生・活用を目指す方法もあれば、売却によって早期に負担を解消する選択肢もあります。
補助金は支援を受けつつ空き家を活用できる点が魅力ですが、申請や工事の手間、自己負担が生じる場合もあります。一方、売却であれば、管理責任や税金負担から早期に解放されるというメリットがあります。
資金状況や活用意向をふまえて、どちらが現実的かを検討しましょう。
Q: 古い空き家や傷みがある空き家でも補助金は使えますか?
A:はい、使えます。老朽化した空き家は、多くの補助金制度において主な対象とされています。
たとえば、耐震性が低い住宅の改修や、倒壊のリスクがある建物の解体などを対象とした補助が、積極的に実施されています。
ただし、建物の劣化が著しく、改修が困難と判断された場合には、リフォームではなく解体に対する補助金の対象となるケースが多いです。
Q: 補助金申請が難しそう…誰かに頼めますか?
A:以下のようなサポートを活用することができます。
・施工業者(工務店・解体業者など)
→ 補助金を活用した工事の実績がある業者であれば、必要書類の準備や手続きのサポートをしてもらえることがあります。
・行政書士
→ 書類作成から提出までを有料で代行してくれるため、手続きに不安がある方にとって有効な選択肢です。
・自治体の窓口
→ 補助金申請の流れや必要書類について、無料で相談することができます。
Q: 買取業者って本当に大丈夫?だまされそう…
A:買取業者を選ぶ際には慎重な判断が必要です。以下のポイントを確認しましょう。
・宅建免許の有無を確認する
→ 免許番号のカッコ内に記載された数字は更新回数を示しており、営業年数の目安になります。
・査定価格の根拠をきちんと説明してくれるかどうか
→ 納得できる理由を提示する業者であれば、信頼性が高いといえます。
・複数の業者に査定を依頼する
→ 複数の見積もりを比較することで、価格の妥当性を把握しやすくなります。
信頼できる業者を選ぶために、免許の有無や査定の根拠、他社との比較を行えば、空き家買取はスムーズかつ現実的な選択肢となります。
まとめ
東京都内では、空き家の増加が大きな社会課題となっています。放置すれば、固定資産税や修繕費などの維持コストだけでなく、倒壊や近隣トラブルといったリスクも高まります。
こうした負担を軽減する手段として、各自治体が提供する補助金制度は非常に有効です。
リフォーム・解体・家財整理・取得など、目的に応じた制度を活用することで、空き家の再生や処分が現実的になります。
ただし、補助金を利用するには事前申請や自己資金の立て替えが必要な場合もあり、すべての人にとって最適な選択とは限りません。
条件に合わない場合や、早期に問題を解決したい場合は、「売却」という選択も視野に入れましょう。
空き家パスでは、再建築不可物件や相続トラブルを抱えた物件、遠方にある空き家など、他の不動産会社で買取を断られたようなケースでも、積極的に査定・買取を行っています。
全国の物件に対応しており、査定やご相談はすべて無料です。室内に残置物がある状態でも、現状のままで買取できますので、手間をかけずに空き家を手放したい方に最適です。ぜひ一度空き家パスへご連絡ください。