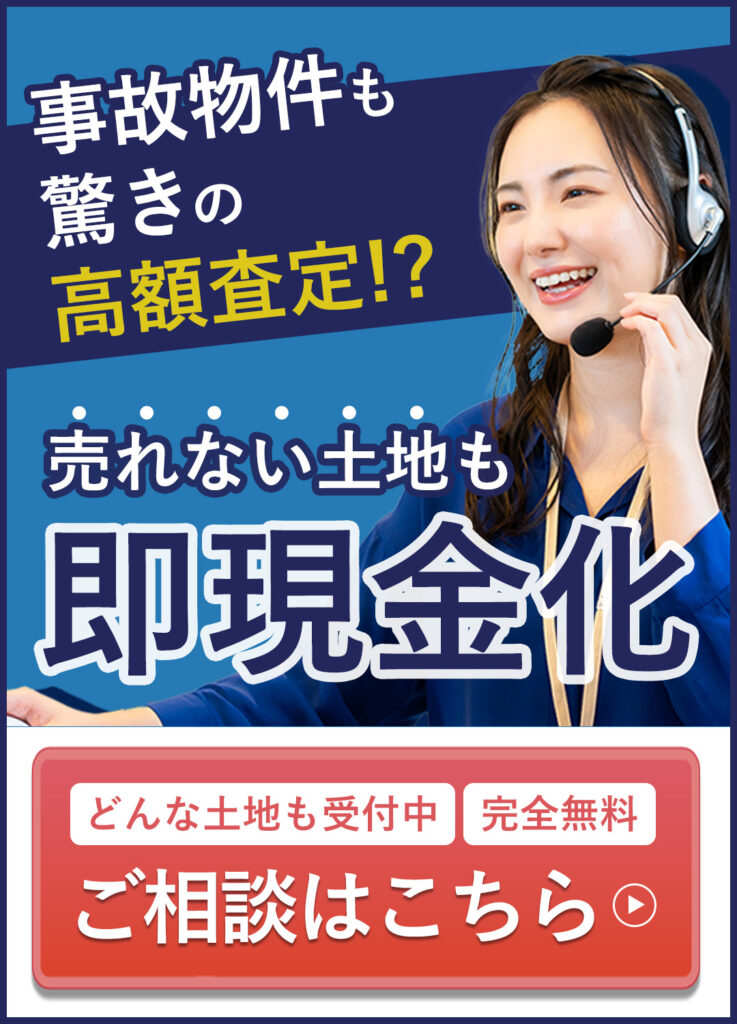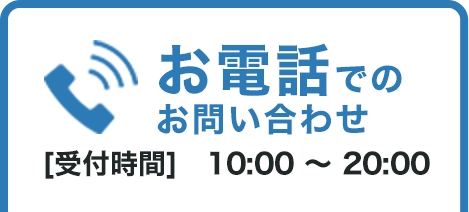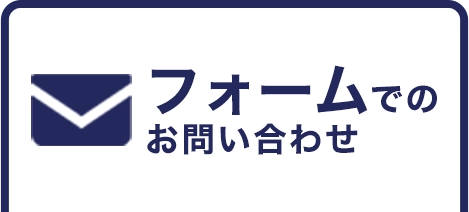山梨県の空き家補助金を解説ー解体・リフォームなどで活用!申請の流れや注意点も
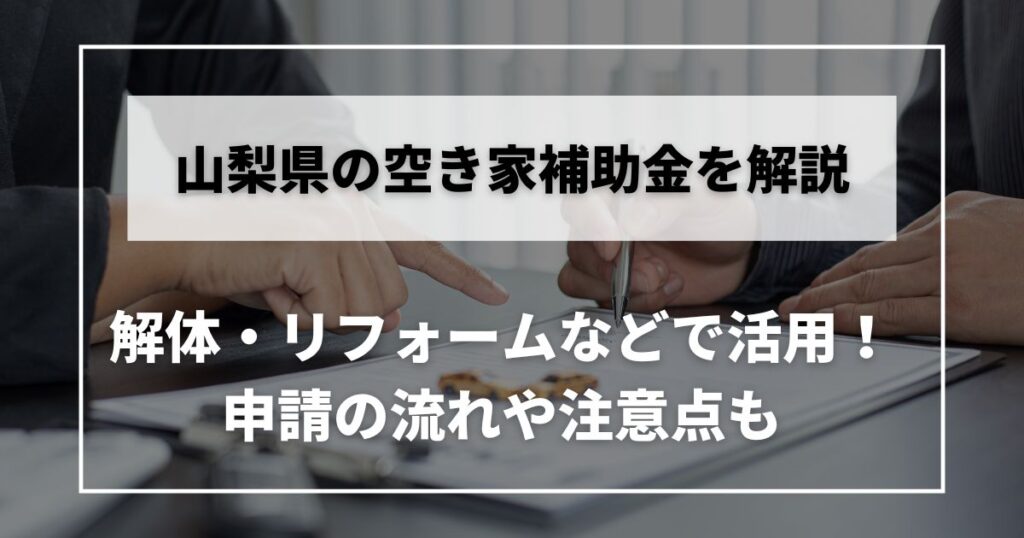
「山梨県の空き家をどうにかしたいけれど、費用の問題で動き出せない」そんな悩みを抱えていませんか。
山梨県では、空き家率が全国平均を大きく上回っており、老朽化した空き家の増加が地域課題として深刻化しています。こうした状況を受け、県内の多くの自治体では、空き家のリフォーム・解体・取得などに利用できる補助金制度を整備し、所有者の経済的な負担を軽減する取り組みが進められています。
制度を活用すれば、管理や活用にかかる費用を抑えながら、空き家の再利用や売却、解体といった次のステップに踏み出すことが可能です。申請には一定の条件がありますが、うまく活用すれば実質的な支出を大きく減らせる場合もあります。
本記事では、山梨県で利用できる補助金の種類や対象条件、申請手続きの流れ、補助金ではカバーしきれないケースの対応策までを、具体的に解説します。
空き家の対応に悩んでいる方は、資金面の選択肢を広げるためにも、ぜひ最後までご覧ください。
- 山梨県における空き家の現状と課題
- 山梨県および各市町村で使える主な補助金制度
- 補助金を申請する際の具体的な流れと注意点
- 補助金だけで対応できない場合の対処法
- 空き家パスを活用した売却・処分の選択肢
空き家パスでは、築古や訳あり物件も含め、全国対応で空き家の無料相談・査定を受け付けています。補助金の対象外だった場合や、遠方で管理が難しい空き家の処分を検討している方も、まずはお気軽にご相談ください。
山梨県の空き家問題、現状は?
山梨県では、空き家の増加が深刻な問題となっています。
2024年4月に公表された総務省の「住宅・土地統計調査(2023年)」によると、山梨県の空き家率は20.5%で、全国平均の13.8%を大きく上回っています。この数値は徳島県と和歌山県(ともに21.2%)に次いで全国で3番目に高く、空き家の管理や利活用に対する社会的な関心が高まっています。
背景には、人口減少や高齢化に加えて、別荘地や農家住宅といった使われない建物が多いという地域特性も影響しています。
こうした状況を受けて、山梨県では県全体での空き家対策が進められており、市町村ごとに補助制度を設けて対応を強化しています。補助制度を上手に活用すれば、空き家の適切な処分や再活用を費用面からサポートしてもらうことができます。
【参考:令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果】
空き家問題解決策のひとつ「補助金制度」
空き家を所有している方が最も悩みやすいのが、リフォームや解体にかかる費用です。老朽化した建物を修繕したり、安全に解体したりするには、数十万円から百万円を超える出費が必要になることも珍しくありません。
特に相続によって突然空き家を所有することになった方にとっては、「使う予定もない家に、なぜこんなに費用がかかるのか」と困ってしまうケースが多く見られます。
こうした負担を軽減するために、山梨県および県内各市町村では、空き家のリフォームや解体、家財整理、取得などに活用できる補助金制度が用意されています。
制度の内容は自治体によって異なりますが、共通しているのは「放置空き家の減少」と「地域の安心・安全な暮らしの確保」を目的としている点です。
補助金制度は、空き家を単なる負担ではなく、「再活用できる資産」として前向きに動き出すための支援策です。たとえば、住宅として再生する、移住者に貸し出す、安全に解体して跡地を活用するなど、次のステップへ進むための手助けとなります。
山梨県で使える空き家関連補助金
山梨県では、空き家の利活用や解体を支援するために、県や市町村がそれぞれ独自の補助金制度を整備しています。
補助金の対象や上限額、条件は自治体によって異なりますが、いずれも空き家を有効に活用・整理するための強力な後押しとなります。
ここでは、山梨県内で活用できる代表的な補助制度を、目的別に紹介します。
空き家のリフォーム・改修に関する補助金
空き家を住まいとして再活用するうえで、多くの方が最初に直面するのが改修費用の問題です。老朽化したキッチンやトイレの修繕、断熱性の向上、外壁や屋根の補修など、住める状態にするには多額の工事費用がかかる場合もあります。
こうした負担を軽減するために、山梨県内の各市町村では、空き家のリフォーム・改修を対象とした補助金制度を設けています。
制度によっては、空き家バンクへの登録が前提となっていたり、定住や移住促進を目的にした加算措置がある場合もあります。
主な制度の一部を紹介します。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 甲斐市 | 空き家バンクリフォーム補助金 | 100万円 |
・空き家バンクへの登録 ・市内施工業者の利用 ・住民票の移動 |
| 南アルプス市 | 空き家活用定住促進事業補助金 | 100万円 |
・5年以上の定住または空き家バンクへの登録 ・3親等以内の親族間取引でないこと |
| 北杜市 | 北杜市空き家バンク活用促進リフォーム費等補助金 | 100万円 |
・空き家バンクへの登録 ・5年間の定住・登録義務(違反時返還) ・市内事業者の利用 |
| 甲府市 | 甲府市地域活性化施設整備費補助金 | 200万円(耐震改修含む場合300万円) |
・地域活性化施設(交流施設等)への改修 ・10年以上の施設利用 ・自治会の同意 |
| 南部町 | 南部町空き家バンク利用促進事業補助金 | 50万円 |
・購入者は5年以上の居住予定 ・空き家バンクへの登録 ・町内事業者の利用 |
| 笛吹市 | 笛吹市空き家バンク登録物件に係る改修等補助金 | 20万円 |
・空き家バンクへの登録 ・市内施工業者の利用 |
| 上野原市 | 空き家・空き店舗バンクリフォーム補助事業 | 40万円 |
・対象者:空き家バンク登録物件の賃貸借契約者・所有者 ・市内施工業者の利用 |
| 富士川町 | 富士川町空き家改修費補助金 | 25万円 |
・対象者:空き家バンク登録物件の購入・賃貸者 ・5年以上の定住意思があること ・町内事業者の利用 |
| 富士河口湖町 | 空き家リフォーム補助金制度 | 20万円 |
・空き家バンクへの新規登録と5年間の登録継続 ・町内事業者の利用 |
| 小菅村 | 小菅村空き家改修等補助事業 | 100万円 | ・5年以上の貸出意思があること |
これらの制度を活用することで、改修費用の負担を軽減しながら、空き家を再び居住用住宅として生まれ変わらせることが可能です。
ただし、制度ごとに申請条件や事前審査の有無が異なるため、必ず各自治体の公式情報を確認しましょう。
空き家の解体に関する補助金
老朽化が進んだ空き家の中には、倒壊の危険性がある建物や、衛生・防犯面で周囲に悪影響を与えるケースも少なくありません。
しかし、空き家の解体には数十万円から百万円以上の費用がかかることがあり、「解体したくても費用が出せない」と悩む方も多くいます。
山梨県内の多くの自治体では、こうした状況に対応するため、空き家の除却(解体)に関する補助制度を整備しています。
制度によっては、特定空家に認定された建物に対して助成を行うケースや、解体後の跡地活用を条件に高額な補助を受けられる場合もあります。
主な制度の一部を紹介します。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 富士吉田市 | 富士吉田市老朽化空家除却事業費補助金 | 100万円 |
・昭和56年5月31日以前着工の個人所有の木造住宅 ・耐震診断で倒壊の危険性があると判断されたもの ・事業着手前の申請が必要 |
| 都留市 | 不良空家等解体事業費補助金 | 60万円 |
・市が不良住宅と認めたもの(特定空家は対象外) ・所有者等に市税等の滞納がないこと ・所有権以外の権利がないこと ・交付決定前の着手は不可 |
| 都留市 | 空家等地域活性化拠点整備事業補助金 | 200万円 |
・除却後の跡地を自治会等に10年以上貸与し、地域活性化拠点として利用すること ・所有権以外の権利がないこと ・交付決定前の着手は不可 |
| 山梨市 | 山梨市空き家解体工事補助金 | 20万円 |
・空き家バンク登録物件で売買契約が成立していること ・解体費用が100万円以上 ・所有者・購入者に市税滞納がないこと ・市内業者の利用、事前申請が必要 |
| 中央市 | 中央市空き家バンク物件解体工事補助金 | 100万円 |
・対象者:空き家バンク経由の購入者(3親等以内の親族間取引は除く) ・解体後1年以内に居住用住宅を新築すること ・解体費用が100万円以上 ・事前申請が必要 |
| 大月市 | 大月市空き家解体に伴う跡地利活用事業補助金 | 50万円 |
・延床面積75㎡以上 ・解体後1年以内に跡地を売却・賃貸し、相手方が1年以内に住宅建設に着工すること(2親等以内の親族間取引は除く) ・解体費用が50万円以上 ・市内業者の利用 |
| 笛吹市 | 笛吹市空家等解体費補助金 | 20万円 |
・昭和56年5月31日以前建築で危険性のある空き家 ・所有者等に市税滞納がないこと ・建替え目的でないこと ・市内業者の利用、事前申請が必要 |
| 甲州市 | 甲州市空き家情報バンク登録促進事業補助金 | 100万円 |
・対象者:空き家バンク登録物件の所有者で、売却が解体の条件であること ・市内解体業者の利用 ・市税の滞納がないこと |
| 小菅村 | 小菅村空き家解体撤去補助事業 | 50万円 |
・1年以上使用されていない危険な老朽空き家 ・所有者等に村税滞納がないこと ・貸借権等が設定されていないこと |
多くの制度では「事前申請」が必須であり、解体後に申請しても補助を受けられないことがあります。
事前の情報収集と手続き準備を徹底しましょう。
空き家の取得に関する補助金
山梨県では、空き家を購入して移住や定住を目指す方を対象に、住宅取得にかかる費用の一部を支援する補助制度が用意されています。
対象となるのは、主に若年層や子育て世帯、三世代同居を希望する家庭などで、地域への長期的な定住や人口減少対策の一環として活用が進められています。
補助の上限額や対象年齢、定住期間の条件などは自治体ごとに異なるため、検討の際は各市町村の要綱をよく確認することが大切です。
以下に、主な制度を紹介します。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 身延町 | 移住・定住祝金 | 20万円※18歳未満の子1人につき20万円加算(上限100万円) | ・町の空き家・土地バンクを利用して中古物件を購入した移住者 |
| 大月市 | 定住促進中古住宅取得助成金制度 | 最大20万円 |
・市内で中古住宅を取得した者 ・相続や贈与による取得ではないこと ・別荘や営利目的でないこと ・世帯全員の市税等に滞納がないこと |
| 道志村 | 土地、中古住宅購入補助 | 100万円 |
・対象者:35歳以下の者、45歳以下の夫婦、中学生以下の子がいる50歳以下の世帯のいずれか ・事業費が50万円以上であること |
| 鳴沢村 | 三世代同居等支援事業補助金 | 最大80万円 |
・三世代での同居・近居のために中古住宅を取得すること ・中学生以下の子がいること ・子世帯が村外から転入し、1年以内に同居・近居を開始すること ・3年以上の同居・近居を継続する意思があること ・世帯全員の村税等に滞納がないこと |
これらの補助金は、地方移住を検討している方や、空き家を取得して定住したいと考えている方にとって、費用負担を減らしながら新生活をスタートできる貴重な支援制度です。
空き家購入と合わせてリフォーム補助や家財整理補助が併用できる場合もあるため、セットでの確認がおすすめです。
空き家の家財処理に関する補助金
空き家の活用や売却を進める際、意外と大きな障壁となるのが室内に残された家具や生活用品の処分です。
長年使われていなかった空き家には、家財、日用品などがそのまま残されているケースも多く、処分には数万円から数十万円の費用がかかります。
こうした負担を軽減するため、山梨県内の複数の自治体では、家財の撤去や清掃に対して補助金を交付しています。リフォーム補助と一体となっている制度もあり、空き家バンク登録を条件とする場合もあります。
以下に、代表的な制度を紹介します。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 南アルプス市 | 空き家活用定住促進事業補助金(空き家片付け事業) | 10万円 |
・5年以上の定住または空き家バンクへの登録 ・3親等以内の親族間取引でないこと ・産業廃棄物処理費は対象外 |
| 北杜市 | 北杜市空き家バンク活用促進リフォーム費等補助金(家財処分事業) | 100万円(リフォームと合算) |
・5年間の定住・登録義務 ・3親等以内の親族間取引でないこと ・市が許可した業者の利用 ・倉庫・納屋は対象外 |
| 南部町 | 南部町空き家バンク利用促進事業補助金 | 10万円 |
・対象者:空き家バンク登録物件の売買・賃貸契約者(予定者含む) ・町税の滞納がないこと ・許可された業者の利用 ・事業総額が1万円以上であること |
| 甲州市 | 甲州市空き家情報バンク登録促進事業補助金(清掃等事業) | 20万円 |
・対象者:空き家バンク登録物件の所有者 ・市税の滞納がないこと ・許可された業者の利用 ・事業総額が5万円以上であること |
| 上野原市 | 空き家・空き店舗バンクリフォーム補助事業(残置物処分) | 10万円 |
・対象者:空き家バンクを利用した賃貸借物件の所有者・借用者 ・市税の滞納がないこと ・許可された業者の利用 ・事業総額が5万円以上であること |
| 小菅村 | 小菅村空き家改修等補助事業 | 10万円 | ・5年以上の貸出意思があること※空き家改修等補助事業の一部として適用 |
| 笛吹市 | 笛吹市空き家バンク登録物件に係る改修等補助金 | 20万円(改修と合算) |
・対象者:移住者で5年以上の居住予定があること ・廃棄物処理業者の利用※改修等補助金の一部として適用 |
撤去費用が高額になると、補助金だけでは足りず、自己負担が大きくなります。
事前に制度活用の可能性を確認し、対象となる業者や条件を満たす形で進めることが重要です。
その他の補助金
空き家対策に関する補助制度は、リフォームや解体、取得といった大規模な工事に限らず、空き家バンクの登録や成約、登記費用など、空き家の流通を促進するための支援も用意されています。
金額はそれほど大きくありませんが、「空き家を動かす」ための第一歩として役立つ制度です。
以下に代表的な例を紹介します。
| 市町村名 | 補助金制度名 | 補助上限額 | 主な条件 |
|---|---|---|---|
| 韮崎市 | 韮崎市空き家バンク活用支援事業補助金(登録者支援事業) | 最大10万円 |
・対象経費:空き家バンク登録時の登記手数料・委託料(5万円以上) ・補助金交付後、2年以内にバンク登録の取消や物件の解体をしないこと |
| 韮崎市 | 韮崎市空き家バンク活用支援事業補助金(成約者支援事業) | 最大10万円 |
・対象経費:バンク経由の仲介手数料や引越し費用(5万円以上) ・利用者は所有者の3親等以内の親族でないこと ・市税等の滞納がないこと ・補助金交付後、2年以内の転居・転出は不可 |
| 富士河口湖町 | 空き家バンク成約奨励金 | 10万円 |
・対象者:物件所有者 ・町外在住者(要転入)との賃貸借契約が成立すること ・契約相手が3親等以内の親族でないこと |
| 道志村 | 空き家バンク登録促進報奨金 | 3万円 |
・対象者:物件所有者 ・売買または賃貸契約が成約すること ・村税等に滞納がないこと |
| 甲斐市・笛吹市 | 【フラット35】地域連携型 | 当初5年間、借入金利を年0.5%引下げ | ・市の特定の補助金(空き家バンクリフォーム補助金等)の交付を受けること |
これらの制度は、空き家の利活用や売却の「きっかけづくり」として有効です。
補助金額は小規模でも、うまく組み合わせれば実質負担を大幅に軽減できるケースもあります。
補助金を受けるための流れと注意点
空き家に関する補助金制度を活用するには、各自治体が定める申請手順や提出書類の要件を正確に把握し、漏れなく対応することが重要です。
せっかく制度を見つけても、条件に合わなかったり、書類の不備があると、補助金を受け取れない場合があります。
ここでは、一般的な補助金の申請手順と、注意すべきポイントを整理します。
申請に必要な主な書類
補助金の申請にあたっては、以下のような書類が必要になるケースが多く見られます。
※詳細は各自治体のホームページや担当窓口でご確認ください。
- 補助金交付申請書(指定の様式あり)
- 事業計画書や見積書(工事・解体・家財処分などの内容)
- 位置図・配置図・建物写真(対象となる空き家の状況が分かる資料)
- 税の納付状況を確認できる書類(市町村税の滞納がない証明書)
- 空き家バンク登録証や登録申請書の写し(登録を要件とする制度の場合)
- 身分証や住民票、住民基本台帳に関する書類(定住を条件とする制度の場合)
- 誓約書や同意書(交付条件・遵守事項に関する同意を示す書類)
また、工事完了後には実績報告書や領収書の写しなどが必要となることが多く、申請から実績報告まで複数回の書類提出が求められます。
申請する上での注意点や落とし穴
補助金をスムーズに受け取るためには、以下の点に特に注意が必要です。
・工事や契約を始める前に申請が必要:
→ほとんどの自治体では、交付決定前に着工すると補助対象外になります。
・補助対象となる費用に制限がある:
→家具の購入や外構のみの工事など、一部の費用は対象外です。自治体の要綱を確認しましょう。
・申請から完了までの期間に期限がある:
→年度末までに工事を完了し報告することが条件になっている場合もあります。
・市税や町税の滞納があると申請できない:
→多くの制度で「税金の滞納がないこと」が条件とされています。
・定住や用途指定などの義務がある場合も:
→「5年以上の定住」や「跡地の活用」など、補助金交付後も義務が続くケースがあります。
制度の細かいルールやスケジュールは自治体ごとに異なるため、事前に必ず公式サイトや窓口で最新情報を確認しておきましょう。
補助金以外で空き家問題を解決する方法
空き家の改修や解体に役立つ補助金制度ですが、すべてのケースに対応できるわけではありません。
制度の条件に合わなかったり、補助額では費用をカバーしきれなかったりと、活用が難しいケースもあります。
また、補助金を使うことで改修・解体が可能になったとしても、空き家自体に活用の予定がない、管理の負担が重いといった理由で、結局放置されることもあります。
空き家をそのまま放置していると、固定資産税がかかり続けるうえ、老朽化による倒壊リスクや近隣住民への迷惑など、さまざまなトラブルの原因になります。
補助金の利用が難しいと感じたときは、補助金以外の選択肢から問題の解決を図ることも検討してみましょう。
補助金だけでは難しいケースがある
補助金制度には、自治体ごとにさまざまな要件や制限があります。
たとえば、工事を着工する前に申請しなければならない、補助対象となる経費が限定されている、空き家バンクへの登録が前提となっているといった条件が一般的です。
また、実際に補助金を活用しようと考えても、補助金を使っても費用が不足してしまうケースや、申請手続きが煩雑で途中で断念してしまうといった声もあります。
そもそも空き家を今後活用する予定がないため、改修や解体にお金をかけたくないという理由で、制度の利用を見送る方も少なくありません。
さらに、交付までに時間がかかる、交付額が上限に満たないため自己負担が大きくなる、物件の状態や立地によっては対象外になるなど、補助金には限界もあります。
こうした事情から、「補助金を使いたかったけれど条件に合わなかった」「自己負担を減らすには限界がある」と感じる方にとっては、売却や貸し出し、地域制度を活用した利活用など、別の選択肢を検討することも現実的な対応策です。
空き家を売却する
空き家を処分するうえで、もっともシンプルで確実性が高いのが「売却」です。
とくに今後住む予定がなかったり、管理や維持費の負担を軽減したいと考えている場合には、早めに売却することで固定資産税や老朽化リスクから解放されます。
ただし、築年数が古い物件や再建築不可の土地などは、一般的な不動産仲介では買い手が見つかりにくく、売却が難航するケースもあります。
そういった空き家でも、空き家買取に特化した専門業者であれば、現状のままでもスムーズに売却できる可能性があります。
空き家パスのような専門サービスを活用すれば、
・築古や訳あり物件でも買取対象
・残置物があってもそのままで査定可能
・現地立ち会い不要で手続きが進められる
・相続登記や名義変更などの手続きもサポートあり
といった特徴があり、遠方の所有者や時間がない方でも安心して売却できます。
関連記事:山梨県で空き家売却に強い買取業者5選!選び方やすぐに買い取ってもらうためのポイントを解説
空き家バンクを活用する
空き家を「貸したい」「売りたい」と考えている場合には、自治体が運営する「空き家バンク」の活用も有効な手段です。
空き家バンクは、地域への移住希望者や定住促進を目的としたマッチング制度で、登録することで次のようなメリットがあります。
・移住希望者や地元の購入希望者に物件情報が届きやすい
・自治体がリフォームや片付けの補助制度と連携している場合が多い
・自治体による現地調査や広報支援が受けられることもある
とくに地域によっては、空き家バンク登録物件を対象としたリフォーム補助や解体補助などが用意されているため、制度の利用とセットで進めやすい点が特長です。
ただし、次のような注意点もあります。
・成約までに時間がかかる場合がある
・価格交渉や条件調整に手間がかかることもある
・登録後も定期的な清掃や管理が必要になることがある
早期に処分したい方や、物件の管理に手が回らない方にとっては、空き家バンクが不向きなケースもあるため、自分の目的に合った活用方法の見極めが大切です。
空き家を活用する
「すぐに売る予定はない」「思い出のある家なので手放したくない」と考えている方には、空き家を活用して収益化する方法もあります。
具体的には、次のような選択肢があります。
・賃貸住宅として貸し出す:
→リフォーム後に長期賃貸やシェアハウスとして運用。安定収入を得られる可能性がある
・民泊や簡易宿所として活用する:
→観光地や地方であれば、インバウンド需要に応じた短期貸しができる場合も
・店舗や事務所、教室として貸し出す:
→カフェ、雑貨店、コワーキングスペースなどの用途で活用される事例も多い
・倉庫やトランクルームとして活用する:
→修繕費を抑えつつ、資産として維持しやすい活用方法のひとつ
空き家の状態や立地によって適した活用法は異なりますが、「売却ではなく、しばらく保有しながら活用したい」と考えている方には有効な選択肢です。
ただし、活用には初期費用や管理の手間もかかるため、コストに見合うかの冷静な判断が大切です。
よくある質問
空き家の管理や処分に関しては、補助金の活用を含めて多くの方が悩みや疑問を抱えています。
ここでは、特によく寄せられる質問について、分かりやすくお答えします。
Q:補助金と売却、どちらが良いですか?
空き家の状況や今後の予定によって異なります。
リフォームして住む・貸すなどの活用を考えているなら補助金の活用が有効です。一方、今後使う予定がない場合や管理が難しい場合には、売却によって固定資産税や管理の負担から解放されるメリットがあります。
築古や訳あり物件でも空家パスのような買取可能な業者を活用すれば、補助金申請やリフォームを経ずに、空き家の売却と処分をスムーズに進められます。
Q:古い空き家や傷みがある空き家でも補助金は使えますか?
はい、多くの自治体では老朽化した空き家ほど補助金の対象になりやすい傾向にあります。
ただし、「一定の耐震基準を満たしていること」や「住宅として再利用できる状態であること」が条件となっている場合もあります。
一方で、著しく劣化した建物については、「危険空き家」として解体補助の対象となるケースもあります。
空き家の状態によって申請できる制度が異なるため、まずは自治体に相談し、現地調査などを受けて確認することが大切です。
Q:空き家を壊すのにかかるお金は?
木造住宅(30坪程度)であれば、解体費用の目安は約80万〜150万円ほどです。
建物がコンクリート造や鉄骨造の場合、さらに高額になる傾向があります。
また、庭石や井戸、ブロック塀などの撤去が必要な場合は追加費用が発生します。
正確な費用を把握するには、複数の解体業者に見積もりを依頼することが重要です。
Q:空き家を解体すると固定資産税はどうなる?
建物を解体すると、それまで適用されていた「住宅用地の特例」が外れ、翌年度から土地の固定資産税が最大で約6倍に増える場合があります。
また、空き家が老朽化して「特定空家」に指定されると、建物が残っていても特例が解除されるケースもあります。
税金面だけで解体をためらうよりも、将来的な管理リスクや売却のしやすさを総合的に判断して進めることが大切です。
固定資産税の詳細は、各市町村の税務課で個別に確認するのが安心です。
まとめ
山梨県では、空き家のリフォームや解体、取得、家財整理などに活用できる補助金制度が複数整備されています。制度を活用すれば、費用負担を抑えて空き家の利活用や処分を進められます。
ただし、補助金には対象条件や上限額があり、すべてのケースに対応できるとは限りません。
対象外だった場合や、手続きが複雑で進めにくいと感じたときには、売却や空き家バンクの利用、収益化といった別の選択肢を検討することも現実的です。
補助金と売却の両面から状況に合った方法を判断すれば、空き家問題をよりスムーズに解決できます。
「補助金の申請が難しかった」「売却を検討しているけど手続きが不安」「遠方にある空き家をどうにかしたい」そんなお悩みがある方は、ぜひ空き家パスにご相談ください。
空き家パスでは、山梨県を含む全国の空き家に対応し、築古物件や訳あり物件でも無料で査定・ご相談を承っています。専門スタッフが状況に合わせた解決策をご提案しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


この記事の監修者 高祖広季
株式会社ウィントランス 代表取締役 高祖広季
空き家パスを運営している株式会社ウィントランスの代表です。日本の空き家問題を解決するため空き家専門の不動産事業を展開中。「空き家パス」と「空家ベース」というサービスを運営しています。これまで500件以上の不動産の売買取引に携わってきました。空き家でお困りの方の力になりたいと思っています。