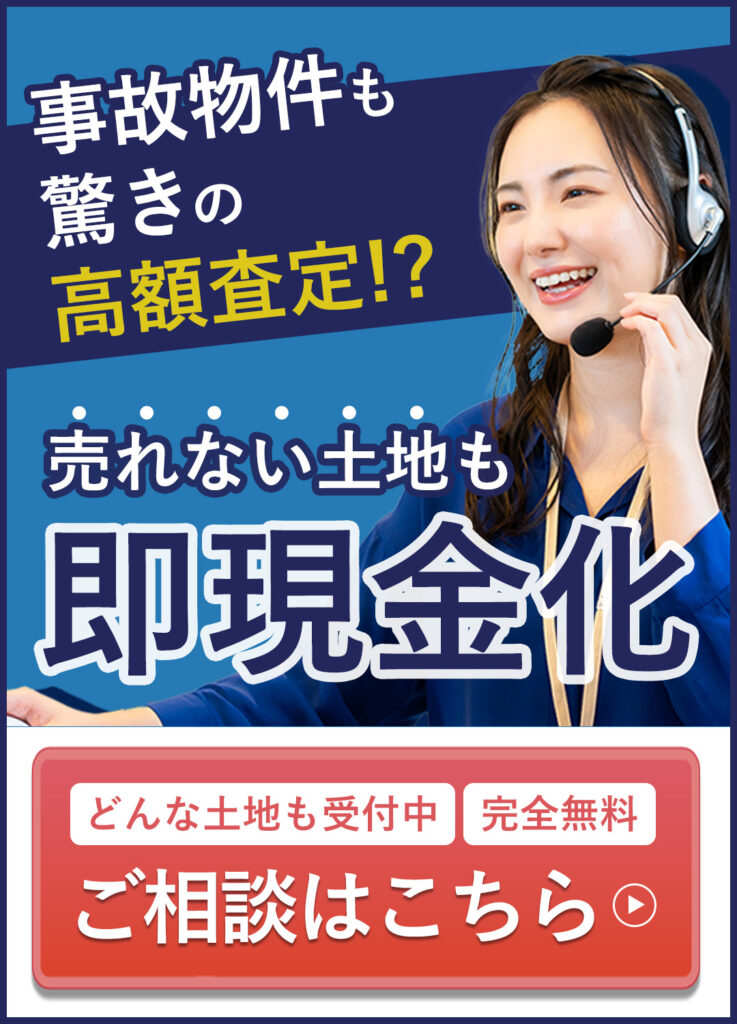住んでいない家を売却するときに知っておきたい税金と特例
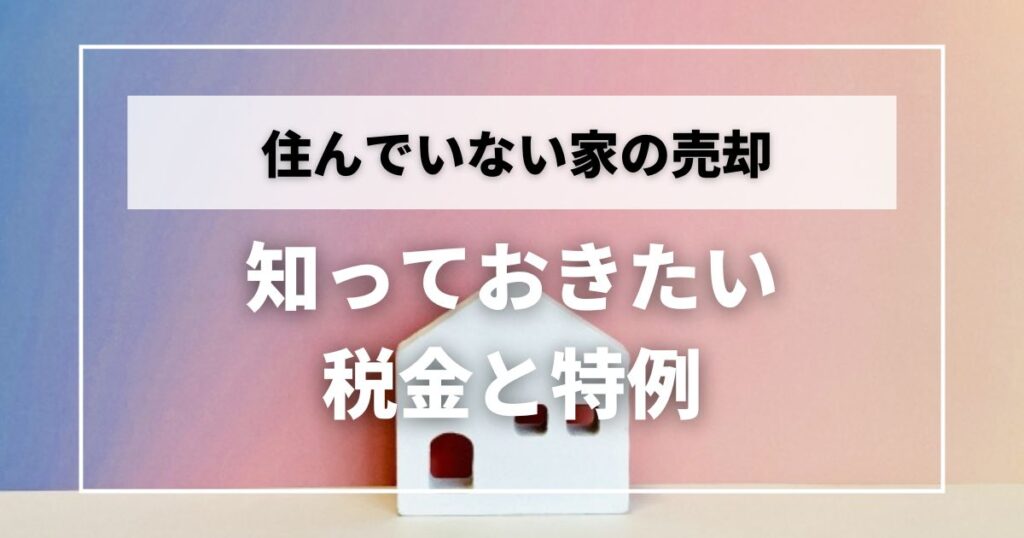
相続した実家が空き家のままになっている方、親が施設に入所して自宅が使われなくなった方、あるいは使っていないセカンドハウスの管理にお困りの方。こうした「住んでいない家」をどうすれば良いのか、お悩みではありませんか?
空き家を売却する際には、譲渡所得税などの税金がかかります。ただし、条件を満たせば税負担を軽くできる特例も存在します。
また、空き家をそのまま放置しておくと、固定資産税などの維持費がかかり続けるだけでなく、「特定空家」に指定されるリスクも出てきます。
本記事では、空き家の売却に関わる主な税金や控除制度、所有状況に応じた特例の使い方、さらに売却方法の選び方まで、分かりやすく解説します。
- 住んでいない家を売却する際にかかる主な税金と計算方法
- 相続や親名義の空き家に使える特例・控除の条件
- セカンドハウスなど非居住用物件の税金の扱い
- 空き家の維持にかかる費用と放置リスク
- 仲介・買取・更地売却・空き家バンクなど売却方法の違い
相続した実家が空き家になる、売却したいがなかなか売れない、などお悩みの方は、まずは空き家パスへご相談ください。空き家パスは、築年数の経った古い空き家や、相続など権利関係が複雑な不動産の買取を得意としています。全国の物件の買取りが可能で、ご相談や査定は完全無料です。
目次
住んでいない家の売却にかかる主な税金は?
空き家を売却する際には、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税に加え、印紙税や登録免許税なども発生します。税金の種類と金額を把握しておくことで、実際に手元に残る金額を事前に正確に見積もれます。
譲渡所得税・住民税・復興特別所得税
譲渡所得税などの課税対象となる譲渡所得は、不動産の売却価格から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いた金額です。
取得費には物件の購入代金や購入時の仲介手数料、登録免許税などが含まれます。譲渡費用には売却時の仲介手数料や測量費などが含まれます。
譲渡所得には、所得税に加えて住民税と復興特別所得税も課税されます。確定申告によって税額が決まり、所得税と復興特別所得税は申告期限までに税務署へ納付します。住民税については、確定申告の内容をもとに自治体が課税額を算定し、6月ごろに送付される納付書に記載された内容に沿って、住民税を納付します。
【所有期間による譲渡所得税率の比較】
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|
| 5年以下(短期譲渡所得) | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 5年超(長期譲渡所得) | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
例えば、3,000万円で購入した住宅を4,000万円で売却し、譲渡費用が200万円かかった場合、譲渡所得は800万円となります。所有期間が10年なら、税金は約162.5万円(800万円×20.315%)になります。
印紙税・登録免許税などその他の費用
住んでいない家を売却する際には、譲渡所得税以外にもさまざまな費用がかかります。まず不動産売買契約書には印紙税が必要で、売買価格に応じて金額が決まります。たとえば、売買価格が1,000万円超5,000万円以下であれば1万円、5,000万円超1億円以下であれば3万円です。
また、所有権移転登記にかかる登録免許税は、建物の場合は固定資産税評価額の2%、土地は1.5%が基本です。その他売却に伴って測量費や不用品の処分費が発生することもあります。
さらに、司法書士報酬や不動産会社への仲介手数料も必要です。仲介手数料は「売買価格の3%+6万円」に消費税を加えた金額で、4,000万円の物件であれば最大約132万円(税込)です。
こうした費用は売却価格から差し引かれるため、事前に総額を把握しておくことで、最終的な手取り額を正確に見積もれます。
親から相続した空き家を売却するときに使える控除・特例
相続した空き家を売却する場合、税金の負担を軽くできる特例制度があります。なかでも「被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除」と「取得費加算の特例」は、大きな節税につながる制度です。ただし、どちらも適用には細かな条件があるため、事前に内容をしっかり確認しておく必要があります。
空き家の3000万円特別控除
親から相続した空き家を売った場合、一定の条件を満たせば「3,000万円の特別控除」が使えます。これは、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける制度で、税負担を大幅に軽くできるため、必ず確認しておきたい特例です。
特別控除の制度が使えるのは、以下のような場合です。
- 被相続人が亡くなる直前まで住んでいた家だった
- 他に住んでいた人がいなかった
- 建物が旧耐震基準(昭和56年5月31日以前建築)である
- 相続後3年以内に売却する
- 売却価格が1億円以下
旧耐震基準の建物は、耐震リフォームをするか取り壊して更地にすることで適用されます。
たとえば、取得費1,000万円の空き家を5,000万円で売り、譲渡費用が200万円かかった場合、本来の譲渡所得は3,800万円です。しかし特例を使えば、課税対象が800万円となり、納税額が大きく抑えられます。
参考:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
取得費加算の特例
相続した空き家を売却する際に活用できるもう一つの制度が「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(取得費加算の特例)です。相続税のうち、譲渡した不動産に対応する金額を取得費に加えることができ、結果として譲渡所得を圧縮できます。
相続した不動産は、被相続人が取得した時の価格が取得費となりますが、古い物件の場合は取得費が不明または低額であることが多く、結果として譲渡所得が高額になりがちです。取得費加算の特例を使うと、相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得を減らせます。
適用条件は以下の通りです。
- 相続または遺贈により財産を取得した人であること
- 相続開始の日の翌日から3年10ヶ月以内に譲渡すること
- 相続税申告書に記載された土地等や建物であること
取得費加算の特例は「空き家の3,000万円特別控除」と併用が可能で、特に取得費が不明な古い物件や、相続税の支払いが高額だった場合に効果的です。
参考サイト:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁
存命の親が住んでいない家を売却するときに使える控除・特例
親が高齢者施設に入所していたり、別の住まいに移って自宅が空き家になっている不動産を売却するときに利用できる特例があります。
そうしたケースで税金の負担を軽くできる2つの制度、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」と「10年超所有の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」について詳しく解説します。
条件を満たせば大きな節税につながるため、事前の内容確認が大切です。
3000万円特別控除
親が健在で、親名義の空き家となった実家を売却する場合、条件を満たせば「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」という特例を利用できます。この特例により、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けるため、大きな節税につながります。
特例を受けるには、次のような条件を満たしている必要があります。
- 売主がかつて実際にその家に住んでいたこと
- 住まなくなってから3年目の12月31日までに売却すること
- 親族や配偶者などが住み続けていないこと
- 売却価格が1億円以下であること
たとえば、親が介護施設に入所して空き家になった実家を、3年以内に売却するケースでは、この特例が適用できる可能性があります。
なお、「住まなくなった日」の判断には注意が必要です。たとえば一時的な入院などは対象になりませんが、住民票を移していたり、家財道具をすべて搬出していた場合には、居住実態がなくなったと判断されるケースがあります。
適用には確定申告が必要で、住民票の除票や、家財の撤去を証明できる資料など、事前に準備しておくと安心です。
参考サイト:No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁
10年超所有で活用できる軽減税率の特例
住んでいない家の所有期間が10年を超える場合には、「10年超所有の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」が活用できます。この特例では、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分について、通常よりも低い税率が適用されます。
長期譲渡所得の通常の税率は約20.315%ですが、軽減税率を使えば6,000万円以下の部分に対しては約14.21%に引き下げられます。
適用のためには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 売主が住宅を10年以上所有していること
- 住まなくなってから3年目の12月31日までに売却すること
- 売主の配偶者や親族などがその住宅を引き続き使用していないこと
- 住まなくなってから3年目の12月31日までに売却すること
軽減税率の特例は、「3,000万円特別控除」との併用も可能です。たとえば、親が15年間所有していた自宅の譲渡所得が5,700万円だった場合、通常であれば税額は約1,158万円になりますが、軽減税率を適用すれば約810万円に抑えられます。さらに3,000万円特別控除を併用すれば、税額は一段と少なくなります。
セカンドハウス・別荘の売却時にかかる税金
セカンドハウスや別荘などの売却では、主たる居住用財産とは税金の取扱いが異なります。基本的にセカンドハウスや別荘は「居住用財産」とは見なされず、3,000万円特別控除や軽減税率の特例が適用できない場合が多いです。ただし、一定の条件を満たす場合は居住用財産として扱われることもあります。
居住用財産と見なされない場合の扱い
セカンドハウスや別荘は、原則として「非居住用財産」として扱われます。非居住用財産の売却に対する税率は所有期間によって計算されます。
例えば、5年前に3,000万円で購入したセカンドハウスを4,500万円で売却し、譲渡費用が200万円かかった場合の譲渡所得は1,300万円です。非居住用財産として扱われると、税金は約264万円(1,300万円×20.315%)になります。
【居住用財産と非居住用財産の判断基準】
| 居住用財産と見なされる可能性がある基準 | 非居住用財産と見なされる可能性が高い基準 |
|---|---|
| 住民票を移して生活の拠点としていた | 週末や休暇時のみの使用で滞在日数が少ない |
| 週の大半をそこで過ごしていた | 賃貸に出していた期間がある |
| 光熱費の使用実績が通常の居住と同等 | 他に明らかな生活の本拠地がある |
| 家財道具や日常生活用品が十分に備えられていた | 事業用途(民泊など)で使用していた |
特例を受けるには、実際に居住していたことを示す証拠が必要になるため、光熱費の領収書や近隣の方からの証明など、生活の実態を裏付けられる資料をあらかじめ保管しておくと安心です。
特例が使えるケースと使えないケース
セカンドハウスや別荘でも、使用実態がある場合には「居住用財産」として扱われ、税制上の特例が適用されるケースがあります。生活の拠点として機能していた事実が証明できれば、3,000万円特別控除や軽減税率の特例を受けられる可能性があります。
- かつて住んでいたが、転勤や介護などの事情で別の場所へ移った場合
- 一時的に親族が生活しており、生活の拠点として使われていた実績がある場合
- 売却直前に一定期間住んでおり、居住実態を証明できる場合
- 毎月1日以上の頻度で居住し、生活拠点の一部として継続的に使用していた場合
これらの状況では、光熱費の使用履歴や住民票の記録、生活用品の設置状況、近隣住民からの証言などを用いて、居住実態を示す証拠が必要になります。
一方で、以下のようなケースでは特例の適用は難しくなります。
- 週末や休暇時のみの利用で、生活拠点としての実態がない場合
- 賃貸物件として長期間貸し出していた場合
- 主に民泊や事業目的で使用していた場合
- 居住実態を裏付ける資料が一切ない場合
税制上の判断は、表面的な使用目的ではなく、実際の生活実態によって左右されます。特例の適用を希望する場合は、あらかじめ生活の記録や証拠資料を整えておき、必要に応じて税理士など専門家へ相談することをおすすめします。
住んでいない家を放置するリスクと維持コスト
住んでいない家を売却せずに放置すると、固定資産税やメンテナンス費用などの継続的なコストがかかるだけではなく、適切な管理を怠ると特定空家に指定されるリスクもあり、税負担が大幅に増加する可能性があります。さらに防犯面での課題もあるため、長期間の放置は様々なリスクを伴います。
固定資産税・都市計画税と特定空家のリスク
住んでいない家を所有していると、毎年、固定資産税と都市計画税がかかります。固定資産税の標準税率は1.4%、都市計画税は最大0.3%です。住宅が建っている土地には軽減措置(住宅用地の特例)があり、課税額が大幅に抑えられます。
たとえば、小規模住宅用地(200㎡以下)では、固定資産税は1/6、都市計画税は1/3に軽減されます。ただし、空き家を放置して管理が行き届かなくなると、「特定空家等」に指定され、税金が最大6倍に増える可能性があります。
特定空家の主な判断基準は、倒壊の危険性や衛生・景観の悪化、近隣への悪影響などです。改善指導に応じない場合は、最終的に行政による強制解体や解体費用の請求を受けることもあります。
空き家を長期間放置せず、適切に管理することが、余計な税負担やトラブルを防ぐ鍵となります。
管理不全空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?法改正の内容と対策を解説
参考:特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)
メンテナンス費用・防犯面の課題
住んでいない家を維持するには、定期的な管理が必要です。たとえば、水回りや屋根・外壁の点検を怠ると、劣化が進んで修繕費が高額になるケースがあります。草刈りや庭木の手入れも必要で、年間数万円の費用がかかるケースも少なくありません。
さらに、空き家は不法侵入や放火などの犯罪被害を受けやすい傾向にあります。総務省の調査では、全国の放火火災の約12%が空き家で発生しています。防犯カメラや見回りサービスの導入など、安全対策の初期費用・維持費も検討が必要です。
加えて、地震や台風などの自然災害で空き家が損傷し、近隣に被害を与えた場合、所有者が損害賠償責任を問われるおそれがあります。
管理費用、リスク対策を総合すると、住んでいない家を適切に維持するためには、年間で20万円〜50万円程度の支出が発生することがあるため、放置せず、売却や活用を含めて早めの対応が重要です。
空き家の維持で年間約35万円かかる?意外と知らない維持費の内訳とリスクを解説
住んでいない家の売却方法と進め方
住んでいない家を売却する方法には、仲介、買取、更地にしての売却、空き家バンクの活用など複数の選択肢があります。物件の状態や売主の状況によって最適な方法は異なるため、各方法のメリット・デメリットを理解した上で自身に合った方法を選択をしましょう。
仲介を利用する場合のメリット・デメリット
仲介では、不動産会社が広告活動や買主との交渉を行い、広く市場に情報を出すことで市場価格に近い金額での売却が期待できます。
ただし、売却までに時間がかかるほか、内覧対応の準備や仲介手数料の支払いといった負担もあります。以下に、仲介のメリットとデメリットを比較してまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット |
・買取より高く売却できる可能性がある ・広告や内覧対応を不動産会社が代行 ・レインズ登録で広く買主を探せる |
| デメリット |
・売却までに時間がかかる(平均3〜6ヶ月) ・仲介手数料(売却価格の3%+6万円+税)が発生 ・内覧対応のために清掃や整理が必要 |
仲介による売却は、物件の状態が比較的良く、売却を急いでいないケースに向いています。少しでも高く売りたい場合や、買主の選択肢を広げたい方に適した方法といえるでしょう。
買取を利用するメリット・デメリット
買取とは、不動産会社が物件を直接買い取る売却方法です。仲介と比べて売却までの期間が短く、手続きもシンプルで済むのが特徴です。
特に、早く現金化したい場合や、遠方の空き家・老朽化した物件の処分を検討している方にとって、有力な選択肢となります。ただし、価格面では仲介より低くなる傾向があるため、事前に比較検討が欠かせません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット |
・売却までが早い(最短で数日〜2週間) ・確実に売却できる ・老朽化や状態の悪い物件でも対象 ・内覧対応・価格交渉の手間が不要 ・仲介手数料がかからない |
| デメリット |
・仲介より売却価格が低くなる傾向(市場価格の7〜8割) ・業者によって査定額に差が出やすい |
買取は、「手間なく早く売りたい」「現地に行かずに手放したい」といったニーズに適しています。査定額は業者ごとに差が出るため、複数の不動産会社に見積もりを依頼し、各社の条件の比較が大切です。
更地にして売却する際の注意点
住んでいない家を更地にして売却する方法もあります。古い建物の場合、更地にした方が高く売れる可能性があります。
更地にして売却する場合の注意点としては、解体費用を考慮する必要があります。一般的な木造住宅の解体費用は坪あたり3〜5万円程度で、30坪の住宅なら90〜150万円程度かかります。
また、住宅用地の特例が適用されなくなる点も重要です。建物がある状態では固定資産税が1/6〜1/3に軽減されていましたが、更地にすると特例が適用されなくなり、税負担が増加します。売却までの期間が長期化すると税負担が大きくなるため注意が必要です。
更地にして売却を検討する際は、更地にした場合と建物付きの場合の査定額の差額、解体費用、固定資産税の増額分、売却までの想定期間などを総合的に判断することが大切です。
空き家バンクや自治体制度の活用
空き家の売却方法として、空き家バンクや自治体の支援制度を活用する手段もあります。空き家バンクは自治体が運営するマッチング制度で、費用を抑えながら売却できる点が特長です。
地方移住を希望する層や、二地域居住を考える人へのアプローチにもつながります。 また、自治体によっては、購入者へのリフォーム補助金、空き家の解体費用支援、固定資産税の軽減などが受けられる場合もあります。
ただし、売却までに時間がかかることが多く、対象が地方物件に限られることもあります。 活用を検討する際は、物件所在地の自治体ホームページを確認し、空き家対策担当窓口に問い合わせるのが確実です。
参考:建設産業・不動産業:空き家・空き地バンク総合情報ページ – 国土交通省
まとめ
住んでいない家を売却する際には、譲渡所得税をはじめとした税金や、それぞれの状況に応じた特例の有無が大きく関わってきます。相続した空き家や、親が住まなくなった家、自分名義のセカンドハウスなど、所有の経緯によって適用できる制度や負担額が異なるため、事前の確認が欠かせません。
また、空き家を放置すれば維持費がかさむだけでなく、特定空家に指定されるリスクや近隣トラブルの原因になる可能性もあります。売却方法も仲介や買取、更地売却、空き家バンクの活用など複数あるため、目的や状況に合った選択が重要です。
相続した実家や住んでいない不動産の処分でお悩みの方は、空き家パスへご相談ください。空き家パスは全国の空き家の買取を行っており、相続などで権利関係が複雑な物件や築年数が古い物件も、現状のままでの買取が可能です。ご相談・査定は無料ですので、住んでいない家の売却でお困りの方は、ぜひお問い合わせください。