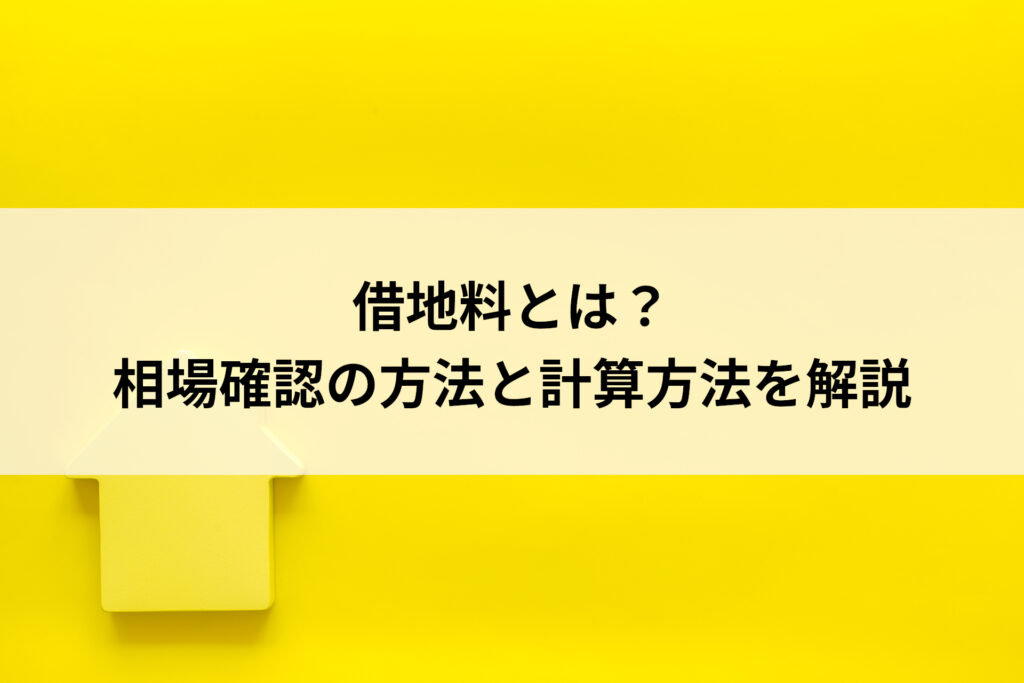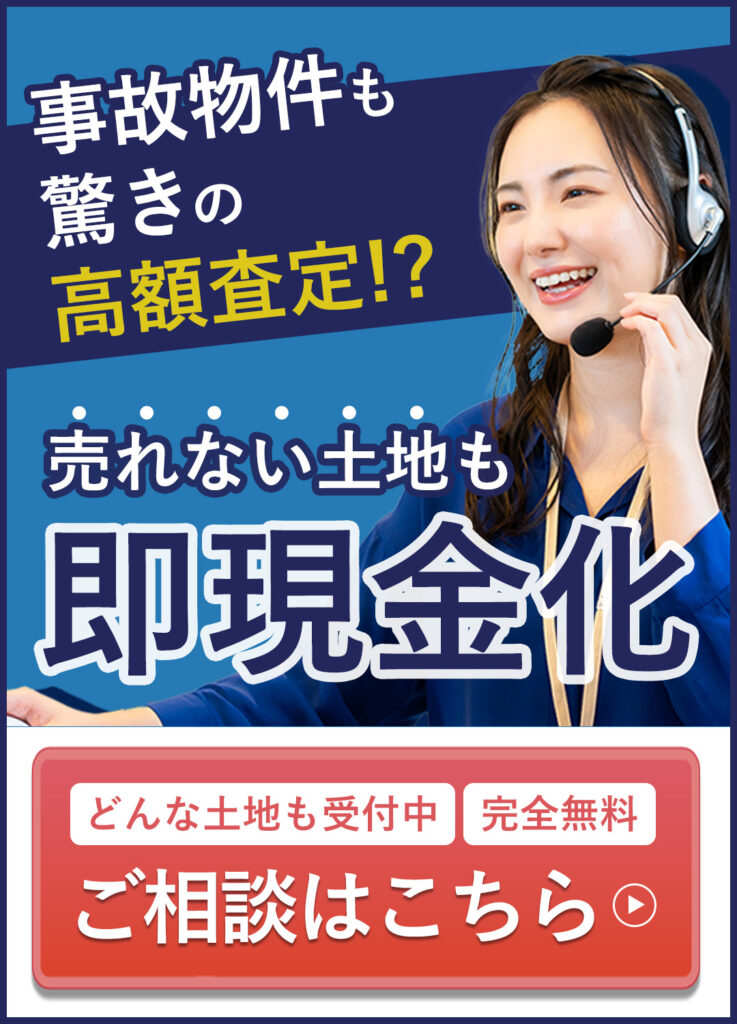借地の地代相場はいくら?借地料の計算方法、地代を得るメリットや税金についても解説
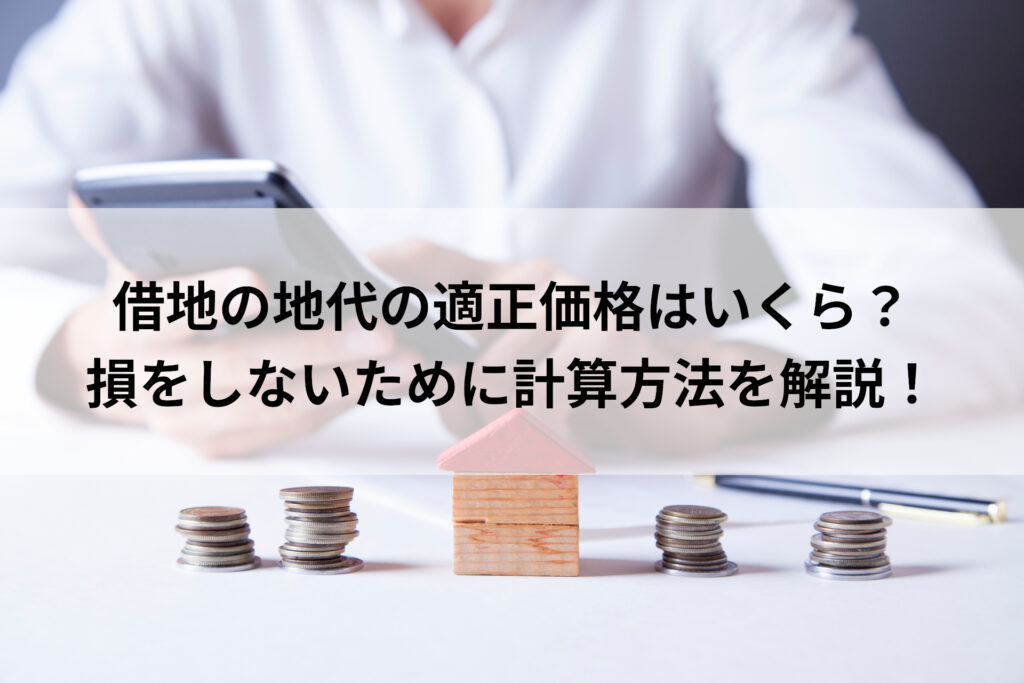
借地権付き建物をこれから所有する予定の方はもちろん、すでに所有している方でも地主から請求される借地の地代(借地料)の計算方法を理解している方は少ないのではないでしょうか?
しかし、借地の地代の計算方法をしっかりと把握していないと、知らぬ間に相場から大きく外れた高額を請求されていたということも起こりえます。
そこで、この記事では借地権者(借地人)の皆さまが損をしないよう、借地の地代の計算方法などについて解説していきます。ぜひご一読ください。
土地を貸したいと考えている方は、以下の記事を参考にされてください。
- 借地の地代の種類
- 借地権設定時の地代の計算方法
- 契約継続時の地代の計算方法
目次
そもそも地代(借地権)とは?
地代とは土地を貸すことで得る賃料のことで、地代を得る権利のことを借地権と呼びます。
借地権は一般的に登記することで完全なる権利となり、土地に借地権を設定することで所有権とは別の権利を付与できます。
つまり、借地権は借主と口約束で締結されるものではなくお互いの合意を持って登記される権利ということになります。
また、地代には毎月支払われる賃料以外にも更新料や手付金なども含まれることから、「土地を貸すことで得られる利益の総称」が地代です。
借地権は大きく分けて3種類
借地権にはいくつか種類があり、目的によって使い分けることが多いです。
そこで、それぞれの借地権が持つ特徴を正しく把握し適切な借地権で契約を締結することが重要です。
選択する借地権によっては何十年も自己利用できなくなってしまう可能性もあることから、この章で解説するポイントを事前に押さえておくことをおすすめします。
| 借地権の種類 | 内容 |
|---|---|
| 普通借地権 | ・契約期間が30年の借地権 ・1回目の更新は20年、2回目の更新は10年が最長期間 ・契約に関する書類に決まりはない。 |
| 定期借地権 | ・契約期間が50年の借地権 ・更新はできない。 ・期間満了時までに建物等を解体撤去した上で貸主に返還する必要がある ・契約については公正証書の作成が必要 |
| 建物譲渡特約付定期借地権 | ・定期借地権の1種 ・契約期間は30年が最長 ・契約満了時には残存価値をベースとした金額で建物等を地主に売却できる |
普通借地権
普通借地権とは更新ができる借地権のことで、最低30年を契約期間とする権利です。
この期間は30年よりも短くはできませんが、1回目の更新は20年、2回目は10年と期間が短くなるのが特徴です。
また後述する定期借地権のように必ず当事者間で公正証書を作成しなければならないというルールもなく、契約書の形式は自由です。
そのため、融通が利かない借地権の中でも貸主と借主間で納得のいく契約内容に設定しやすいといえます。
定期借地権
定期借地権は普通借地権とは違って更新ができず、期日満了をもって建物やアスファルト舗装を撤去し貸主に土地を返還しなければなりません。
そのため、定期借地で土地を借り家やオフィスを建てた場合は将来必ず解体することになるため、相続や贈与の予定がある人は注意が必要です。
一方で定期借地権の契約期間は最長50年と普通借地権よりも長く、貸主にとっても不都合が起きやすい契約形態です。
このように定期借地権は貸主と借主の資産に大きな影響を与えることから、後から意見の食い違いによるトラブルが起きないようお互いが合意した内容を公的文書である公正証書に記載が定められています。
建物譲渡特約付定期借地権
建物譲渡特約付定期借地権は定期借地権の1種ですが、契約満了時に建物を貸主に売却するという点に違いがあります。
この借地権は期間が30年となっており建物を解体する必要がないことから、期間を定めた居住や事業を営む人に向いています。
ただし、 建物譲渡特約付定期借地権は契約を締結するタイミングでしか設定できず後から付与できない権利となっているため、注意が必要です。
なお、売却する建物は建築した金額ではなく期間満了時の残存価値によって売却となるため、期間満了時が近くなったタイミングで不動産会社に査定を依頼しておくことがおすすめです。
地代は大きく分けて3種類

借地の地代と一言で言っても、実際には大きく3種類に分けられます。ここでは地代の種類について、一つずつ解説していきましょう。
| 借地権の種類 | |
|---|---|
| 通常の地代 | 土地の価額×(1-借地権割合)×6% |
| 相当の地代 | 土地の価額×6% |
| 実際の地代 | 実際に借地権者が地主に支払っている地代 |
そもそもの借地について知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
定期借地権とは?契約期間やメリット・デメリット、注意点について分かりやすく解説
通常の地代
「通常の地代」とは、借地契約締結時に「権利金」の授受がある場合、地主に支払われるべき地代のことを指します。権利金とは、契約締結時に一括で地主に支払われる一時金のことです。
なお、通常の地代の算出方法は以下の通りになります。
通常の地代=土地の価額×(1-借地権割合)×6%
相当の地代
一方「相当の地代」は、権利金の授受がない契約の場合の地代のことを指します。親族間での借地契約などのケースが該当します。相当の地代は以下の計算式にて算出可能です。
相当の地代=土地の価額×6%
「通常の地代」と異なる点は、権利金の授受がない分、借地権割合を考慮しないので高額になる点です。
実際の地代
「実際の地代」は、実際に借地権者が地主に支払っている地代のことを指します。そのため、借地権者の皆さまに関係があるのは、この地代だと言えるでしょう。この記事でも、これ以降はこの「実際の地代」について解説していきます。
地代相場について種類別に解説
借地権には「定期借地」と「普通借地」、「事業用定期借地」がありますがそれぞれ地代の相場が異なります。
地代は借地契約締結と同時に確定するため、あらかじめ相場を知っておくことで借主と貸主の双方が納得できる内容となります。
そのため、どの借地契約であっても相場の理解は重要です。
| 地代相場 | 内容 |
|---|---|
| 定期借地権の地代相場 | 一般定期借地の場合は事業を目的とした借地ではないケースが多く、地代の相場は土地価格の2〜3%と比較的安い傾向にある。 |
| 普通借地権の地代相場 | 住宅の建築などを目的とした場合に設定される借地権のことで、土地価格の1%前後が相場。 |
| 事業用定期借地権の地代相場 | 事業用定期借地は収益を目的としているため土地価格の6%前後が地代の相場となる。 ただし、相続税路線価を使って計算した場合は土地価格の5%程度まで地代が下がることになる。 |
定期借地権の地代相場
事業用定期借地ではない一般定期借地権の場合、土地価格の2〜3%を地代とするケースが多く比較的安くなります。
この理由として一般定期借地は土地の利用用途が定められておらず、借主が事業を実施していない場合に採用される傾向にあるからです。
収益目的での土地利用ではないため地主が地代を高くすることは難しく、地代を抑えた契約になってしまうことが多いのです。
このように、定期借地の場合は借主の目的が地代に大きく影響することが分かります。
普通借地権の地代相場
普通借地は住宅の建築などを目的とすることが多く、事業用で使用することはほとんどありません。
そのため地代は一般定期借地よりもさらに安くなる傾向にあり、土地価格の1%程度が相場です。
ただし定期借地とは違って地代をまとめて支払う権利金という名目を設定するのが一般的なことから、借主はまとまった資金が必要になるため注意が必要です。
このことからも、毎月の地代と権利金とのバランスを契約前に確認しておくことをおすすめします。
事業用定期借地権の地代相場
事業用定期借地は住宅やマンションなどの居住用建物の建築が目的ではなく、文字通り事業を供することが目的です。
つまり、土地を借りることで大きな収益を得られることになるため地代は他の借地権よりも高くなり、土地価格の6%前後が相場です。
ただし、事業用借地の賃料計算をする上で「相続税路線価」を使用することもあり、相続税路線価は公示価格の80%程度となっています。
この場合は土地価格の5%程度まで地代が下がることになることから、どちらで算出すべきかが地代を決める上で大きなポイントとなります。
借地権設定時の地代相場の計算方法

それでは、借地権者が実際に支払っている「実際の地代」が妥当な額なのかどうかを判定できるように、計算方法を解説していきましょう。
まずは借地権設定時における地代の計算方法です。
固定資産税・都市計画税をもとに地代相場を算出する方法
公租公課(固定資産税+都市計画税)の額から、年間の地代相場を算出することが可能です。具体的には、公租公課の合計額に一定の倍率を乗ずることでおおよその相場が分かります。なお、乗ずる倍率は借地の用途によって異なり、以下の表の通りになります。
| 借地の用途 | (固定資産税額+都市計画税額)に対する倍率 |
|---|---|
| 住宅地 | 3~5倍 |
| 商業地 | 5~8倍 |
また、固定資産税の算出方法は以下の通りです。
固定資産税=課税標準額(固定資産税評価額)×税率(1.4%)
固定資産税の税率は、標準税率で1.4%とされていますが、地域によっては1.5%や1.6%などと異なることもあります。
そして、都市計画税は以下のように算出します。
都市計画税=課税標準額(固定資産税評価額)×税率(~0.3%)
都市計画税の税率は上限0.3%の制限税率となっており、地域によっては0.3%未満のところもあります。
ご自身の地域の税率をしっかり確認して公租公課の合計額を算出し、借地の地代相場を計算してみましょう。
相続税路線価をもとに地代相場を算出する方法
相続税路線価からも地代のおおよその相場を算出することが可能です。
「相続税路線価」とは、相続税額などを決める際の基準となる評価額のことで、国税庁が毎年発表しています。これは国税庁が公開している「路線価図」より確認可能です。
また、相続税路線価は、国土交通省が毎年発表している「公示地価(公示価格)」の80%程度の水準で決められています。つまり相続税路線価から大体の公示地価を求めることが可能で、計算式は以下の通りです。
公示地価(公示価格)=相続税路線価÷0.8
=相続税路線価×1.25
なお、公示地価は1平方メートルあたりの価格です。地代の相場は、この価格に土地面積を乗じた「更地価格」の1.5~3.0%ほどになります。計算式にすると以下の通りです。
地代の相場=公示地価(公示価格)×土地面積(平方メートル)×1.5~3.0%
相続税路線価が分かる場合は、以上のようにして地代の相場を把握しましょう。
期待利回りをもとに地代相場を算出する方法(積算法)
積算法という計算方法では、「期待利回り」をもとに地代を算出できます。この方法は、不動産鑑定士などが地代を算出する際などに使われます。計算式は以下の通りです。
地代=更地価格×期待利回り+必要経費
※更地価格は不動産情報ライブラリ(国土交通省)から調べることができます。
※期待利回りとは、不動産取得に要した資本相当額に対する期待収益の割合のことを指します。また、必要経費は減価償却費や維持管理費、公租公課(固定資産税や都市計画税など)、損害保険料などのことです。
近隣の類似物件をもとに地代相場を算出する方法(賃貸事例比較法)
賃貸事例比較法とは、近隣にある類似物件の地代と比較することで対象の土地の地代を算出する方法です。複数の類似物件の地代の平均を取り、さらにそこに対象の土地特有の個別的要因(土地の形など)を考慮して地代を算出します。
類似物件の定義は、国土交通省の不動産鑑定評価基準を参考にしてください。
こういった算出方法のため、近隣に賃貸物件がない場合にはこの方法は使えないという特徴があります。また、対象の土地特有の個別的要因を正確な数値として考慮することが難しいため、なかなか正確な地代を算出することはできないことにも注意しましょう。
不動産利用による事業収益をもとに地代相場を算出する方法(収益分析法)
事業用の不動産の場合には、対象不動産が生むと期待される事業収益に基づいて地代を算出する収益分析法が使用できます。計算方法は以下になります。
地代=予想収益(年間)+必要経費
必要経費は積算法とほぼ同じで、減価償却費・維持管理費・公租公課(固定資産税や都市計画税など)・損害保険料などです。しかし、収益分析法の場合は減価償却費を必ず考慮しなければいけません。
また、この方法は予想収益の算出が難しいため、あまり使われることはありません。
地代を改定する際の計算方法

前項では、借地権設定時に使われることの多い地代の算出方法を解説しました。地代改定時にもそれらの方法が採用されることはありますが、ここではそれらと異なる改定時に使われることの多い地代算出方法(継続賃料評価)を解説していきます。
現行の地代と適正な新規の地代をもとに算出する方法(差額配分法)
契約継続時に地代を改定する際に用いられる計算方法の一つに、差額配分法があります。
この計算方法では、現行の地代と適正な新規の地代の差額をもとに改定地代を定めます。計算式に表すと以下の通りです。
地代=現行の地代+(適正な新規の地代-現行の地代)×配分率
配分率には、一般的に2分の1や3分の1といった数値が採用されますが、場合によっては別の数値が使われることもあります。この配分率を用いて計算することによって、適正な新規の地代と現行の地代に大きな差があった場合にも、突然地代が大きく変動することなく改定地代を決定できます。
継続賃料利回りをもとに算出する方法(利回り法)
利回り法は、前述の積算法とほぼ同じ考え方の地代算出方法になります。しかし、積算法が借地権設定時に用いられる方法なのに対し、こちらはあくまで地代改定時に使用される算出方法です。
対象不動産の取得に要した資本額に対する期待収益の割合である「継続賃料利回り」に基づいて地代を算出します。計算式は以下の通りです。
地代=現在の更地価格×継続賃料利回り+必要経費
必要経費についても積算法に準ずるので、減価償却費・維持管理費・公租公課(固定資産税や都市計画税など)・損害保険料などを経費として考慮することになります。
物価などの変動をもとに算出する方法(スライド法)
スライド法は、地代を定めた時点からの物価などの変動をもとに新たな地代を算出する方法になります。
地代=(現行の地代-想定される必要経費)×変動率+現在の必要経費
変動率は、物価・土地や建物の価格・所得水準などの変動を総合的に考慮して求められます。そのため、経済情勢などを考慮した地代改定が可能なのが特徴です。
地代を得る3つのメリット
借地権を設定し地代を得るメリットとして「収益化しやすい」「土地管理が不要」「税金対策」という点があります。
地主は土地を貸しているだけで借主がアパートやテナントを建てるため、初期投資がほとんどかかりません。
そのためすぐ収益化でき、さらに固定資産税や都市計画税などの税金以外は維持管理費もかかりません。
また、借主が最適な状態に土地を管理してくれるため、草むしりなどのメンテナンス工数も不要です。
借地権を設定することで、相続税や贈与税を借地権割合に応じて大きく軽減できる点も大きなメリットでしょう。
このように、ただ何もしていない土地を保有しているのであれば借地として公開し、借り手を募集するのがおすすめです。
地代を受け取る際に発生する税金とは
地代には所得税が課せられ、確定申告上の分類は「不動産所得」となります。
不動産所得は年間の収益に対し、固定資産税等の税金や維持管理費などの必要経費を差し引いた額が課税額となり、他の所得と合算して課税されます。
そのため、給与所得など他の所得次第では税金が高くなってしまうこともあり、早めに税理士や税務署に相談することをおすすめします。
また賃料には消費税はかかりませんが、建物を含めた借地契約となっている場合、建物部分には消費税が発生してしまいます。
既存の建物がある土地を借地にする場合はあらかじめ税金計算をとしておき、収益計画が成立するか把握しておきましょう。
地代は定期的な見直しが必要な2つの理由
借地契約は一度締結すると自動的に地代が振込まれることから、地代改定せずに放置している地主も多いです。
しかし地代は定期的な見直しをする必要があり、想定外の損失を防ぐためにも市況や物価変動は注視すべきです。
この章では地代の見直しが必要な理由を解説します。
| 地代の見直しが必要な理由 | |
|---|---|
| 地代相場は上昇したり下落したりするから | 市況や物価変動によって不動産の資産価値が変わり、その結果賃料や地代が変動することはよくある。 |
| 借主が同意すれば借地料の値上げもできるから | 納得できる理由であれば地代の見直しを認めてくれる借主は多い。 |
地代相場は上昇したり下落したりするから
アパートの賃料が上下するように、地代も一定ではなく上下するのが一般的です。
たとえば駅が近くにできたり再開発事業がスタートすると街の価値が一気に上昇し、その結果不動産の資産価値が大幅に上昇することになります。
このような状況になると資産価値の上昇に合わせて賃料なども上昇しますが、地代も例外ではありません。
つまり、市況に合わせての地代見直しは当然すべきことで、借地契約の際にしっかり説明しておけば納得してくれる借主も多いです。
また、地代相場を常に最適な状態に保つことで収益を安定させることができるため、資産運用の観点からも重要です。
このような理由から、相場が変動したタイミングで借主と協議し地代を変更すべきでしょう。
借主が同意すれば借地料の値上げもできるから
「一度決めた地代を上げて欲しいと借主に言いにくい」という地主は多いですが、正当な理由があれば借主が納得してくれる可能性も高いことから、積極的に協議すべきです。
特に周辺の地代相場や物価の高騰は地主にとっても生活に影響することから地代の改定は必須で、正当な理由となります。
現行の地代では収益化が難しくなる前に、借主への相談をおすすめします。
地代相場を知るには不動産鑑定に依頼をするのがベスト
地代相場を計算する方法はいくつかあり、インターネットで調べることも可能です。
しかしベースとなる公示価格や借地権割合を含めた計算は複雑で、正確に計算できる地主は少ないです。
また、一度決定した地代の変更は借主の合意が必要となり、「計算を間違えていた」という理由では納得してくれない可能性が高いです。
このような失敗を避けるためにも不動産鑑定士に依頼し、正しい不動産価値と地代の設定方法のアドバイスをもらうのがおすすめです。
不動産鑑定士とは地域の環境や諸条件を考慮して「不動産の有効利用」を判定し、 「適正な地価」を判断する不動産鑑定のプロです。
不動産鑑定士の土地評価は限りなく正確であるといえ、貸主と借主が納得する地代を設定する上で重要な判断材料になるでしょう。
地代相場についてよくある質問
この章では地代相場に関してよくある質問について、解説します。
| 地代相場についてよくある質問 | 回答 |
|---|---|
| 地代相場の月額の調べ方は? |
・固定資産税・都市計画税をベースに調べる ・相続税路線価をベースに調べる ・期待利回りをベースに調べる ・近隣の借地物件に対する地代をベースに調べる方法 ・アパートやテナントビルの収益を想定し地代を算出する方法 |
| 地代相場の坪単価が上がる理由は? | 市況の変化や物価の上昇による不動産価値の変動 |
| 法定地上権の地代相場は? | 固定資産税の3〜4倍が地代となるケースが多い。 |
| 底地の地代相場は固定資産税の何倍? | 固定資産税の3倍が最低ラインになることが多い |
地代相場の月額について調べ方が知りたいです。
地代相場を調べるには主に5つの方法があり、次のようになります。
- 固定資産税・都市計画税をベースに調べる方法
- 相続税路線価をベースに調べる方法
- 期待利回りをベースに調べる方法
- 近隣の借地物件に対する地代をベースに調べる方法
- アパートやテナントビルの収益を想定し地代を算出する方法
これらの方法はインターネットで計算方法が公開されているため地主自身でも計算可能ですが、計算が複雑な上に解釈を間違えてしまい、その結果不適切な地代で設定してしまうリスクがあります。
万が一地代の設定を間違ってしまうと想定した収益計画通りに進まなくなってしまい、地代を再協議する工数がかかってしまいます。
そのため、地代相場を正しく知りたい場合は不動産鑑定会社への相談がおすすめです。
地代相場の坪単価が上がる理由が知りたいです。
市況の変化や物価の上昇によって不動産の価値が変動することは、地代の坪単価が上がる要因になります。
特に物価は月単位で変動することもあり、生活に大きな影響を与える要素でもあることから細かく地代を見直す地主も多いです。
つまり、経済動向や市況変化が起きると地代の見直しが発生する可能性が高くなります。
このことからも借地契約の時点で「地代を見直す可能性がある」ことを双方合意し、契約書の特約に盛り込んだ上で締結することが重要です。
こうすることで地代の見直しをスムーズに進めることができ、適切な収益計画を維持できるようになります。
法定地上権の地代相場はどれくらいか知りたいです。
法定地上権とは契約や差し押さえなどの理由によって建物所有者が土地を一定期間利用できる権利のことで、固定資産税の3〜4倍が地代となるケースが多いです。
法定地上権は通常の借地権よりも強力で、権利設定から最低30年間は立ち退きさせることができません。
このように借主の権利が強く保護されていることから地代の設定で揉めることも多く、当事者間の協議でまとまらなかった場合は裁判所が地代設定の手続きを代行することもあります。
法定地上権が設定される可能性がある場合、地主はなるべく早くに不動産会社や弁護士に相談することをおすすめします。
底地の地代相場は固定資産税の何倍が正しいのか知りたいです。
底地とは地主側から見た借地の呼び名で、貸している土地のことです。
地代相場は必ず固定資産税をベースに算出するわけではなく当事者間の協議で設定しますが、もっとも地代が安い住宅用地の場合で固定資産税の3倍が一般的とされています。
ただし、この相場はあくまでも目安であって土地周辺の市況や利用用途によって大きく変動することになり、同じエリアの土地でも地代が変わることも珍しくありません。
地代相場を正確に知りたいのであれば地主と直接交渉し確認するか、不動産鑑定会社に相談する方法がベストです。
まとめ

この記事では、借地の地代の計算方法などについて解説してきました。借地権付き建物は安く購入できるメリットがある一方、借地の地代を支払い続けなければいけないため、中長期的に所有する場合には多額の費用がかかってしまいます。
そこで、借地権付き建物は売却を検討してみてもいいかもしれません。空き家パスは、借地権付き建物の買取にも対応しております。どこに売却の相談をしたらいいか分からない方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
空き家の買取なら空き家パス| 東京・埼玉・愛知・福岡など全国対応のTOPへ戻る


この記事の監修者 高祖広季
株式会社ウィントランス 代表取締役 高祖広季
空き家パスを運営している株式会社ウィントランスの代表です。日本の空き家問題を解決するため空き家専門の不動産事業を展開中。「空き家パス」と「空家ベース」というサービスを運営しています。これまで500件以上の不動産の売買取引に携わってきました。空き家でお困りの方の力になりたいと思っています。